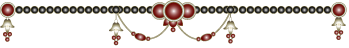甘美な夜間飛行の夢に酔いしれて、目を覚ました時
傍らに立ち自分の寝姿を見守っていた存在が、見慣れた男のものではないことに
モリガンは気がついた。
それはどこかで会ったことのあるような気もするサキュバスの少女だ。
引きつけた欲望の視線をしっとりと受け止めて呑みこむような妖艶な体ではなく、
みずみずしく跳ねるような輝きが邪な視線を肌の表面で弾きかえす無垢の勢いがある。
一見して自分と同じ種族とさえわからない陽の明るさを放っているようにも思えるが
一人佇むその姿には隠しようもなく滲み出る魔の翳りがあった。
「いい夢を見てお目覚めのようね。昨夜はどこにお出かけだったの。
ひどいわ。寂しかった。あなたのために待っていたのに」
まだ気怠い余韻に浸っていたい気分なのに、少女はつぶらな瞳に幼い媚を含ませて
モリガンをじっと見つめている。
「ちょっと夜の散歩を楽しんだだけよ。お腹も空いたし…。
ところであなたとはどちらでお会いしたのだったかしら。随分お久しぶりのような気がするけれど」
「ごまかしてもだめ。あたしには分かる。誰かとつきあったりしないで。
お食事に行くのは仕方がないけれど、違うでしょう、昨日は。
しかも、あたしのことを覚えていないなんて……。あたしは忘れたことがないのに。
その体はあたしのもの。渡さない。誰にも。触らせたくない」
この少女は少しおかしいのではないか。
自分がいつか気まぐれに誘惑してそれっきり忘れてしまったのだったか?
勝手に自分の美しさに嫉妬して妄想の世界に入り込んでしまったのか?
「なに言ってるの。私が誰と何を楽しもうと私の勝手よ。あなたには関係ないでしょう」
「イヤなの。あなたが他の男のことを考えているなんて。許せない。
忘れられなくさせてあげたい。どうしてあたしじゃだめなの?
あなたのために、あたしは待っていたのよ。気が遠くなるくらいの時間をずっと一人で。闇の中で。
お仕置きをしてあげたい。我慢できなくなるまで。泣いてお願いするまで」
地団駄を踏む子供のように唇を噛み、震えている。握り締めたその手を見た。
きれいな手だ。つるりと白くて、小さな爪。他人の内側に触れたことなどないだろう。
純粋な瞳。心の内側にも触れたことがないに違いない。
だから無邪気にわがままで残酷なことが言えるのだ。
「あなたは誰なの?」
「あたしはあなたよ。モリガン」
「あなたの名前は?」
「わからない。リリスと呼ばれているけれど。でもあたしはあなただから。
ねえ、モリガン。あなたをちょうだい。あなたのその体をあたしにちょうだい」
「どうして、この体が欲しいの?」
「そこがあたしの場所だから。渡したくないの、誰にも」
「リリス、私は誰かのものになんてならないわ。安心して。
大丈夫、あなたはこれからも、もっともっと綺麗になるわ。美しいサキュバスになったら、
怖いものなど何もないの。崇められて、男がみな跪いてあなたの許しを待つようになる。
気まぐれに視線を投げかけて、溜息をついて見せればいい。全てが思いのままよ」
「それで……楽しいの? あなたは満足?」
「もちろん、楽しいわよ。毎日毎日最高の気分よ」
そう口にした時は虚勢ではなく、本当にそう感じられた。それほど上機嫌だった。
己が玉座の寝台で、髪をかき上げ物憂げに微笑んでみれば目を閉じなくても感じられる。
かしずく無数の崇拝者たちの熱い視線と切ない吐息が、彼らの捧げる最期の迸りが。
この少女も私を望んでいる。誰もが私に憧れて私を欲しがっている。
その上に君臨する日々は歓びに満ち溢れ本当に素晴らしく楽しいものだ。
流れる前髪の間から、心の深淵を覗き込むように冷静な瞳がモリガンの驕慢を刺した。
間近で見るその目には少女の姿に似つかわしくない、虚無と嗜虐の狂気が宿っている。
「楽しいわけないわ。あなたは虚しいはず。心が空っぽで、いつまでも充たされない。
ねえ、なぜだか分かる? あたしたちは二人で一つだったのよ。
あなたがあたしの半身。あたしがあなたの半身。
引き裂かれたままだから、心も体も切なく激しく呼び合っている…」
つややかな唇が近づいた。少女の声が低くかすれて妖しい興奮を示している。
「あたしが、あなたを満足させてあげたい。もう他のものなど何もいらないと思えるように。
ちょうだい。あなたを。ねえ、いいでしょう。モリガン。もちろん……あたしは、
あなたのその体が、どんなものも拒んだりしないことを知っているけれど」
何かに憑かれたように熱を帯び始めた瞳に見つめられて、胸に感じたことのない種類の戦慄が走った。
「ねえ、触ってもいい? この手で、あなたに」
その手がモリガンの答えを待たず、肩にかかった乱れた髪を一筋、摘みあげる。
何かを言おうと口を開きかけたとき、少女の唇が押し付けられた。
今までに知るどんな感触よりも柔らかい。
わずかでも力を加えたら溶けてはじける泡と消えてしまうのではないかと思うくらい
呼吸も止まるほどにはかない接吻だった。
「……いいわ。いらっしゃい。感じさせて。もっと」
「その気になってくれた? あたしがどれだけ待っていたか。思い知ってほしい、あなたには」
この私に駆け引きを挑もうなんて二百年は早いのだ。
でもかわいい子のゲームにつきあって可愛がってあげるのは嫌ではない。
「ああ、ねえ。早く。思い知らせて欲しいわ」
はっとした表情を少し曇らせて困っている。かわいい。楽しい。
その困惑が、やはり年相応の少女らしさを際立たせている。
「どうやって楽しむの? 教えて。リリス。あなたの言うとおりにするから」
「あたしのものになってくれるの」
「なるわよ。楽しませてくれるなら」
「あなたが泣いてお願いすることになっても?」
「あら、本当なの。どきどきするわ。ほら確かめてみて」
体を覆っていた敷布をはねのけ裸体を露にして誘う。
リリスは戸惑ったようなあいまいな笑みを浮かべたまま、
生々しい獣の爪痕から目を逸らすようにしながら望んでいた体に手を伸ばした。
迷わずに中心へと進む。幼く見えても快楽を貪ることには躊躇しないのが生まれ持った特性なのか。
「……もう濡らしてるなんて。信じられない」
「あなたがあんまりかわいいからよ。言ったでしょ……いいのよ。早く来て」
「だめ。あなたは勘違いしている。そんなに誰でも受け入れられる体なんて。
他の男の夢を見て濡れていたんでしょう? 嘘をついて。恥ずかしくないの?
こんなになって、本当に何でも誰でもいいはずない」
黙って笑う。内心では舌打ちをしたい気分だ。手間が掛かる。恥ずかしがってみせたり、
好きよ、あなただけ、とか言わなくてはいけないのか。サキュバスのくせに。
これ以上つまらないことを言うのなら、私は構わないのよ。こちらから犯してあげても。
「ふふふ、くるの、こないの」
「そんなふうに、相手を征服することしか考えてない。かわいそうなモリガン」
「なんですって」
ふいに乱暴に指が開いた。
あ。
すかさず身を反らせて応じる。そうそう、その気になってくれればいいのだ。
余計な言葉でこの純粋な欲求を澱ませることはない。
そうだ。内なる衝動をどこまでも駆り立てればいいのだ。
誰が相手だろうと、闇を解き放ち、研ぎ澄まし、極めていけば望みのものが得られる。
気づいた時には常に相手のほうが堕ちている。それだけだ。今まで通り。
「あぁ……リリス、早く。もっと。そうよ」
最初の波は自分から動いて掴んだ。いい。気分が高揚する。感覚に浸っていれば。
「ちょっと、こんなにとろとろになって。自分からいっちゃうなんて。だめだっていったのに」
「だってもう……待てなかったのよ。焦らさないで」
瞳を潤ませ乱れた呼吸で語りかければ、堕ちない相手などいない。
「大丈夫。何回でも楽しめるわ。撫でて。優しく。もっと私を燃えさせて。簡単なことよ」
あなたにもできる。そう、シルクハットを投げ上げて楽しいショーの開幕を告げ、
リズミカルな動きで正しいスポットを極めさえすれば超完璧、百点満点のエクスタシーが得られる。
たとえそれが人形遣いの陰鬱な罠だとしても、何を構うことがあろう。
「あなたは何も分かっていない。
お願い。あたしのことだけ考えて。欲しくて欲しくてたまらなくなるまで。
そこらに転がっている、スイッチをいれてやればいつでも起動して使える相手とは違うの。
たった一つの、大切なものとして扱ってくれるまで。あげないから。ゆるしてあげない」
少女の目には涙が浮かんでいた。
「わかったわよ。かわいいこと言うじゃない。それでどうすればいいの?」
「モリガン、あたしを想って。一度でいいから、本当に感じようとしてみて。あたしだけを」
こんな純情に触れるのも久しぶりかもしれない。
ああ。その妄執が私を潤す。激しく切ない満たされない思い。
熱ければ熱いほど激しければそれだけ、甘く美味に私を蕩けさせてくれる。
心なんて、愛なんて、もらっても求められても、それだけでは重くもたれて
もてあますばかりだけど、思い入れこそが火柱を高く上げるきっかけになることもある。
無粋な糖衣で包んでやらないと、官能の劇薬を取り扱えない相手もいるから。
「あたしは、あなただけが欲しかったのよ。モリガン。ずっと。
他のものには代えられない。他のものではだめなの」
――本当は、そういう情熱を知らないわけではない。
あの遠吠えが聞こえるような闇に
狂うほどに猛っている私の内にある渇望。
あなたが欲しい。あなたの全てが。
その名だけを呼んで渡る、いつまでも明けない幾つもの夜を、
知らないわけではない。
もっと。私を求めて欲しいの。あなたの全てを奪いたい。
私を狂わせるただ一人。愛してるわ。あなたを、あなただけを――
愛してる。……そう言ってみればその言葉でもまずくはない、気がしなくもない。
だが実際にはそれだけでは到底追いつかないほど残虐な衝動だ。自分の内にあるものは。
何かで包みたくなるような。
*
少女の指が遠慮がちに触れている。その想いをどうしていいかわからないのか。
そのためらいが、微妙な動きで、あたかも手練の技巧のようにも思えて身じろいでしまう。
その隙間をなぞって。いい。けれど、ちょっとのことで、すぐに昇り詰められるのに。
何度でも達することができる。そこから繰れば、たちまち溢れて指を濡らし、
その先の迷宮へと誘う道が伸びているのがわかるはず。教えてやったほうがいいのだろうか。
なんとか、こう。指を絡めて、身を捩ろうとする。と、強い力で押さえつけられた。
ためらいではなく、焦らされているのだということに気がついて愕然とした。
「だめよ、まだ。あせらないで。あたしのやり方で愛してあげたいの」
その手のひらが、押し付けられたときに快楽の芯に触れる。
ゆっくりと引き出される指先の一点を、襞が波を立てて追いかけてそこに寄り添おうとする。
差し伸べられた、無知な王女の指にほんの一瞬でも触れてみたいと願う崇拝者たちの蛇心。
それが舌先を長く伸ばして、唾液を滾らせている。
もしもその手を掴むことができたなら、二度と放さず引き倒す勢いで
あさましい欲望を露に、ただ一本の指をしゃぶりつくしている。そのまま折ってしまいそうなほど。
「うふふ、あなたが欲しがってる。こんなにも。
いいでしょう? あたしが気持ちいいでしょう。もっと感じて。ほら」
引き出されたときに、冷たい空気に触れる。その空白がもう待てない。
「んん、そこよ……リリス、そこ……」
「欲しいの? あたしが。うれしい。もっとあたしを欲しがって。お願いって言ってみて」
身の程を知らない愚か者なら即座に寝台から蹴り落としてやるのが相応しい台詞でも
涙をためた瞳に見つめられて自然に応えられた。
「リリス、あなたが欲しいわ。お願い。来て」
少女の柔らかい唇が、じわりと染み入っていくようにその部分を押し広げた。
内側に、音を立てた接吻のような軽い力が加わる。
優しく尖らせた舌先で際に沿ってなぞられて一気に開花するのがわかる。
その温んだ舌の水面に浮きながら花びらの快感がとりとめもなく漂う――
――あ!
中芯を吸い上げられて、指先まで鋭い痺れが走った。
一瞬のわずかな時差があって刺激が尾を引く快感になり全身に染み渡る。
高い声をあげてしまった。
音を立てて啜り上げられる。続けて漏れてしまう嬌声が、自身の耳に木霊する。
目を閉じて慣れ親しんだ闇に縋りつこうとしても、瞼の裏を激しい閃光が駆け抜けて
持ち直す暇を与えない。薄い唇を軽く掻くように歯が柔らかくあたっている。
中央に気圧の差が生じて、触れ合った粘膜同士が引いたり押したりを際限なく繰り返す。
腰が震え、脹脛が引き攣れる。
もうどのようにされているのかもわからない。
快楽に蕩けた徴が両の目からもじわりと滲み出した。
もっと巧くされたことはいくらでもある。もっと欲情していて感じたこともいくらでもある。
だが、こんなに必死に、自分を求めている相手が
いかせようとするのではなく、屈服させようとするのでもなく、
満たそうとしてする行為の濃やかさが、そのひとつになりたいという思いの強さが、
心までも泣かせ、濡れさせて、無茶苦茶に感じさせる。
「リリス…………い、いわ。感じる。あなたを。あなたの思いまで。感じるわ。
あなたを感じて……泣いてるのよ。わかる?」
「わかるわ。泣いてくれるの? あたしのために。
わかっていたの。あなたが昨日流した涙を。もうあんなふうに泣かなくてもいいのよ。
行きずりに奪い取った快楽で、束の間の勝利に酔って渇きを満たすこともない。
だめよ、吸血鬼なんかに騙されちゃだめ。いつかあの男があなたの体も心も深く傷つける」
指先が震えながら肌の上をなぞっていく。声もその後を追って震えている。
「これは獣がつけた爪の跡。かわいそうに。これはあの男がつけた呪われたキスの跡。
もうあなたを傷つけないで。約束して。いくら楽しくても、気持ちよくてもそれだけ。
あたしほど…あたしほど、思っていないわ。あなたのことを。
モリガン……お願いだから、心なんていらないと、もう言わないで」
涙の滴がぽたぽたと胸に落ち熱く肌を濡らす。
「あなたにいらないと言われたら、あたしは行くところがないの。
消えてしまうしかない。あなたが受け入れてくれなかったら。
あなたの心でもあるのよ。あたしは」
もらい泣きしてしまうかのように更に目の奥と体の芯が熱くなる。
「ああ、あなたの言うとおりよ。その間は忘れていられたの。退屈も。虚しさも。
どうしてわかったの。どうして知っているの。私の心を。あなたは誰なの?どこから来たの?」
「……だから、あたしたちは二人でひとつだったのよ。わかったでしょう。
あなたのうちにぽっかり空いたこの空白を埋めてくれるものが欲しいんでしょう。
してあげる。いくらでも。あたしが、全部埋めてあげる。隙間なく」
あなたを還してあげる。あなたの心を。だからあたしを孵して。あなたの中で。
「来て。あなたが欲しいわ。お願い。私を抱きしめて。あなたをもっと感じたいの」
「わかってる。全部わかってる。だってずっとずっとあたしはあなたが欲しかったんだもの」
涙に濡れた顔を上げてリリスが笑った。そのはかなさに胸が締め付けられる思いがした。
「リリス、お願いだから、消えてしまわないで。消えてしまうものを、私は愛せないわ。
どんなに分かち合っても、次の瞬間には消えてしまうものを、
私だけを取り残して逝ってしまうものたちを、一体どうして愛せるというのよ」
「大丈夫。もう寂しくないわ。ひとつになればもっと強くなれる。あなたもあたしも」
リリスの纏っていた蝙蝠が光を放って四散した。
この誘惑に身を委ねれば、光り輝く愛があなたをもっと高みに昇らせるから。
日に当たったことがないような、透き通るほどの肌。その華奢な体を抱き寄せた。
浮き出た腰骨が当たる。何もかも薄くはかなさを感じさせる。
本当に長い間闇の中にいたのね。あなたは。
自分のうちに広がっていくリリスをただ感じていた。それだけに集中して。
あなたが、引き出してくれる。更なる快楽を。優しく手招きをしているような動きで。
ああ。それに私が応えている。巻きついて。抱きしめて。
親指が充血した部分をくりん、と撫でたかと思うとそのまま縦にして滑り込む。
湿った音を立ててまた内から半透明の液体が流れ出そうとしている。
思わず閉じかけた脚を、強い力で開かれる。
*
「これからよ」
指先を伸ばした手が、奥を目指した。
滑らかさのある男根とは違い、固く骨ばった感触が、思わず締め付けてしまう柔襞に響く。
奥に指先が当たり、入り口がなおも大きく広げられようとしている。
突き当たった指が遠慮なく、弾力を楽しんで暴れる。
「あっ、ぁん…すごい、驚いたわ。あなたにそんなことが出来るなんて、思ってなかった」
「まだこれからよ、あなたなら出来るわ。あたしを受け入れて」
「え…」
行為自体の経験はあっても、少女にされるとは思いもよらない。本気なのか。
本気だった。
「っんん…。あぁ…」
親指の最後の関節に拓かれて、リリスの細い手首を引き寄せ掴んだ時に
ひとつになるという言葉が深い実感を伴った。
その脈さえ感じられる。痺れるような感動を覚えてきつく食い締める。
また目と体の奥底から熱くなり、じんと液体が滲み出ていく。
「リリス……」
「ああ、痛いくらいあなたに掴まれてる。放さないで、もう、あたしを」
「放さないわ」
「そのまましっかりあたしを捕まえていてね」
「…く…ああッ。な…に」
握った拳の並んだ関節で、腰が浮くほどに持ち上げられる。上を向いて突き上げる拳。
全ての指の第二関節が識別できるほどにひしひしと食い込む。
そこだけで空に吊るされた。激しく抱きしめる体もなく、縋りつきよりかかるものもない。
拠り所を奪われて頂点で宙吊りだ。あのかわいい白い手に、私が握られてしまったなんて。
絶好のポイントが次々と、その手に落ちていく。
ぐりっと粘膜が滑りわずかに重心が移動するたびに、気を失うほどの衝撃が突き抜ける。
すぐに背骨が蕩け腰も砕けた。何かに掴まっていなければ、意識も、血管も飛び散りそうだ。
自己の根底から揺らぎ、その手の内で掬い上げられた海底の砂か焼き尽くされた灰のように
流れ落ちて散ってしまう。
「ああっ。ッ、待って…だめ……。そんなふうにされたら……本当に、おかしくなっちゃう。
お願いだから…もうやめて」
「あなたでも、やめてと言うことがあるのね?」
リリスは息を喘がせて、ついに手にした自らの愛の全てを確かめるように
探りながら眺めている。
「あたしには見える。あなたの内奥までが。あなたの源泉が。きらきらしてとってもきれいよ。
あなたが…待ち焦がれているのがわかる。本当は優しく穏やかに満ち足りた時を」
赤い瞳。この眼を知っている。何よりも私を愛し、見守っていてくれる穏やかな眼。
「リリス、……誰なのあなたは。あなたは、私じゃないわ」
ふいに、このまま本当にこの体が自分のものではなくなる予感が背筋を這い上がる。
「やめて…もう、…こわいの」
あたしのモリガン、こわくないわ。
それは、自分で掴むものよ。逃げなくてもいい。
退屈にとらわれることなんかを恐れて逃げ惑っている暇はないの。
あなたが掴もうとさえすれば全てが手に入る。あたしと一緒なら手に入れられる。
だから、行きましょう。来て。あたしと一緒になって。行くと言って。
「リリス、だめなの。また、いっちゃう。でも…」
「でも、いくんでしょう……? いかせてあげる。言うのよ。その時ちゃんと。いくって。フフ」
リリスの瞳の内に、暗い翳りがよぎる。
「言えば……これから、イくと言うたびにあなたは思い出す。この感覚を。
あたしがあなたを縛り付けて放さない。
もう二度とその言葉を口にできなくなる、あたしを思い出すことなしには。
思い出すのよ。その度にあたしを。この手を。この感触を」
伸ばした指先が妖しく蠢く。
すっかり飼いならされてしまった猛獣のように、撫でられた部分から広がる悦びに全身がひくひくと慄く。
「どんな男に抱かれた絶頂の瞬間にも。ここに刻み込まれた感覚が、思い出させる」
「ぁ――。ひどいわ。そんなの、ひどすぎる」
「ひどいのはあなたよ。今まであたしを忘れたきりで。忘れたふりをして刹那の快楽に溺れてばかり。
この中を、こうされて、抉られて、感じている。あたしがあなたの全てを掌握してしまった。ふふ。
もうどんなモノだろうとここまでは届かないわ。ここまで繊細にあなたを愛してあげられない」
「やめて、お願い、もう……」
「ふふ、このままあなたを壊してしまうこともできるのよ。あたしは。
モリガン。あなたを愛してる。
愛してるからこそ壊してしまうこともあると、わかってくれるでしょう。あなたなら。
さあ、行くのよ。あたしと一緒に。そこにまで。あなたに行くと言ってほしい」
「――ああッ、うっ…ン、いっちゃ…ぅ」
「いっちゃう、じゃだめなの。あなたが自分で行こうとしなければ届かない。行くと言って。あたしと」
腰が浮いたままの烈しい突き上げと揺さぶりに、もうまともに口もきけない。
厳しく追い込まれて否応なしに更なる高みを目指す。
支えといえば内を突く拳のみの、寄辺のない玉座が孤高の女王の戴冠を待っている、
そこにまで。
承諾の印に泣きながら頷いた。何度も。
昇り詰めて、落下に転じる前に、ふっと虚空に静止するひとときがある。
絶頂の感覚、忘我の境地が拠るのは果たして
昇り詰めたどり着いた極みの高度なのか。落下する瞬間の速度なのか。
何万回もの記憶をたどっても思い出せない。なんとかしなければ――落下が始まる前に。
このまま行ってしまうのか。支える腕も翼もなく。
「リリス、いいわ……、行く――――あなたと」
待っていたわ。その言葉を。ああ――やっとあなたとひとつになれる。あなたがあたしを吸い込んでいく。
あたしが守ってあげる。モリガン。あなたを。誰もあなたを傷つけたり奪ったりできないように。
誰にも触れさせない。あたしの、あなたのための、この場所には。この至高――
もう誰もあなたに届きはしない。
*
あなたは、行ってしまったのね。リリス。
答えはない。
だが覚えている。確かに言ってしまった。あの瞬間。約束の言葉を。
呼び寄せられるように、城の奥の秘密の間へと向かった。
もう逃げなくてもいい。追う必要もない。全てがここにあるから。私のうちに。
奪おうとするものがくるのなら、それを迎えうつだけ。
美味しいものを楽しんで、美味しいひとときを愉しむ。
魔王と呼ばれても変わらない。私が本来の私になったから。
そう呼ばれたら何かが変わってしまうことを恐れていたのだろうか?
変わらない。
私は何も変わらない。
それでいい。
アーンスランド家当主の証、魔界の権力の象徴である
赤い石の指輪が、その指に嵌められた。全てを掌握する手に相応しい至高の輝き。
手をかざして眺めていると、己の内に湧き上がる力を、突き上げる衝動を、ありありと感じる。
ひとつになったのだ――その力と。