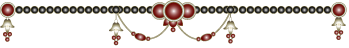近々魔界に拠点を移すという、吸血鬼の城を訪れた。
赤く爛れた色の美しい月が出ている。やはりこちらの世界で見る月は一層綺麗に見える。
全てが震えるような刺激に満ちて感じられるのはどういう心の変化なのか。
色鮮やかな刺激だけではない、以前なら顧みることもなかったような
深々と沁みいるような 穏やかな調いまでもが熱く豊かな潤いをもたらす。
上着を脱ぎくつろいだ姿の吸血鬼。危うい闇の獰猛さよりも、どこか諦観にも通じる端正なたたずまいに
一層の魅力を感じるようになったのもこの身の変化によるものなのか。
「君か。いつ見ても変わらずにお美しくお盛んのようで何よりだ」
皮肉な口ぶりだが、その目が見事な美術品を観たような称賛の色を帯びていることに満足する。
「何なのよ。その気のないそぶりは。遊んであげようと思ってきたのに」
「君のお気に召すような食後酒は……残念ながらもうないな」
「何もなくてもあなたがいるじゃないの。それに今夜はディナーはまだなのよ」
「どうだか…あやしいものだ」
その視線が、自分の手に注がれていることに気がついた。
「気になるの、これが」
「他の男から贈られたものをつけて私の前に現れるとはいい度胸だ」
「うふふ、そうよ。貰ったのよ。あなた以外の人にね。どう、綺麗でしょう?
あなたって見かけによらず繊細なのよね」
「見たところ、君の指には合っていないようだな。相手の男は、まだ君をよく知らないのかな。
あるいは測り損ねたか? 君の……器(サイズ)を」
「繊細じゃなくって、小心者と言い換えてあげてもいいわよ」
確かに彼女の細い指に、魔界を掌握するアーンスランド家当主の指輪は、
今はまだ輪の直径が若干の余裕を残している。
中央に輝く赤い石と、その周りを飾る翼の意匠が大きいので
かろうじて手の甲に正面を見せて留まっているが、そうでなければくるりと裏側に回ってしまうかもしれない。
正式な継承の儀式の後に、指輪は選ばれし当主の指にぴたりと収まるようになるということだ。
吸血鬼の眉間に皺がより、執拗な視線が見えない糸のように彼女の手元に絡みつく。
彼は知っているのだろうか、この指輪の意味を、とモリガンは訝った。
それとも、一人の男として思い人へのありふれた嫉妬にすぎないのか。
「そんなに気に入らない? 時には乙なものじゃないかしら、ジェラシーのスパイスも。ふふふ。
外すつもりはないわ。あなたにはわからないのよ。これがどれだけ大切なものか」
「ふ、本気で言っているのか?」
「そうよ。これは私への愛の証なの。あなたからは得られないものを、他の男から得て何が悪いの」
その言葉の真意を測ろうとするように、吸血鬼の目が瞬きをしてじっと顔を見つめた。
「君のふるまいが、あくまで無邪気なものだと信じて教えてやろう。
指輪にまつわる物語が、常に甘く切ない恋をめぐるものとは限らないことを。
昔々あるところで…ある遠い国で反乱が起きた。早々に反逆者を捕らえた領主は彼に一つの機会を与えた。
手を差し伸べ、その指に嵌められた権力の象徴の指輪に接吻して、永遠の忠誠を誓うようにと、
そうすれば恩赦を与えると言ったのだ」
今でも鮮やかに瞼に浮かぶ、世紀を遡るあの時。
捕らえられた男は後ろ手に拘束されたまま、魔王ベリオールの前に引きずりだされた。
支配者の威厳が辺りを制する中、その静かな怒りが冷たい炎のように揺らめいている。
『デミトリ、分かっている。お前は罠にかけられただけなのだと。
釈明の機会を与えよう。赦しを請い、汝が主君の指に誓いの口付けをして、
変わらぬお前の忠誠心を表し証明してみせよ。されば慈悲が得られるだろう』
魔王の大きな拳が目の前に突きつけられた。
『殺すがいい。悔いてなどいない』
唾を吐きかけてやりたかったが、それには口の中が乾きすぎていた。
あの指に輝いていた同じ石が、今目の前にある――。
吸血鬼の視線が遠くなっている。
「それで?」
「それで、それを拒んだ反逆者は炎に焼かれ、追放されたのだ」
「そしていつまでも幸せに暮らしました……。フフ、面白いお話ね。
忠誠を誓っていたら、きっと即座に殺されていたわけね。でもそれとこれと一体何の関係があるのよ」
出来る限りの無邪気な顔をして聞いてやる。
彼女の悪巧みを、いつも余裕の笑みを湛えて受け止めてきたその目はもう笑っていなかった。
質問には答えず、彼は静かに言った。
「外したまえ。わざわざここまでやって来て、この私に、まだ何か期待することがあるのなら。
その指輪をした君に、私は触れたくないし、触れられたくもない」
このまま、ぴんと優雅に指を反らせた手を差し伸べて、この指輪に誓いのくちづけを迫ったら、
と一瞬考えずにいられなかった。激しい誘惑にかられる。
蕩けそうな笑顔で、甘い声で囁くのだ。『デミトリ…キスして、ここに』と。
一体どんな表情を見せてくれるのか?
気取った色男の顔が苦悶に歪むさま。想像しただけで滴り落ちてしまいそう。
これまでの自分なら迷わず行動に移していただろうが、いつになく寛大な心がそれを押し止めた。
男の誇りはいたずらに挫くものではない。立ててやるべきものなのだ。
「あなたを試したりして悪かったわ。ちょっと妬いて欲しかっただけなのよ」
指から引き抜かれる時、指輪は関節に当たってあの箇所のあの感触を一瞬甦らせた。
「今日ここに来たのはね、あなたの願いをかなえてあげようと思ってなの」
彼が考えを変えればいいのだ、とモリガンは思っている。
時々会うなら最高に楽しめる相手。何も魔王の座を争って果し合いをする必要などない。
そちらもこちらも相性は悪くないし、いい関係を長く保てるはずだ。彼さえ自身の立場に納得すれば。
「私の願いとは気まぐれな君の欲望を満たして差し上げることではないのだが」
継承者の証を身につけてやって来て、言うことがそれか。とデミトリは運命の皮肉を噛み締めた。
からかわれているのではない。
本懐はと問われれば、魔王を倒し、自らが真の魔界の覇者となることだ。
すなわち、目の前のこの女を倒すこと。
この女。
叶わない望みであるただ一人。
全てを賭けても構わない。その女への想いを、自分自身が断ち切らねばならない。
出会ったときからわかっていたことだ。しかし、それがこれほどにも困難になるとは思ってもみなかった。
ただ、己の力を高め、極めれば、届くと思っていた。順調に歩を進めてきたのだ。これまでは。
そこに立ちはだかる壁が、最後の最大の障壁があまりにも高く、
あまつさえ自ら超えなければならぬ情が、気づいたときにはあまりに深まってしまっていた。
それこそが討つべき敵の魔力と知りながら。
肘掛椅子にしどけなく横向きに陣取った女の背後に近寄り、細い髪をかき分けてその項を眺める。
「残念ながら、私は君が考えているほど、物分りがよくはない。
だから、君を時々手にして愉しむだけでは到底満足できない。心安らかでいられないのだ。
跪かせ縛り付けその心までも支配しなければな。こんな私を哀れんでくれるか?」
見るものによっては怠惰にさえ感じられる、満ち足りた優雅なる貴族の物腰に尽きせぬ野心を包み隠しても
心の奥底に燃え盛る執念の炎、煮え滾る情念の焔は絶えることなくじりじりとその身を焦がしている。
もはや噴き上げる憤怒の業火を叩きつけこの身この思いもろとも仇敵を殲滅するしかないのか。
美しく傲慢な小悪魔に甘く心を乱されながら、その髪を物憂く梳いてやる恵まれた紳士を装う自分の手が
その場で全てを打ち壊したい凶暴な欲求に今にも震えだすかと思われた。
そんな葛藤をよそに、モリガンは上をむいてふっと息を吹きだして笑った。前髪がふわっと浮く。
仰け反って、息を吸い込み喉から胸元を張らせ背後の吸血鬼の視線を捉える。
「何で私を縛るつもりなのよ? あなたの魔力? 執念? 愛情…なんて言われてもちょっと困るけど」
一瞬目を泳がせた男を満足げに眺めると、淫靡な本性を現して立ち上がった。
潤んだ瞳、発情した肌がぬめった色香を放つ。その勢いはとどまるところを知らない。
「あなたの秘密の、暗くて甘ぁい欲望を、この私が、叶えてあげたいって言ってるのよ。感謝感激じゃない?
ね、デミトリ、教えて。あなたのしたいこと。あなたと、まだ試してないこと…何か、なかったかしら?」
「私が君に望むものは……そうだな、キスだ。ただ一度、触れ合うだけの」
永遠の、そして決別の。
今夜で、この関係を、想いを、永久に葬り去らねばならぬ。
そしてそれ以降はもうお前は憎き倒すべき仇敵でしかない。
「…キスだけなの?」
「それだけだ。そしてそれが今夜の君とのお別れの挨拶だ」
「あなたって随分ストイックだったのね。驚いちゃうわ」
「見かけによらず、な」
ふふん、と笑った女の唇が、近づく。吐息が感じられるほどに迫ったところで触れない。
目を逸らせたら負けだとばかりに見つめあっていると、
女が小さく舌を覗かせて、考えを変えたように引っ込める。
「君が、私にくれるんじゃなかったのか」
「そうよ、そこにおとなしく座って」
自分の胸を抱きしめるように寄せると、軽い溜息と共に身に纏っていたものが消え、白い肌が露になる。
柘榴の粒を思わせる乳首が赤く血を透かせ、内側の芯の抵抗まで感じさせるように
丸く膨らんでしこり、男の歯に噛み潰されるのを待っている。
鎖骨に沿って舐めるような視線が這う瞬間を意識して、果肉を持ち上げ
彼の胸板の上に載せて差し出す。無言で瞬きをする。その火花で点火しようと。
人差し指が唇をつつく。左右になぞる。ひりつきを感じるほどの間それが繰り返されていた。
「……本当に、キスだけ? ……ねぇ、そろそろ後悔してきた?」
頬を胸の先で突きながら膝の上に座り直し体重を乗せてとどめの圧力を掛けてくる。
「キスだけというのは試してないだろう」
「……」
「モリガン……、君がして欲しいことを素直に言ったらどうなんだ」
その瞬間、下唇にぶつかるような勢いで噛み付かれた。
見開いたままの目に映る怒りがいじらしく感じられる。
やがて鼻腔から切なげな声を漏らすとそのまま、唇が移動していった。
顎を、喉仏をなぞり、鎖骨を越えて、次第に動悸を速める胸を渡る。
間を遮るものをその手が剥ぎ取り、さらけ出された心臓の上を探りながら
更に降りていくにつれ、ずるずると滑り崩れ落ちていく。背もたれに預けた体も精神も。
女の体がやや浮き、わずかに唇が折り返してその先を通る。
そこでしばらく留まっている唇がちゅちゅっと接吻らしい音をたてた。
仰ぎ見た先端に、今度は彼女自身を離さないように
唇から滑らかな首筋、盛り上がった胸、尖った乳首、臍の窪みと全ての凹凸の道を辿らせる。
そこが甘美な逍遥の果てに、脚の付け根にたどり着いたときには、
細く締まったウエストからゆるやかに丸みを帯びた下腹にかけて
まるでなめくじの這ったような粘液の跡がひとすじ残り、光っていた。
細い指がその跡をなぞる。得意げに視線を引きつけて、赤い舌を覗かせ
彼女のものではない体液に濡れた指先を舐めてみせる。
目を逸らさずに見つめ返す、ただそれだけのことが恐ろしいほどの苦痛を伴った。
それでも次の動きを悟ったとき、無駄と知りながら、はかない抵抗をした。
「……よせ、もういい」
決して聞き届けられることのない言葉。しかし声に出して発しなければ、
残された矜持すら軟体動物のごとく溶かされ踏みにじられてしまう気がした。
「キスなのよ。あなたの言ったとおり、たった一度触れ合ってまだ離れない」
「……う」
やはり、無駄だった。
そのまま呑みこまれてしまった。熱く深く苦い極上の泥の淵に。
一気に駆け上がる、女の軽やかな天上の悦びへの足取りが
男にとっては一段一段と下る奈落の重厚な痺れになる。
片膝を立てて開き、濡れて絡み合い喰い合う肉の辺を見せ付けながら揺すり上げても
その部分は完璧な反応を見せているにも関わらず、彼の瞳はどこか虚ろなままで精気を失っている。
手をとって胸に触らせても握る力がない。ペースが速すぎたか。これではだめだ。
全くついて来ていない。本当にその気がないのか。そんなことがあるだろうか。淫魔は苛立った。
湿った体を摺り寄せて仕切り直しを図る。男の乳首に爪をたて、その上に生ぬるい唾液を垂らしながら囁く。
「ゆるして…我慢できなかったの。あなたしかいないのよ。本当に私を満たしてくれるのは。あなたに、
抱いて、欲しかった。こうしたかった。ぁあ、だめ…当たってる…。いい、ところに、あなた、が…、っ」
媚態の一部でもあった言葉に自ら煽られて深部を溶かすうねりが高まる。
声と体を震わせてその胸に縋りつき、内なる感覚に埋もれてその兆しに集中していると
気合を入れたかいあって、ようやく眠りから目覚めたような彼の欲望が追いついてきた。
脚を絡めてその体を上に導く。ゆっくりと感触を確かめるように探られる。
最も大きく内壁を拡げてその存在を主張している部分が、くきゅとしこった音を立てて
中で二度三度と擦れる感覚が目覚めた衝動を急速に押し上げる。
「あっ、っ。いぃ。今の、あっ…ん、今のして」
すかさず急き込んだ勢いで、掴んだ調子を逃さず追い立てる。
男が息を詰めた。
もっと狂わせてやりたい。夢中にさせたい。余計なことは何も考えられないほどに。
息が切れ、意識が途切れても、他に逃げ場もなくただただ私だけを求めるまでに、堕としてやりたい。
主導権を譲り渡した形をとりながら、握った箇所は追撃の手を緩めない。
脳髄に磁力を発して突き刺さるその楔をどこまででも駆ってやる。
「ねぇ、もっと奥まできて? だめなの。もっと…激しく、して欲しいの。あなたに。ね。お願いよ」
もっと、深く深くこの私を貫いて。誰も知らない真底は、あなただけに触れられたい。
口ではなんと言おうとも、彼女のお願いは必ず聞いてくれるのが彼のいいところだ。
いい。もう――。
動きを止められた。
あぁ。ここまできてお預けだなんて、そんな、そんな余裕が残っているとは思わなかった。憎たらしい。
腰を浮かせ、身を仰け反らせて顎をあげた下目遣いにその表情を覗う。
ぞくぞくするほどの、冷たくそれでいて欲情した目だ。それだけでまた溢れてしまう。
「きてよ」
「……」
「はや、く。お願い」
思いきり食い締める。そんな風に言えば期待に違わずじっくりと、
防御不能な真夜中の愉楽責めが、二度とその場に起き上がる気をなくすまで
緻密かつ陰険なまでに繰り広げられるのがまたいいところなのだ。
しかし、今回は彼女の期待の展開にはならなかった。
「違う。私がもう、限界なんだ…、ゆるせ。もう無理だ」
切れ切れに言葉を吐き出すその顔が薄笑いを浮かべているようにも見えて
どこまで本気なのか疑わしい。片目だけが合図を送る時のように細くなり、
閉じた瞼がぴくぴくと震えているさまがたまらなく愛おしい。
その表情にしばらく見惚れていると、やがて決然と赤い双眸が見開かれた。
ゆっくりと抉りだすように動き出し、速度を上げる。
「モリガン、さあ、来い、殺れ、私を。君の望むままに、今、すぐ、絞りつく…せ」
奪うがいい、我が命を。今が最大のチャンスだ。
「ああ、何をいうのよ。大事に思ってるのよ、あなたを。誰よりも。
こんなこと言うのは最初で最後だけど。デミトリ、愛してる、あなたを。心から」
吸血鬼は思わず呻いた。考えられる限りの最悪だ、それは。お前から投げかけられる言葉のうちで。
くっ、何てことだ、もう陥落したのか、私は……。
「……あら、あなたまさか、出ちゃったの。もう、信じられないくらいかわいいわ。
かわいい私のデミトリ。大好きよ。あぁ、あなたのとっても美味しいわ」
胸に抱きしめた。熱い吐息がかかる。汗に濡れた髪を撫でる。
傷のない滑らかな、どこも綺麗な曲線を描いた体が大きな動きを止めて停泊している。
厚くその身を覆っている筋肉が、力を緩めているときには柔らかく素肌に感じられる。
そんなにも力を求めて、それを得て、その体も心も鎧で固めていなければ守れないものが
この男にはあるのだ、と思うとモリガンは切ない気持ちになった。
捨ててしまえば楽になれるだろうに、きっとそうは出来ないのだ。かわいそうに。
あの残虐な焦燥とは別の、汲みきれない思いが湧いている。
私だけのものにしてあげたい。かわいそうでかわいい、私のヴァンパイア。
いつまでもこうしていられたらいいのに。大丈夫よ。あなたなら。まだ終わりじゃない。
*
サキュバスの、ただ一度と交わす接吻がまだ離れることなく続く。その熱い下唇を丸い形にして、
引き抜くときに極限まで鋭く細く、突き入るときに究極に優しくたおやかに。
降伏の白標を一度揚げたくらいでは全く容赦される気配もなく、弱ったところを更につけこまれる。
お前にそうやって弄ばれていると、本当に全てがどうでもよくなってしまいそうだ。
それを恐れていたのに。
今だけだ。こんなことを、閨房の逸楽に耽りきったそぶりで言えるのも。
こうして引きずりまわされて、お前に繋がれているうちにしか、言えない。
――逝かせて欲しい、ここで、このまま。殺してくれ、その手で。
夜毎お前が見せる悪夢の中でと同じく錯乱のうちに懇願し喘いでいる。
だがそれが本心なのだ。愚かな私の。
こんなざまで、どうして支配できるなどと一時でも考えたのか。
身も心も自分自身が摩りつくされてしまうだけなのに。
こうして我が意志も圧し潰されていくのか。こうしてはぐらかされて。
自分は既に、全てを賭けて死ぬに相応しい最適の時期と舞台を逃し
長い間そのことに気がついていなかっただけなのではないかという底知れぬ絶望と恐怖に捉われる。
「頼むから、もう逝かせてくれ」
「どうしちゃったのよ、そんなに甘えた声をだして」
たわいない睦言に、ただならぬ気配が色濃くなっていくのを気づかないふりをした。
「本当に、限界だ、頼む、もう耐えられない、なんでもきくから、君の言うことはなんでも……」
「なんでもって……あなたは、全てを私にくれるのかしら」
「とうに、全て君のものだ」
「支配したいの? されたいの? どっちなのよ」
赤い瞳が潤んでいる。
「奪うがいい……。奪え、今ここで、私の全てを、この命も」
あなたがそんな顔をするなんて。自分からそんなことを言うなんて。柄にもなく胸が痛んだ。
「まだ余裕があるんでしょう。ねえ、呼んで。いつかみたいに。私を。
ちょっと、わかってるの? あなたの魔王の命令なのよ。しっかり目を開いて。
私を見て。聞きなさいよ」
ぐったりした表情の頬を、ばちばちと叩いて目覚めさせてやる。ちょっとふざけた口調で。
そうでもしないと自分が泣いてしまいそうだったから。
顔を叩いている細い手首を掴んだ。その手のひらに口付けると
掴んだ手首がぶるぶると震える。
「ああ、そんな顔をして微笑むな。ゆるしてくれ……。
モリガン、モリガン、モリガン、後生だから、逝かせて欲しい。
このまま。この手で。もう解放してくれ。私を。このくびきから。
君が魔王になるのなら、私は君を永遠に失ってしまう…」
あの指輪の嵌められていた中指を噛む。
失う? 自分で口にしておかしい。手に入れたこともないのに。
今この指を噛み切ってしまうこともできないのに。
馬鹿げている。本当に。もう無理だ。これ以上は。この馬鹿げた関係を続けることも不可能だ。
今夜体を離したらもう二度とお前を抱きしめることはない。
モリガンはぞっとして掴まれた手を引っ込めた。
決して色恋沙汰などに収束されない、この男の最も暗い執念と嫉妬を見たという思いが
噛まれた指と心とを疼かせる。
「そんなことどうでもいいわ。でしょう? どうでもよくないの? あなたには。
私は私なのよ。魔界のことなんて関係ない。どうでもいいって…言ってよ!」
「魔界自体はどうでもいいのかもしれん。が、その統率者はどうでもいいことではない。私には。
私が悪いのだ。君に惑わされた。それが間違いだ」
「間違いじゃないわ。誰もが私に魅かれ、私を求める。当たり前みたいなものよ」
「間違いだ…」
その後は決して言えない。間違いだ。不覚にも、のめり込みそしてこんなにまで……。
自分を見失い、泥沼に溺れながらこのままの生を送ることに自分自身が耐えられない。
何かを賭けて闘っていなければ。
生きる意味を失い、なお永遠の命を保つ暗黒を、ベリオールは知っていたのだ。
野望に、復讐に、再起に、心を燃やしていなければとても耐えられない。
志を挫かれ、腐り、自滅の道をたどった者がどれだけ多いことか。
自分の運命はそれとは違う、と信じていなければとうに朽ちている。そのまま、お前を倒せばよかった。
もう、わかっている。お前を倒すことが自分には出来ないと。必要な力も意志も欠けている。
それだけなら、勝負を挑み早々に敗れ去り、敗者の烙印を謹んで拝受するのみだ。
だが、愚かにも、お前に惑わされて。こんな誘惑にさえ打ち勝てない。
そのことを持てる実力が発揮できない、お前が倒せない理由に理性がする。
感情がお前を失うことの恐怖を見つけ、本能までも闘いに躊躇を覚え淫靡な刺激に溺れきり…
納得しようとしている。無意識のうちに。自分の心が自分にブレーキを掛けて落とし所を探りだす。
甘んじてこの生を、この屈辱を受け入れようとしている。
卑しく…軟着陸の生温さに己が魂と誇りが朽ち果てようとも。
間違いだ。
お前が魔王となり、お前に遊ばれて喜びさえ感じ、何のために生きながらえようというのか。この私は。
到底許せない。耐えられない。そんな結末のために私はここまでやってきたのではない。
だから、
「もう殺してくれ。モリガン。私を。
君に殺されたい。他の男たちのように、無慈悲に蹴り殺されればそれで足りる」
逃げといわれても、卑怯といわれても。でなければ……
やはり私がお前を倒すほかはないのか――。
お前を失う苦しみか、私自身を失う苦しみか。どちらかを選ばなければならぬ。
これが罰なのか。私への。貴様への復讐心を抱いた罰か。
堕落に誘う淫魔を後継者に選んだ貴様の狙いは冴えている。感服するほどに。
そんなことを言うなんて。…あの、あなたが。
殺してくれ。それがこの男にとって最果ての、それでも自分に対する愛の言葉なのだ。
その顔に浮かんだ覚悟を見てしまった。その運命を。
デミトリ、この私は、いらないのよ。魔王の称号なんて。そんなもの全然望んでいないのよ。
と、きれて叫んでしまいたかった。だがそれを言ったら全ておしまいだ。
彼は既に復讐の機会を永遠に失ってしまったのだ。ベリオールが斃れた時に。
私では……だめなのだ。おそらくは。私を倒したところであなたが満たされることはない……。
それを無意識にでも知っているから、そんなにも苦しむの?
私の存在があなたを狂わせる。決して甘い夢ではなく。
あなたの理想と誇りを打ち砕く。私の望まない形で。
いつかこうなるとわかっていた気がする。だから闘いは避け続けてきたのだ。
先送りにして、今だけを楽しんで、その瞬間だけに燃え上がり
見なくていい宿命なら、目を逸らしたまま終わりまでいけると思っていた。
もう戻れない。
私が終わりにしてあげる。この因縁を。あなたに出来ないのなら。
あなたがあなたらしくなくなっていくのは、もうそんなあなたは、こんな運命は、見ていられない。
「デミトリ……。キスして、ここに。
私に証明してみせて。あなたの、永遠の愛と忠誠を」
赤い瞳が見開かれ、凍りついたように萎縮する。
「……そんなものを今更どうしようというのだ。まだ弄り足りないのか、私を」
「奪ってあげるわ、お望みどおり。だから見せてよ。あなたの全てを」
抑揚のない彼女の声だった。冷酷な支配者ではなく、追い詰められて最後の抵抗をする獲物の。
何を恐れる、お前が。
私の言葉か。それがそんなにお前を動揺させたのか。嘲笑って絞りつくすことも出来ないほどに。
その唇が震えている。怯えているように……。
急速に冷静な意識が戻ってきた。その身を引き起こし、強張って添わない体をなだめるように抱き寄せる。
「それが……、それが、本当に、君のして欲しいことなのか、ん?」
その行為の意味するところをお前はまだ知らない。
「そうなのか?」
モリガンは黙って微笑んでみせようとした。
平手打ちを食らわせて舐めきった態度を糾弾し、やっぱりふざけてみただけなのだと、言わせようか。
蹴り倒して、煽ったら本気で殺しあえるだろうか。
どれも上手くいきそうにない……もう溜まった涙が零れ落ちてしまう。
「してくれないの? おねが」
「言うな」
優しく抱きしめられる。瞼に唇が触れ、眉をなぞり、目尻にたまった涙を吸いとっていく。
「…それが君の望みなら、喜んで従おう……だが、君を…後悔させたくない。
君を、失いたくないのだ、私は」
「放してよ。後悔なんて、するはずないわ。私を何だと思っているのよ。
それともあなた自信がないのかしら、期待はずれと思われるのが怖いの?」
昂然と顔を上げ、自信に満ちた淫魔の態度で挑発する。
「あなたの全てを、味わわせてよ、私に」
でも、涙声になってしまった。あなただけは消えてしまわないと思っていたのに。デミトリ。
出来る。せめて最後に、その誓いがあれば出来る、私には。あなたを奪い、終わらせることが出来る。
吸血鬼は、やっと笑いを浮かべた。見たことがないほど情の込められた優しい笑みだった。
「わかった。いいだろう。……味わえ。この私が君に捧げるくちづけを。こころゆくまで愉しむがいい」
お前がそう言うのなら。その意に従うことこそ我が喜び。
下された罰を受けることに今更何を躊躇うことがあろう。そうだ。ここまでやってきたのはそのためだ。
己が定めをもう恐れはしない。貴様もだ。その権威ごと打ち破る。そして全てを手にする。
全てを――お前もだ、モリガン。決して失いはしない。
一瞬だけ唇が触れ合った。そんな風にしたことは確かになかった。
耳朶を甘く噛まれ、堪え切れない思いが溜息になって漏れる。
その声に反応するように、肌に触れた唇が震えるのがわかる。
感じられる。面と向かってはついに発せない言葉を告げているのが。
その心臓の鼓動が、感じたことのないほど高まっているのが。
なぜわかるかといえば自分も同じだからだ。デミトリ…。私自身が今初めて気がついたけれど、
こんなにもあなたを愛していたわ。ずっと。はかなく移り気な夢の分際で。
そう言ったら、あなたはどこまで信じてくれるのかしら。嘲り、鼻で笑い飛ばしてくれるかしら。
思い上がりの自信家の顔を取り戻してくれるかしら。
微かな声で呟いてみる。私もよ、私もあなたを…。
聞こえただろうか。
聞こえていたに違いない。一瞬彼の動きが止まるのを感じたと思った。
腕の中で強くしっかりと体が支えられているのに
その指先は壊れやすいものを大事にそっと扱うような軽い力で肌を撫でている。
そうだった……、この冷たく優しい手は数多の血に染まり、
とりわけ多感で脆い品種の取り扱いには長けているのだ。
温かい唇が首筋に触れている。限りない繊細さで。
この感触。全身のあらゆる場所が知っている。この感触を。
触れられなかったところはない。どんな小さな部分にも。全ての感覚が甦るような気がする。
その唇がこの身に触れた瞬間のひとつひとつが、その味が、一斉に開き薫りたつ。
甘い記憶に皮膚を覆いつくされて息が詰まり、気が遠くなる。
個々の感覚に自己の存在が分断されて、その一片一片が
愛しい男に所有され、占められて、埋め尽くされていた、窒息しそうなほどの恍惚感。
その感触が呼び覚ます、ひとつに結ばれていた幾夜の記憶は
こうしていつかまた細切れになって散っていくのか。
やがて、
そこに熱を感じた。
そして鋭い尖端を。
ああ。
それが欲しかった。
何よりも。
あなたのそれが、ずっと欲しかった。
処女は待ち望んでいるのだ、その味を知らなくとも。
圧倒的な力に破られて血を流し、己の全てが拉し去られる瞬間を。
私の吸血鬼。連れて行って。もっと高みに。私の知らない永遠の果てまでも。
連れ去って。彼方に。未だ味わったことのない悦びの極みに。私のデミトリ。
それこそ私が求めていたものだから。
もうその姿は優雅な貴公子のものではない。赤い瞳だけが光る黒い魔の姿だった。
愛おしい、変わらぬその声が祈るように囁いている。
「我が宿敵、私の運命の―致命の女、モリガン、君に捧げよう、私の全てを。
受けるがいい。最後のくちづけを。我が永遠の忠誠の証、そして君への果てなき愛の証だ」
滑らかな皮膚に鋭い牙の一撃が下された。