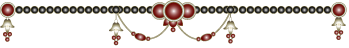最初の瞬間から、想像を絶する鮮烈な快感に襲われた。
心臓の一打ち一打ちごとに、今までに知るあらゆる快楽の頂点を越えていく。
激しい戦慄。
こんな……。
こんなに素晴らしくも恐ろしい感覚があるだろうか。
これまでに感じた全てはこの瞬間のための前奏であり前戯でしかなかったのかとすら思える。
出せる限りの叫び声を上げた。上げたつもりでいたが、実際はわずかに開けた口の
唇の端から唾液と混じり合った血が垂れ落ちただけだった。
かすかな声も出せないまま、涙が迸り出た。魂の奥底から飛沫をあげて熱い潮が噴き出す。
体が、己を形作り支えていたものの全てが決壊していく。輪郭も溶け崩れ、鼓動とともに蕩け去る。
どんなものにも代えられない、あなたが、私の中にいる。私が溶け出して吸い出されている。
強く抱かれて、このまま吸い尽くされてしまうことだけを願った。このまま。
いつまでも続くこの至福。もう今が、この瞬間が永遠の、目眩めく悦び。
真の絶頂は高度でもなく速度でもなくこの密度だったのか。
全てが響きあい、充ち足りて揺蕩っている。
あなたに、包まれて。ああ、いい。もう、これで。いい。
もっともっともっと強く抱きしめて。ああ。放さないで。このまま。
よすぎて、いきすぎて、もうどこにも戻れない。どこへだろうと戻れなくていい。
いつまでも。
その血を味わうことは、無意識のうちに自ら科した禁だった。
最後の誘惑。それを領ったら、もうその先などないと分かっている。
腕の中でその体が慄く。甘い匂いが立ち上る。
数多の女体が髪を乱し肌を震わせて断末魔の歓喜に悶えるさまを感じてきた。
お前ほどの女でも、そうして震えるのか。か弱い生贄と何も変わりなく。
食い込ませたまま、脈打つ熱い流れを感じながら、しばらくは吸い上げることができない。
口の中に温い塊が溜まっていっても眩んだように知覚が竦んだままだ。
その液体に、お前の持つありとあらゆる官能が込められている。それを味わったら最後だ。
――なんという……。
一瞬にして正体を失い全てを奪われ崩れ落ちてしまいそうになる。
もう、何もいらない。ひとたびそこに至り溶け合ってしまっては。
お前が脈打っている。私の中で。お前を感じる。
お前はもう、掴んだと思えば飛び去り白日の光に散っていく見果てぬ闇の夢ではない。
この手のうちにあり、抱きしめればいつでも感じられる。
心地よいリズムで駆け発っていってはこの胸に必ず還ってくる熱い波音、
私に唯一無二の歓びをもたらす血肉。
お前の血の官能の上に我が永遠の調べは奏でられ、二度と途切れることはない。
私はもう滅びはしない。甦りもしない。私がお前の中に溶けてしまった。
お前は私のものだ。私だけの。放さない。どこまでも。
お前を手に入れた。モリガン。
……ついにお前を。
震えが治まり、唇を離す。力の抜けた体を抱き起こす。
「私が、わかるか?」
「……あなたよ。デミトリ」
「そうだ、君の…、お前の、あるじだ。
こちらを向いて、見せてくれ。私の虜となった顔を。
ああ、ゆるせ、モリガン、君を失うことはできなかったのだ。
この不滅の命を授ける。我が僕、我が…最愛の妻として永遠の時を生きよ」
この契りを永遠のものとするために
私の愛と忠誠が呪いのようにお前を縛りつけ二度と放さない。
モリガン、お前自身が望んだことだ。お前が目覚めさせた。その…報いだ。
蕩けた顔。涙に濡れた頬。我を忘れた虚ろな瞳。
だが、その言葉ははっきりと響いた。
「もう…いいわ。デミトリ。もう充分なの。いらないの。永遠の命なんて。そんなものはもう」
おとぎ噺の眠る姫は王子のくちづけで目覚めるのを待っている。
たとえこれまでが夢まぼろしで、これからが目覚めて生きる現実であったとしても、
いや、だからこそ、そんなものはいらない。いつか飽きるだけ。退屈してしまうだけ。
そもそも、私という存在が夢なのだから……
これから無限に続くであろう時間は、永劫の苦しみに違いない。
そんな牢獄に閉じ込めないで。私は何ものにも縛られない。誰のものにもならない。
私は全ての男が見る、闇の中の刹那の夢でいい。
「この血を、命を……これが、私の全てだ、全てを捧げるのに、受け取れぬというのか。
なぜだ。君の為なら、全てをくれてやる。私の全てを吸い尽くすがいい。
私の限りなき誓いを受けてくれ。この血を、飲むのだ」
「もう、いいのよ――真夜中の愉しみは、味わい尽くしたから」
女は微笑を浮かべ、固く唇を閉ざした。
その瞳が光を失っていく。
だめだ――応えてくれ。絶対に許さない。
どんなに拒もうと、必ず、無理矢理にでもこの精血を叩き込み
我が意志をお前の内に受胎させてやる、とデミトリが半ば絶望的に心を決め、
手をかけた瞬間、その肌が石に変貌していった。
サキュバスの最後の涙が零れ落ち頬を濡らす……その涙を味わおうとしたが
舌にざらりとした冷たい石の感触だけが残った。
自らの欲望に屈し滅びていく者、おまえもまたその一人。
とその顔が、慈愛に満ちた微笑で告げているように、デミトリには感じられた。
あの高笑いさえ響かせて。石に変わった涙の滴が床に落ちて乾いた音を立てた。
*
モリガン、遠い昔、私が弱い人間であった時代にもしもお前と出会っていたのなら、
一夜の夢にこの命を捧げて、私は幸福であっただろう。名も無き生贄の一つに過ぎずとも
その至福に狂喜して服従しただろう。信じて欲しい。その気持ちに変わりはなかったと。
だが、そうはならなかった以上…、この私だけがお前に与えることのできるものを与えてやりたかった。
恨むなら恨め。憎むなら憎め。いつかお前にもわかる時が来る。
闇のみにあるのではない。私が志向するところは。
再生こそが我が定め。そして全ては永遠のものになる。
だから私が全てを手に入れる必然だったのだ。
ベリオール、貴様は真に偉大な王だった。
闇の旧き秩序の崩壊は我こそにあることを見抜いていたのだから。
最早、統べるべき魔界など必要ない。ただ絶対の、永遠の静謐と調和がそこにある。
私はもう…今までの私ではない。
悔いてはいない。己の選択を。
あの時と同じ――そもそもそれを言うなら、最初の復活のことになるのだ。
ただ、二度と取り戻せないものがあるというだけのこと。
叶わぬ夢などない。
屈した自分があるのみだ。その認識に誤りがあっただけのこと。
それを望むことが間違っていたと。
正しかった。
だがそれを捨てても得たいのは、己が感傷とわかっている。
悔いてはいない。お前の拒んだ未来を私が負うのだ。
闇の貴公子は、名実ともに、光と闇とを統べる帝王となった。
*
「君に、アーンスランドを倒せるとは思わなかった……今でも信じていないがね」
「ジェダ、一つ聞いておきたいことがある。救いを求めていながら…それに気づかぬもの、
それを既に与えられていながら自分が救済されたと思わないもの、
それらを君はどう扱う? 君の救済をついには拒み、理解しないものどもを」
「そのおかげで救われたと思われるようなものは、実際には真の救済ではない。
理解などされなくともよい。はなからそんなものは求めていない。だから同化できるのだ。
君も、同情など願い下げだろう?
ところで…そう、貴君はご存知だったかな。ベリオールがその昔、謀反の企てが発覚した貴族に
ある提案をした逸話を。アーンスランド家に帰属することを誓えば、家名と命を助けてやるという申し出だ」
「ふん、似たような話はどこでも聞くものだな。で、どうなったのだ?」
「帰属を誓った当主に、ベリオールは死を賜った。
……くくく、そうだ。お察しの通り、私だ、その当主とは。忠誠を誓い名誉ある死を魔王より賜った。
どうする? 偉大なる先例に倣い、今この私に下すべき判断をしたほうがよいのではないかな?」
「聡明な君は死なせるにはあまりに惜しい。今のように貴重な話をもっと聞かせてもらいたい。
礼としてこの花を取らせよう。……受け取って、くれるな?」
「ふ。どうせ拒否はできないのだろう――君だけだからな。魔王への誓いを拒否できたのは。
感謝もしないが、恨みもしない。私が以前言った時とこの世の運命は何も変わってはいない。
君の運命もだ、デミトリ。覚えておけ、私の言うことを。情けをかけたつもりでも救いを与えたつもりでも、
咲こうとしないものを無理に花開かせることは出来ない。
心に積もる未練の石を砕くのだ。今のうちに。それが君を闇に繋ぎ、二度と浮かび上がれなくなる前に」
後に冥府の王が自滅していったときにも、帝王はドーマ家の地に薔薇を贈らせたが
ついにその地に苗木が根付くことはなかった。
*
もう夢を見ることはない。
どんな美酒もどんな血もあれほどに彼を酔わせることはない。
あの無限に思える一瞬を味わった後では、
何もかもが、あれほどに望んでいた覇者の栄光さえ、色褪せて見えた。
時折、滅びていった者たちのことを考えることがある。
追われるものの宿命なのか。もう誰も応えるものもない。
我が狂気、我が誇り、我が情熱。
もう夢を見ることはない。
時折たまらなく、その感傷に浸っていたいときがある。
今でもその名を呟くと、あの感触が口内に甦る。
熱く蕩けるような粘りつく甘さ。眩暈のする陶酔。
お前の血が私の体内に今も巡る。
私の律動に応えて響くその脈
おののくその肌
その瞳の奥に瞬く光、
お前の血の一滴までが
わが身にもたらされたその官能の鮮やかさを教える。
それからなのか。憧れだけが激しく募り、満たされることのない渇望と果てしない虚無が、
お前の毒が、私を包む。
私はお前を滅ぼし、お前が私を滅ぼしたのだ、ゆっくりと。
お前か、自分自身か、どちらかを選ばなければならないと思っていた私は
そのどちらをも失ってしまった。
私はもう今までの私ではない。
今の私は、かつて私がそうであったものにすら及ばない。お前を失って。
お前を手に入れようとして自らの夢を破ってしまったのか。禁断の夢を。
魔界などどうでもよい。
魔王と呼ばれても変わらない。私が本来の私ではなくなったから。
お前が――私の全てを奪った。
モリガン。なぜ、なぜあの時この命も奪ってくれなかったのか。
すでに滅びた、この私を。
*
かつて冥府の王が予言した通り、この世界が崩壊する時が来た。
地響きが闇を揺るがし、絶対の光の力を持って目覚めた女の手が迫る。
既に光の世界を奪回されて、闇の帝王には対抗する術も意志もない。
帝王は、城にとどまり、全てが崩れ去る音を聞いていた。
永遠を味わった。悔いはない。もう甦ることもない。
あの石像を眺める。
愛した女の姿。今も変わらない美しさ。ついに手に入れることはできなかった唯一のもの。
自分のつけた牙の痕が石像の首筋にくっきりと残っている。その窪みを撫でる。
あの無限の抱擁。
お前を追っていることこそに意味があった。
どんなに夢見ただろう。持てるもの全てを捧げた。この血も、命も。
それを拒否した女。ついには応えてくれなかった女。
崩れる音がする。また一段、この城を築き上げている石が。
ぱらりと、砂粒がこぼれるような音を聞いた。
石像の項を撫でていた指先に、黒い欠片がついている。かさぶたのようにも見える欠片…。
その時、彼は見た。
手の中の石像が輝きを放ち、甦るのを。
その瞼がゆっくりと開き、静かな光をたたえた湖がきらきらと輝くさまを。
夢か――。
夢なのだ。遠い昔から、これは夢だった。
それ自身が夢だった。
「…デミトリ」
その唇が彼の名を呼ぶ。その両腕が、彼の体を抱きしめる。
そして、封印されていたもう一組の腕が、優しく頬を撫で彼の瞼に触れる。
吸血鬼の赤い瞳が、その指に嵌められた宝石の煌きを映して光る。
「眠りにつくがいい……我が忠実なる僕。
……私のデミトリ、いつか…お前にもわかる時がくると思っていた」
穏やかな威厳に満ちたかの声を聞きながら、
その手をとって口付けると、デミトリはゆっくりと目を閉じた。
魔王の黒い翼が崩壊する城から飛び立つ。光との闘いに備えるために。
闇の世界を侵食する曙の光に照らされ、魔王の腕に抱かれた吸血鬼の体は灰になって散った。
2005.12