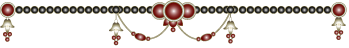満月の夜に遠吠えが木霊している。
あれは誰かを、何かを求めて呼ぶ声なのか。
なぜ狼はあんなにも哀しげに闇の中で咆哮するのだろう。
その孤独に耐えられないからか。
そこに生きていることを、その存在を、知らせたくて声を張り上げているのか。
応えるのは、木霊ばかりなのに。
あれと、私は同類なのだ。
夜に抱かれて疾駆し、裡に広がる底無しの黒い闇。
その渇望に衝かれてあてもなくさ迷っている。
私は全ての男が見る夢。でも牙を忘れたものに私を夢見る資格はない。
愛しい、あの男だけが、私を満たすことができる。
誰も知らないのだ。
どんなに激しい衝動がこの胸を灼き、求めているかを。
誰も、まだ知らない。私の全てを。
私に愛された者はその運命を呪うだろうか?
また、あの遠吠えを聞いた。
いつの満月の時か、その叫びを聞き、その姿を見たことがある。青い毛並みの狼だ。
声に引かれて、荒野までやって来た。
雲が月を隠し、吸い込まれるような一瞬の沈黙の先に
その影を見た。
すかさず追っ手の蝙蝠を放つ。だがたちまちのうちに千切られてしまったようだ。
遠吠えの木霊を長く引いて、閃光が遙かに遠くなる。
速力にかけて引けをとるつもりはない。
モリガンは地を蹴った。
宙に身を躍らせ、鋼鉄の翼を開く。唸りをあげるエンジンが炎を噴いて加速する。
夜の空気が渦巻き、摩擦と狩りの興奮が素肌を焼く。
速く、より速く。
決してとらわれることのないように。退屈が追いつかないほどの彼方にまで。
こうしてスピードを上げて、自分は一体何を追っているのか、何から逃げているのか。
考えてはいけない。もう。あとは興奮の渦に飛び込むだけだ。
「誰だ。なぜ、俺を追う」
足を止め、振り返った狼の眼は、いつか見たものとは異なっていた。
哀しみを湛えた苦渋の表情ではない。超えたのか。どうやって?
疾さを極めれば振り切れるのか。
闇に呑まれることなく、その体は薄い光を放ち輝いている。
一歩近づいた。
閃光が走った瞬間、鋭い爪が肉を切り裂き
気がついたときには地に倒されていた。生温かい血が流れるのがわかる。
やるならやればいい。見せてみるがいい。獣の名にふさわしいその欲望を。
それさえも、自分を満たすだろう。それが、あさましい淫魔の本性なのだから。
一時だけで構わない。決して他人には見せない残虐な笑みがこぼれた。
「どうしたの。好きにしていいのよ」
誘惑の余地があれば、こっちのものだ。どんな相手だろうと、そこに隙が生じる。
「なぜ俺を追う」
獣がゆっくりと辺りを回る。傷を負わせた獲物の反応を覗うように。
「私を知っているでしょう。あなたに最高の夢を見せてあげられるわ」
「知らんな。俺に過去はない。目の前のものは全て切り裂いた。
そうか、知っていた…というべきか。おまえの見せる幻など今の俺には無用のもの」
「なぜ。いつか会ったときは違っていたわ」
「おまえの目には迷いがある。己の本能に従うことに、まだ迷いが。
あの時おまえ自身が言ったことだ。
内なる欲望に耳を傾け、闇を解き放て、と。野獣の本能に身を任せろ、と」
自分に迷いがある、それは思っても見なかったことだった。他者に指摘されるとは。
獣の舌が傷口に触れた。
その感触に悶える。疼いている。負わされた傷の痛み以上に。
早く。擦れあう皮膚一枚の感触で、それだけでいいのだ。それだけで逃れられるものばかりだ。
人の言うこの世の苦しみや哀しみなんて。それだけで脱け出せる。この不毛の牢獄から。
だから早く。
鳥肌が立っている。空気の冷たさと、触れ合う熱さに。
傷口から流れる血と獣の唾液が混ざり合う。そのままの姿で構わないから、
もっと激しく、息つく間もなく、引き裂かれてしまいたい。
ああ、そんなやり方ではなかった。求めていたのは。
獣の毛が、素肌に触れる。突き刺さるような強い毛だ。
もっと激しい痛みでいい、その感覚が、自分とこの地上を繋いでいると実感できるから。
前足が、胸の上に掛かった。尖った爪が柔らかな肉に食い込む。
「ぐ…」
やられる。
血に濡れた鼻先が、顎に触れた。獣の唾液が喉に流れ落ちる。
青い眼が見ている。冷たい瞳だ。舐め上げられた箇所が痛いだけだった。求めても得られない。
「早く、殺ればいいわ」
「おまえの目に恐れが見える。何を恐れている?
血に飢えた獣ならそれなりの生き方がある。それを選べないのはなぜか、
答えを求めるなら、俺ではなくおまえ自身に聞け。
獣には獣の理がある。逃れようとしても自分の闇からは逃れられない。
闘う意思をなくしたものを、牙を失ったものを、嬲って相手にする暇はない」
髪が踏みつけられ、狼は走り去った。
相手にする価値もないほど、自分は堕ちたというのか。
――このまま逃がすか。もう、生かしてはおけない。
立ち上がると、暗闇の中で微かに揺れる影を探す。
再び宙に舞い上がり、思い切り加速する。
届かない。瞬発力だけでは追いつけない。
負けるものか。必ず捕らえて始末してやる。
その後姿が視界に入った、と思った瞬間、シフトチェンジしたように急加速して
たちまちのうちに長い光芒を引いて見えなくなる。機銃掃射しても届かないだろう。
闇の中で風の流れを感じる。
内なる闇を研ぎ澄ませば、その軌道が読める――。
そこだ。
先回りして追い詰めたと思った時、炎に包まれた龍に襲われた。
かわしきることが出来ない。翼を焼かれてたちまち地へと墜落した。
敵わない。
地に落ちた。何もかも。文字通り。この自分に届かないものがあるなんて。
望めば全てが手に入った。夜はいつでも優しく、柔らかく、甘いものだったのに。
泥にまみれ、一人取り残されて、鼻の奥につうんと、嫌な刺激がこみ上げてきた。
目の奥が熱い。
こんなところで、私が……
夜の女王と呼ばれたこの私、魔界の全てを手にしようかという私が、
涙を落としているなんて誰が知ろう。
お付きの蝙蝠が一匹だけ戻ってきた。あとはみな炎に焼き尽くされてしまったのか。
もう飛べない。以前のようには。
城に戻れば、何事もなかったように気ままな暮らしが続けられるけれど
何だかもう全てを失ってしまったような虚しい気持ちがする。
うっ、と喉の奥から漏れた嗚咽が、冷たい夜に吸い込まれていく。
またたく星がこみ上げた涙に滲んで次々と流れていく。地に横たわったまますすり泣いた。
闇の中でちかちかと点滅する赤い光。
それが、傍らに舞い降りた蝙蝠の目であることに、だいぶ時間が経ってから気がついた。
泣き顔を見られてしまった。
この世で一番、弱みを見せたくない相手に――。
いっそこのまま大声をあげて泣いてしまおうか、と思う。
*
そうしたら、この意地の悪い蝙蝠はどうするだろう。
間が悪い時には逆切れに限る。つけこむ隙が大きい相手ほど大げさにご機嫌を伺うのに必死になる。
だけど、もうそんな仕掛けも今は虚しい。
――いつからそこにいるのよ。
差し伸べた手にためらいがちに蝙蝠が擦り寄る。
白いタイをつけた小洒落た姿。その気障な仕草までが変わらない。滑らかな毛並みを撫でる。
しゃくりあげるのを止めたいと思ったが、止まらない。
小さな温もりが手の中で微かに震えている。このまま引き裂くことも縊り殺すことも出来るのだ、と
考えてみる。なんの慰めにもならない。
――意地悪。嫌いよ……あなたなんか。
乱暴に耳を引っ張ると弱々しい鳴き声をあげて逃れようともがく。
冷たい夜風に吹かれて体が冷え切っている。目を閉じた。新たな涙が溢れる。
ふいに蝙蝠が身を捩じらせて手から逃れた。
全身を温かい熱が包み込む。抵抗しようとしてももう無駄だ。目が開けられない。その顔を見られない。
嫌い。
そんなやり方は。
冷え切った肌に体温がゆっくりと伝わる。
押し当てられた頬が同じくらい冷たい。どのくらいの時間そこにいたのだろう。
このまま何もかも吸い取られてしまったら。
この魔物の犠牲となった乙女たちはこうして抵抗をあきらめたのに違いない。
深い夜の淵に溺れ、もう逃れられないと知って。
その温もりに騙されて自ら身を投げたのか。
それともそれを望んでいたのか。
魔物はそれを望んでいる者の前に現れる。望んでいるから、その姿が見えるのだ。
あなたが、この私の見る闇の夢? この世の終わりに見る最高の幻?
……ふ、馬鹿にしている。随分と笑わせてくれるじゃない。
このままこの手にかかって殺される――少なくとも、この男は私を無視することなどできないはずだ。
そうでしょ。だから来たんでしょう?
涙が止まっても、喉の奥がひくひくと鳴った。
あ――。
雨の滴のように、額にぽつりと降る接吻。
それはだめだ。今そんなふうにされたらだめなのに。
「……見ないでよ、もう」
先ほどまで手の中で震えていた蝙蝠はおとなしく目を閉じて横を向いた。
*
「……狼など、追わなくてもいい。捕らえたところで君に何も与えてはくれないだろうよ。
向かってきたら蹴落とせばそれでいいのだ。君は強いし美しい。
多くの崇拝者が君を讃えている。だから、もう……」
「どうして、そんなことがあなたに言えるのよ」
「私も、そのうちの一人だからだ。……さて、美しい月を楽しめるうちに
我が翼で君を運んでやるとしよう。行き先は、君の城か私の褥か、――どちらを選ぶ?」
「どちらか……、長くいられるほうにして。あなたの腕の中に」
「滞空時間の長さでフライトを選ぶのなら、距離の遠い君の城だが。
……それとも、滞留時間でステイ先を決めたいのかな、ん?」
「機長さんにお任せするわ。彼のお疲れ加減を考えてあげないとね、ふふ。
でも、安心して。今夜だけは、優しくしてもらいたい気分なの」
「君も安心するがいい。今の君みたいな敏感な小娘の相手は充分心得ている」
そうして攫われていった処女が数知れずなのね――。
力強い翼が、一息に冷たい地上を遠く引き離して
その重力も、何もかもを忘れさせた。