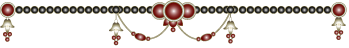最初に突き入った時以外、女は全く声を上げなかった。
ただその息づかいだけが微妙な起伏を持って波紋の外縁をなし、
中心を穿つものの存在を告げている。
服を脱がせ、触れた素肌はどこまでも白く冷たかった。中の温かさとは対照的に。
この毛穴すらない、肌理の細かな肌。生身の匂いがしない。浮き出た肩甲骨の形を眺める。
形象など意味を持たないと言ったか……この女は自分の形を知っているのだろうか。
冷徹な観念に実体を与え、血を通わせるようにその背骨の一つ一つを舐めていく。
一つずつ目覚めた感覚が、脚韻を響かせて次の行へと繋がっていくように。
女の肩が震え、吐息がリズムを変える。
机上に投げ出されたままの、血の契約書が目に入った。
お望みどおり署名してやることにしようか、と思い立つ。まずは腰を遣ってだ。
契約書の文章を横目で眺めながら、
『Demitri the Vampire, 偉大なるヴァンパイア、デミトリ…』
と、試しに一文字一文字、ゆっくりと女の中に綴ってやる。
不規則な横の動きと、抜き差しがうまく融合してかなりいい手ごたえだ。
女が苦しげに呼吸を深めている。続けて
『…魔界の覇者にして不滅の王』
と進むと、声こそ漏らさないものの、呼気に明らかな喜悦の色が滲みだした。
押さえられた手首の先の長い爪が空を掻きむしる。
側壁を余すところなく擦りあげていき、頂点で拍子が変わる、Mの文字を描く時が
格別にいい響きになる。その嗜好を示しているわけでもあるまいが。
その怜悧な美貌が歪み、泣き乱れる様を見てみたい。
深く奥まで食い入ると、その耳元に流れる血を舐めながら、ことさら甘い声で囁いた。
「ご褒美をやる約束だったな。君のご希望どおり、その契約書に署名してやってもいい。
どうだ、嬉しいか?」
女がわずかに身を捩る。
「ただ今日は愛用のペンを忘れてきてしまった。だから、後で君のものを借りて書くことにする……」
転がっている羽根ペンをとって羽根の部分で脇腹をなぞり上げると、ひくひくと体が震えた。
両の腕の中に囲い込んだ体を背後から更に締め上げて
右手で女の大きく張った左胸を掴み絞り上げる。
弾力のある肉を握りしめると手の中に冷たい心臓の脈動が感じられた。
くびり出された乳首がぴんと膨れてわななく。人差し指を下から添えながら教えてやる。
「ここだ、これで血文字の署名をしてやろう」
細長く突き出たペン先の調子を確かめるように、指を左右に振り爪で弾くと
さすがに小さな呻き声が漏れた。薄い皮膚が傷つき血が滲み出す。指が濡れ、滑るのを感じる。
強張った女の上体を抱きしめて持ち上げ、机の上に散乱している書物の角に
その先端がほんのかすかに触れるように加減する。
試し書きをするように、腰から動かして体ごと横へ移動させると
それだけで、あぁッ、と短い悲鳴をあげて力が抜け、その体の重みが腕に掛かった。
「覚悟しておけ……私のフルネームは長いぞ」
返事は聞こえなかったが、その中が感極まったようにきつく締まり痙攣する。
デミトリはその反応にほくそ笑んだ。後はその声だ。どうして泣かせようか。
「さて契約を結ぶ前に、君の理念について理解を深めておきたいものだ。
続きを聞かせてもらおうか」
「…このままで?」
「このままで、だ。おしゃべりは終わりか? 今なら君のご高説謹んで拝聴するぞ。
どうした。もう言葉が尽きたか? 観念の従僕よ」
「……意地が悪いのね」
「本当だ。個別の肉体など意味を持たないというのなら
今こそ君の崇高な理念を語ってもらいたいものだ。その身をもって証明してもらおう」
断続的に腰を引いていくと、引き伸ばされる余韻を惜しむように膝が震える。
いい傾向だ。何気ないそぶりで続ける。
「演説が無理なら、朗読をお願いしようか。これがいい。
『冥王の教理問答書』、これを読みあげてもらおう」
目に付いた書物を取り上げて、目の前に広げる。
「ちょうどいいわ。それにはいい序文があるの。聞かせてあげる」
首をめぐらせた女の横顔。わずかに潤んだ瞳。大きく息を吸い込み、女は語りだした。
その声は意外なほどに澄んでいた。
「我はひとつの大きな河。とどまることを知らぬ悠久の流れ。
すべてを癒す果てなき慈しみの泉。
朽ち果てた遺骸のうちに成就されぬまま眠る思いを
我こそが、ひとつの流れに統べ、導くことができる。
大いなる栄光のもとへ……」
速度と強度を増して責め立てたが、区切りで軽く息をつく以外に女の声はほとんど揺るがない。
次の詩句を思いおこすようにしばし考えているような間だけ
ふっと内部の緊張が緩む一時がある。
デミトリは自分のほうが息が乱れてくるのを感じた。額に汗が浮かぶ。
「なかなか興味深い思想だな……それはどこに書いてある? どの頁だ?」
「どこにも書いてないわ。今貴方のために詠んであげたのよ」
その目がここではない彼岸を見据えているのがわかる。
こいつは本気なのだ、と背筋の震える思いで初めてデミトリは理解した。
喋らせて乱れる声音を弄ってやろうと思っていたことも忘れて。
自分には見えないが、ジェダの目にははっきりと見えているものが確かに存在するのだ。
ふいに、たまらなくその血を味わいたいという純粋な欲望が湧き上がった。
「それで……それで、君の思いはどこにあるのだ。冥王よ。君の眠っている
成就されえぬ思いは。見せてみろ。その血の中に眠る思いを味わってみたい」
女が口を閉じ、無言で振り返る。拒絶の意思だった。
デミトリは構わず、その首の付け根に牙を立てた。
「あっ…く…ぅ」
吸血鬼に襲われた女が白目をむいて悶える。脇腹が激しく波打つ。
やがて血に濡れた唇を離して告げた。
「……続けるがいい。なかなか悪くない」
「殉教者の憂いが……、現世で理解されることはない。
赦そう、愚者たちを。限りなき哀れみを持って」
喋らせると気道の動きが、噛み締めた顎に伝わる。歯が浮き立つような振動がある。
喉の奥に流れ込んだざわめく血潮が吸血鬼の魂に囁きかける。
その憂いが沁みる。その味わいは、予想に反して
月のない静かな夜の雨にも似てぽつぽつと心を濡らす、湿った叙情に満ちたものだった。
どんな感情も凍りついた極限の、無味乾燥な観念の世界ではなかったのか、ジェダの思念とは。
触媒となることに耐えられるのか。それで。その繊細さで。血と肉とは分かちがたいものであるのに。
絶望に囚われることはないのだろうか。
それほど冷たく苛烈な「救済」とやらの理想が貴様を充たしているのか。
そんなものは遠い昔に超越してしまったのだろうか。
今まで感じたことのない畏怖の念すら覚える。
佳い味だ。繊細さと憂いと、絶対零度の官能に満ちている。確かに、お似合いだ……。
この女の冷たい威厳に相応しい。
吸血鬼は身震いをすると、白い肌に己の双方の牙を深く食い込ませ、
喉を鳴らしてその体を強く抱きしめ、更にその味わいに没頭していった。
腕の内に囚われた女が、たまりかねたように身悶えする。
書物や紙が音を立てて床に散乱した。
「おっと、勝手に動くとはお行儀が悪いな。クールな君には似合わない」
冷たい白い双丘を撫でまわして、平手でわざと音を立てて叩いてやる。
心の乱れを映すように内部がざわめいている。鞭を使ったときよりも動揺が激しい。
「いけないな。こんな劣情に心を乱されては。君の忠告だ」
「貴方は、本当に意地が悪いのね」
女が溜息まじりに呟いた。
「そうだ。知っていたんじゃないのか。聞かせてやろうか。君の感触を。君の動きを。
気取った顔で、ここにこうしてくわえ込んでよがっている姿を」
「趣味も悪いわ」
「ふふん、聞きたくないか?」
「聞きたくない」
「なぜ聞きたくないんだ?」
「言う必要はないから」
女の手首を頭上で押さえる。絡んだ腕飾りが金属的な音を立てている。
女の尻が突然悍馬のように跳ねあがる。
「動くなと言っただろう。言うことが聞けないのか。なぜ勝手に腰を動かす」
――だめだ。この流れに浸っていると、その血とその感触が、狂わせる。
先刻の、ジェダの言葉が脳裏をよぎる。
――あなたは考えたことがあるのかしら――?
振動が激しくなっていく。女の体と、そして自分の心の揺れが。
だめだ…よせ。そんなに。
軽く、戯れにたしなめていたのに、最後はほとんど懇願になっていた。
「…く…ぅっ」
集中が途切れ、流れ出す感情を押し留めようとしたが叶わなかった。
小さな水滴が、小雨のざわめきが、やがて濁流のうねりとなって全てを押し流す。
その果てに――
闇の底から声が聞こえる。
静かな威厳を秘めた、忘れえぬその声。
『その程度の力で、届くと思ったかこの玉座に。下郎が。反逆者の名にも値せぬ愚か者』
流れる血が目に入り視界が濁る。鉤爪が血に塗れた敷石を掻き、繋がれた鎖が音を立てる。
煉獄の炎が引き裂かれた翼を焼く。焦げた肉の臭いがあたりに漂う。鞭打たれる。
焼け爛れた皮膚に鋼鉄の爪が食い込む。その苦痛に咆哮し、のたうつ。
穏やかな魔王の声が、痛みよりも深く身を貫く。
『余は寛大なる君主だが、お前は赦さぬ。慈悲ある死など決して与えてはやらぬ。
己の愚かさを悔やみ続けるがいい、その永遠の命を呪うまで』――
「だめだ、動くな…」
炎に灼かれた胸を癒すようにぴったりと沿わせてその思い通りにならない体をきつく抱く。
氷のような体に、もはや縋りつくように灼熱の思いを押し付けていると、
黒煙をあげて記憶が純粋な水に溶けていく心持ちがする。
燃え尽きようとする隕石が氷の海に投げ込まれて深く沈んでいくように。
産毛も毛穴も見えない、血の通わない冷たい肌。生者ではない、これは死神の体なのだ。
冥界を流れるという忘却の河に身を投じ、血の淵に溺れ、急流に運ばれていく。
死神よ。これが、これが――お前の言う救済なのか?
…動かないでくれ……頼むから。
*
解放された腕を机について、放心した男の体ごと、ぐいと女が起き上がる。
体を捻って脚を上げ、その肩に脚をかける。
その芯に沿ってくるりと体を回転させると腰を引いて座りなおす。
引かれた体にあわてて男の器官がついてくる。
向かい合った格好で
後ろに手をついて長い両脚で男の首筋を抱えるように引き寄せる。
女の瞳がまっすぐに見つめている。
「黙ってしまったのね。意地の悪いデミトリ」
揶揄されても、すぐに返事ができない。
答えない相手に追い討ちをかけるように、ヒールの踵が耳の上を突く。整った髪を乱す。
その無作法な足首をのろのろと男の腕が掴んで止める。
「……行儀が悪いぞ」
「私の言葉を本気で信じていなかったんでしょう?」
だから忠告したのに。
先ほどは一瞬で逃れ去った唇がゆっくりと触れた。
磨かれた鉱物のような瞳が、男の眼差しを反映したように赤い光を帯びている。
「味わったのね。私の血を。私の思念を」
「ああ。良い味だった。もう、言葉すら…必要ないほどに」
酩酊し、目を閉じた。体の芯がふらつく。勢いを失った器官が、ずるりと滑り落ちそうになる。
くっくっくっ、と女の喉が鳴っている。
あざ笑っているのだろう、自分の無様な姿を。そう思った。
勝ち誇る女の前で力なく首を垂れているのがわかる。
なんと言われようと、もう構わない。それほどに……。
目を開けると、女は泣いているのだった。その涙だけは純粋に透明な滴だった。
女の涙を見て見ぬふりをすることは身についた紳士の嗜みだったが、
問わずにいられなかった。
「なぜ君が泣く?」
「貴方を感じたからよ。わかってくれて嬉しいの」
「どういうことだ」
「もう言葉で語る必要はないわ」
ふいに女が机から滑り降りて彼の足元に跪いた。
逃れる暇もなく、一瞬でその空間に包み込まれた。たちまち無数の舌先が攻め上る。
その柔らかな唇が言葉ではない技を操って、打ちひしがれた男の自尊心をくすぐり奮い立たせる。
論理を超えた筋道を辿るゆるゆるとした上り坂の行程に、やがてひび割れた亀裂が湧き水に潤む。
手のうちでいいように転がされ、傘下に右往左往するものの惑いが更に礎を高め強固なものにする。
瞼の裏に白い光が差した。昇る志が天蓋を突く。
そこに生じた真空に全てが吸い込まれそうになる、沸点に達した思考が気化しはじめる境地。
見えるはずよ。貴方にも。その道が拓けるのが。
手に取った鞭を女が差し出す。
それは、さながら新たな力の勃興を知る預言者が示した王杖、
目の前に掲げられ、手を伸ばせば届く絶対の光明、
そして再び力を得た、その身に備わる無限の持続と不倒の精根だった。
答えの代わりに再び倒れこんだ。女のもとへと。迷わずにその選択をした。
忌まわしさと死神の凍る墓場の記憶を埋め尽くすようにその肉体を屠った。
彼の情熱に反応するように女の肉も今は熱を宿して燃え上がっていた。
「ああ、いいわ。もっと。きて。ああ。そうよ。デミトリ…。貴方を感じる…」
同じ血が、一つに結ばれた肉体を巡るのよ。こんなに素晴らしいことがあるかしら。
暗示にかかったように、その温もりを夢中で抱きよせる。
触れた部分が、次々と鮮やかな色合いと輝きを増して咲き開き
砕け散る波のように細かい飛沫になって還っていく。
よく反応し、逆らうことなくより添ってくる。どこまでも心地よい感触で。
全てが目の前に、ひらけている。これこそが、色鮮やかに咲き誇る栄華の精髄。
揺らめくオーラの微光が吸血鬼の体から立ち昇る。赤い瞳が爛々と輝いた。
与えてやろう。我が不滅の炎を。今この手の内にある万能の力。全てが叶う。
尽きぬ愉楽の地獄を味わうがいい。
あたりに満ちた血の匂いが、温度を上げて充分に開いていく。
女の血と花が持つ、アロマとブーケの妙なる調和が際立った存在感を示し
その中心で昇りつめたい衝動を抑えられなくなる。
女の紅い爪が、背中に食い込む。
極まる悦楽を示すように、長い脚ががっちりと絡みつき、離さない。
そのまま腰が浮きあがる。抜こうとしても、くわえ込まれたまま退くことができない。
吸血鬼の顔が青ざめた。
ピンヒールの踵が、男の孔を正確に捉える。
女の瞳のうちに妖しく冷たい炎が燃え盛っている。
「きて…。私の中に。熱く激しい貴方をちょうだい。
その不滅の誇りと溶け合いたいのよ。放さないわ。放さない、貴方を。もう二度と。
このまま溺れて。この中で。赤い血の海が乾きを満たしてあげられるわ。
憂いも、嘆きも、癒してあげられる」
ぎりっとヒールが食い込んだ。
鮮鋭な感覚が脊髄を直撃し、衝動を加速させる。
無数の血柱が欲望を追い上げていく。
昂ぶる女の声が更に激しくなる。
「私の血を味わったわね。私の思いを知ったわね。
きて、デミトリ。ここよ。中よ。聖なる胎内に。
貴方の血と魂を返してもらうわ。いいの、そのまま、っ……」
ギリギリまで煽られて、頂点に達することを許されない。
唸った。声を抑えることも出来ない。口元から血が噴出す。女の血を吐き出した。
しかし、それでも動きは止められない。
女の唇が何かを呟いている。
同じ呼吸をして、同じ血が巡り、永久に、完全なる結合の中にあるのよ。貴方と。
「恐れてはいけない。私は最初で最後――」
――!
我に返った時にはもう遅い。
くそ、やはり……。しかも、この失態は命取りだ。
続いたのは紛れもない、冥王ジェダの哄笑だった。
「そうだ。その調子だ。さあ一気にぶちまけるがいい。君の野蛮な本能を。獣の欲望を。
爆ぜ、熱く迸るほどに私の中で君が蒸留されて、純粋な魂が、
純度の高いそのエッセンスが、君の本質だけが残る――。
その魂を我に捧げよ、真の救済のために。それが君を活かす唯一絶対の道だ」
ジェダの体から血が送り込まれる。その一点に集中し、膨張していく。
今来る、救済の時。
冥王が指を鳴らした。
絶頂を迎えた女の体がびくりと跳ね上がる。
渾身の力で、デミトリはその首を食い破った。鮮血が高くしぶきをあげて迸る。
溢れ出る血が、散乱した書物の文字を滲ませ、観念を消し去ってゆく。
緩んだ拘束から逃れた瞬間、引き抜いて契約書の上に放った。
飛沫をあげて叩きつけられた白濁が紅い血文字を覆い尽くし、紙もろとも音を立てて蒸発していく。
吸血鬼の血と精を浴びた女は、陶然とした表情を浮かべてその光景を眺めている。
一瞬の後に、愉悦に滲んだ声を上げ、氷の煌きを残して手の中で溶けて流れ去った。
*
血の海が消失した後の、背後の空間に元の姿に戻ったジェダが出現した。
「見事だな、吸血鬼よ。気に入った。どうやら君の魔力も完全に復活を遂げたようだな。
こちらにはいつでも受け入れる用意がある。君たちの種族は血と血を分け合い交わるものだ。
我が志向するところも、その目的に適っているとは思わないかね」
「血にはそれぞれの味わいがある。一つとして同じ味はない。
貴様の理念に統合されるまでもない。あるものは感じやすく、あるものは強く、あるものは優しく
全てが私の中で溶け合いこの上も無い喜びをもたらす。私に向かって二度と血を語るな」
乱れた髪を整えながら、止まらない指の震えを懸命に抑えようと努力した。
「再建されたわが城の庭に、私を讃える栄華の花々が美しく咲き誇る日が、やがて来る。
その暁には、真紅の薔薇の花束を贈って貴君に礼を尽くすこととしよう」
貴様と契約するつもりはこれぽっちもないがな、と心の中で付け加える。
外套を纏い、手袋を嵌めかけて、棘のささった指からまた血が一滴膨らむのを見る。
ゆっくりと椅子に掛け、ジェダは落ち着いた声で告げる。
「まあ、帰ってゆっくり己の立場をよく考えてみることだな。忘れるな。私は警告したのだ。
いつでも受け入れる用意がある、と繰り返しておく。
だがな、もう二度と君からの花を受け取るつもりはない。ただ一度で十分だ。
最後に一つだけ教えてやろう。形而上の憂いとは、めそめそした感傷の涙とは無縁なのだよ」
用件は済んだ、といわんばかりに鋭い爪が指し示した方向に、出口の扉が現れた。
足元には渡るものを引き込む細く赤い川が、依然として高い波を上げて逆巻いている。
「ならば、貴様への答えを今受け取るがいい。これだ」
血に汚れた白い手袋を床に叩きつけ、傲然と顎を上げた吸血鬼は
ジェダを見据えたまま、外套の裾をなびかせてすうっと背後に滑るように遠ざかり
軽やかに小川の結界を越えて宙に姿を消した。
「十分だ…、ただ一度、それだけで私の中で永遠に色あせることはない」
冥王の視線の先は虚空に留まっている。
2005.11
menu