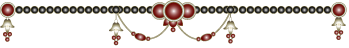魔界に戻るのは久しぶりだった。
城門を通ってから、馬車もすれ違えないほど狭く険しい路を登り
ようやくたどり着いたジェダの居城にて、
「わざわざお呼び立てしてすまなかった。ご足労感謝する。辺境での隠遁生活はいかがかな」
冥王自らの出迎えを受け、デミトリはいささか落ち着かない。
鐙を外した爪先が白い砂埃に汚れているのを眺めて更に神経質な気分になる。
乾いた風が吹いている。ここには季節がない。この空気。
近い将来魔界に拠点を移しても、この辺りには極力近寄りたくないものだ。
眼下に広がる領地を見渡す。なにしろ長年ドーマ家の支配下にある土地なのだ。
狭い石造りの階段を降り、案内された一室は
入り口からは酒倉かあるいは地下牢を思わせるつくりだが、中に入ると、半球形の天井がはるかに高い。
怪しげな図形を描く嵌木細工の床。壁はほとんど書架で覆われている。
中央の書斎机には、黄ばんだ大型の書物―背表紙の文字はラテン語か、
なにやら解剖図や数式が描かれた羊皮紙、羽根ペンなどが乱雑に置かれている。
衒学趣味ここに際まれりといった感のある書斎だが、単なる中世懐古趣味の思索家の部屋にしては
少々異質なものが散見し、その内なる狂気を感じさせずにおかない。
部屋の一角には中世の拷問に使用されたという鋼鉄の処女が据えられている。
錆付いた棘に、今でも生贄の娘たちの血が匂うようだ。
その中に大型のヒュミドールが置いてある。あの中に本当に葉巻を保管しているのだとしたら、
冥王流の洒落た意匠にしても、信じがたい神経だ。デミトリは軽い眩暈を覚えた。
あれでは湿度どころではなく、とても吸えたものではない。
チェンバロもあるが、鍵盤に埃が積もったままだ。弾く者がいないのだろうか。
並んだボトルに目がとまる。マールか。葡萄の雑多な搾りかすから造られる酒。
イタリアでグラッパと呼ばれる、あまり上品な酒ではない。
冥府の王にしては意外な選択に感じられた。
その視線に気づいた冥王が、一杯どうかと勧める。
「いや、結構」
即座に顔の前で手を振った。ここで酒を酌み交わす気分ではない。
「そう警戒しなくともよい。それとも、君の高貴なる俗物ダンディズムには合わないのかな。
ワインに使用された葡萄の残りの搾りかすが、蒸留されることで新たな命を得て熟成されていく。
その観念にこそ酔えるのだよ。ブランデーやモルトウィスキーも悪くはないが」
ジェダが皮肉に笑う。
「それで用件は何だ。手短に願いたい。私も忙しい身なのでな」
冥王が魔界の近況を語る。その将来と繁栄を見越した自己の魔界再編計画とやらを語る。
すぐにデミトリは退屈してしまった。せいぜいそんなところだろうと思った範疇を出ない。
わざわざ呼びたてたことの意味は何か。自分もここまでやってきたことの意味は。
恐れ多くも魔王に反逆し人間界に長らく追放の憂き目を見た男の、次の手を探りたいのだ。
ジェダも想像以上の自分の復権振りに恐れをなしたというところか。
既得権は確保したい。早めに手を打って懐柔したいという意図が見える。
旧体制の三大貴族自体が、デミトリに言わせれば既に終わっている。
いまさら魔界勢力全体の均衡など自分の知ったことか。
そんな思惑を知ってか知らずか、ジェダは構わず自説を繰り広げている。
敵情視察の目的も果たしたところで、そろそろ潮時だ、と思う。
こんなところでいつまでも面白くも無い面と向き合って世迷言を聞かされていないで、
城に戻って、そうだアンジェリカを可愛がってやろう…。
お気に入りの美従を思い浮かべて思わず緩みかける口元を、引き締める。
「私は個人的利益ではなく、この世界全体の終末を真に憂慮している。改革が必要なのだ」
ジェダの熱弁は続く。
「と、言うわけで、貴君にもぜひご理解ご協力いただきたいという訳なのだ。
極力、有利な条件で提案させていただいたつもりだが」
冥王が自信たっぷりに問いかけてくる。
話はろくに聞かなくとも、ご理解ご協力の真意はよく分かっている。
要は下手な動きをしてくれるな、という牽制なのだ。
何をたくらんでいるのかは知らないが、長らく魔界から遠ざけられていた自分の動きが
冥王にとって脅威となりうる事実はデミトリに十分な満足をもたらした。
「貴君の仰る、救済という理念が、どうも私にはぴんと来ませんな。
弱者は淘汰される、仕方のないことだ。むしろそれがあるべき姿といっていい。
いや、全く。ひかれる要素が見当たらない。大変申し上げにくいことだが、
気の抜けたぬるいシャンパン以下、血なまぐさいシガリロ以下、
つまりは丁重にご辞退申し上げたいシロモノということになりますかな」
さも残念そうな表情を貼り付けて、唇の端を曲げる。
ジェダは口元に穏やかな微笑を湛えている。
その顔が一層白くなったように見えるのは気のせいか。
気をよくしたところで、これ以上このいかれた繰言に付き合っていても仕方がない。
長居は無用、とばかりに席を立つ。椅子が意外に大きな音を立てた。
しまった。やや好戦的に過ぎたか。しかもこれでは単なる無作法者と変わらない。
「ま、ただ、魔界の将来ということでは、私も考えないわけではないので……」
室内をめぐり、賢者の提案をよくよく咀嚼しているふりを装いつつ
表面上穏和な辞去の理由を考えているデミトリの視界の端で
書棚に、乾燥した薔薇の花束が、無造作に吊られているのが目にとまった。
遠い大聖堂の誓いの式典で投げられたか、束の間の眠りにつく霊への手向けか、
思いを込めた花束がそのまま冥府に落ちて忘れ去られ、
この閉じた天井から降りその棚に掛かったまま、何世紀もの時を経た――
そんな情景が浮かぶような、埃をかぶった茶色の塊。目を細めて凝視する。
朽ちてしまった亡骸をいつまでも晒しておくのは彼の趣味ではない。
手を伸ばし、乾いた一輪を崩さぬように抜き取った。
色も香りも褪せてしまった花。枯れる前に生きながらえさせる術をほどこすか
さもなくば、その華の盛りに摘み取り、後は散らせてやるのが情けというものだろう。
その様子を眺めていたジェダが、あらゆる花束の不在、と呟いた。
「詩人の表現だが、…その観念を、本質を、愛でれば足りるとは考えられないかね?
移ろいゆく形象など意味を持たない……理解しているはずだ、既に君も。
美しいものに惑わされる、君の誇る審美眼。情にほだされ、揺れ動き、
色(しき)なるものに左右される……そんなところがそのまま君の弱点だな」
憮然とした表情で振り向いたデミトリに、なだめ諭すように
しかし虚礼をとりはらった率直さで彼は告げる。
「何故それほどまでに自分の力を証明したい?
永遠にトランシルヴァニアの山の彼方に隠遁しても、雑魚の相手と美女の負荷で励めば
君のその筋力維持には充分なはずだ。気ままに面白おかしく暮らすこともできるはずだろう?
その身分に何の不満がある。これは警告だ。私には見えるのだ。君がその身を滅ぼすさまが。
悪いことは言わない。魔王の権力に、アーンスランドに固執するのは止めておきたまえ」
「何と…仰いましたかな。失礼、私の聞き違いか?」
もはや苛立ちを押し隠すことはできなかった。
「まあそう焦らずにそこに掛けたまえ。よく聞くがいい。
君はごくごく表面的にしか事象を捉えていない。表か裏か、目の前の敵に勝つか負けるか、その程度だ。
だが別の次元が存在するとしたらどうだ……もう少し君の関心に近づけた話をしようか。
私が近頃発見した、ある魂の正体を知ったら、君はどう思うかな。
それはアーンスランドのサキュバスの能力の一部を封印したと言われているものだが、
いくら潜在的な能力だといえど、封印せねばならぬほどの魔力が幼い淫魔ごときに備わるはずがない。
私の考えでは、あれは魔王の、ベリオールの力だ。魔王はその一部を未来に託して封印していたのだ。
今あのサキュバスの小娘と結べば、強大な、ベリオール自身も敵わぬほどの魔力が生まれる。
永久不滅の絶対王政だ。だが、サキュバスは君も知ってのとおり、永遠などという地獄に耐えられはしない。
その時こそベリオールが甦るのだとしたら。さて君はどうする?」
「馬鹿な。これは驚いた。この私がそんなはったりに乗せられるとお考えとはな」
「隠遁生活が不服なら、君のとるべき道は一つしかない。
私と手を結ぶのだ。デミトリよ。ベリオールが復活してからでは遅すぎる。
君の力は高く評価している。失うには惜しい。
この私と組めば、救いの道が開けるのだ。それがなぜ解らぬ。
君を倒すことなど簡単だ。黙ってみていればいい。いずれ必ずそうなる。
それが遺憾と思えばこそこうして説いているのだ。
個人的な、愚かな野心や復讐心を捨てて、もう一度よく考えてみるがいい」
鋭い目を光らせた冥王の、静かな口調にこもる奇妙な説得力が一段と反抗心を煽った。
「冥界には新たな風は吹き込まぬようだな。朽ち果てた繰言など誰もまともに聞きはしない。
仮にその話が真実であったとしても、大変残念なことを告げねばならないが、貴君に貸す耳はない」
そうくるのならこちらもはっきり言わせてもらう、とばかりに宣言してやる。
互いに譲らなければ、いずれは宣戦布告することになる相手だ。
「そういう態度でいられるのも今のうちだ。もっとも、君が望もうと望むまいと、遅かれ早かれ
結ぶことになる。そういう帰結なのだ。既に条項を用意してある。いらぬ恥をかく前に、
さあ、よく読んで署名したまえ」
デミトリの剣幕にはお構いなしの、事務的な動作でジェダが懐から巻かれた紙を取り出した。
「決して悪い話ではない。君の好みそうな表現をすれば…そう、象嵌されるとでも言おうか、
君の力が未来永劫に渡って…」
「貴様に理解できる表現をすれば、お断り、だ。ノーサンクス。ノ、グラッツィエ」
嫌味たっぷりに語気を強めた時、手の中で弄んでいた薔薇の、乾いた棘がちくりと指を刺して折れた。
吸血鬼の赤い滴を吸い取った花が手の内で膨らみ、たちまち妖しい艶を取り戻して咲き開く。
それを眺めて確信する。これこそが愛でるに値する花なのだ、と。
空虚な観念などではない、この手の中の確かな存在。花びらにそっと口付ける。
「ご忠告ありがたく受け取っておく。だが、貴君とは相容れぬ巡り合わせのようだ。
残念ながら。これで失礼する」
気取った仕草で薔薇を宙に放り投げ、踵を返す。
「君なりの礼を尽くした返事というわけか、この花が。やれやれ、大した礼儀もあったものだ」
投げられた薔薇を床に落ちる前に手に取り、肩をすくめたジェダの姿が変貌した。
*
煙の中から現れ出たのは、妙なる美女だった。
プラチナブロンドの髪。鉱物を思わせる鋭い光を放つ瞳。紅い唇。
青白い首筋から豊かな胸の膨らみを慎み深く隠しているのとは対照的に、
大胆なスリットが見事な脚線美を曝け出している。
優雅なふくらはぎの曲線から締まった足首、その先の踵の高いヒールまで、思わず視線が奪われる。
「それが、貴方のお郷では貴公子の流儀なのね」
女が腰を捻ってポーズをとる。スリットの内側に赤いガーターベルトを覗かせて、そこに花を挿しこむ。
振り向けば背後の扉が消えている。床に赤い線が走ったかと思うと
たちまちのうちに壁際に沿って波打つ血の小川になり、その中に囲いこまれた形になった。
冥王の次元に閉ざされたのだ。
どこまでもふざけた真似をしてくれる。自分の無礼を棚にあげ、デミトリの怒りは増大した。
冥王の声が空間に響く。
――ふふ…君の興味を引くには至極単純な方法が有効だったようだ。
他者の目にどう映ろうとも私は構わぬ。そうだ、本質こそが重要だからだ。
素肌を晒したほうがいいのかな? それとも抑制が君の情欲をそそるか?
惑うがいい。愚かな反逆者。私はアーンスランドの小娘のようにはいかぬぞ。
君の欲望すら、意のままに操ることができる――
目の前の女が口を開いた。
「そう、貴方の器官に血を送り込んで炸裂させることもできる。
私の中に、貴方を取り込んで血の海でもてなすこともできるわ。
せっかくだから愉しんでもらいたいものね。我を忘れて。無我夢中で。
私と結びたいとは思わない? この姿なら、お考えもだいぶ変わるのかしら?
この私と結び契るということは、すなわち血の契約を意味する……もちろん、おわかりよね」
冷笑が、デミトリを焚きつけた。
ふん、吸血鬼に向かって血の契約を語るか、愚かな…。
その思考、くだらん繰言、とめてみせる。勝手にほざいていろ。
「面白い、私を満足させられるか。その姿で」
一気に距離を詰め、書斎机の上に女の体を押し倒した。
インク瓶が転がり落ち、青い染みが床に広がる。
腕を掴んで捻り上げる。女は笑みを浮かべてされるがままになっていた。
スリットから覗く両脚の間に、ぐいと荒く膝を割り込ませてやっても、動じる気配もない。
光る瞳がじっと男の顔を見上げているようで、何も見ていない。
「ん…嫌よ、そう乱暴にしないで」
女の紅い唇が媚びた声音を奏でる。
「ワイルドなのは慣れていないの。見せてちょうだい、お得意の、甘い甘いロマンティストの精髄を」
長い爪が乱れた白いシルクタイをそっとなぞり、その下の筋肉の層を確かめるように指を滑らせている。
威嚇が応えないのなら面白みがない。絡みつく女の手を冷たく払いのけ、体を離す。
「そうか。ご期待に沿えず申し訳ないが、君は私を怒らせた…不注意にして致命的なミステイクだよ」
「すぐに頭に血が上るところも、気をつけたほうがいいわよ。未来の君主に相応しくないわ」
身を起こした女は何事もなかったように髪を整えている。
大きく腰を振る歩き方で机の周りを回って酒瓶を取り出した。
「一杯いかが。捨てたものでもなくてよ」
幾何学模様のカットグラスに女の赤い爪が反射している。
艶めいた唇が、グラスの縁に触れる。飲み込む量ではない琥珀色の液体を味わって
白い喉が微かに動く。
――女たちが無防備に晒している、最も滑らかで柔らかいその部分は
吸血鬼の目にいつもこの上ない愉しみを与えてくれるものだった。
それが生意気な美女であれば言うことはない。いらついた気分も自然とほころぶというものだ。
ほぼ同じ高さの目線が交錯する。
思わせぶりな笑みを浮かべグラスに新たな酒を注ぎ、近づいてくる。
目の高さに掲げ、無言で勧める。杯を持った女の指の上に、手を重ねて握った。
そのまま引き寄せて、口をつける。
グラスではなく紅い唇のほうに。
弾力のある縁から、酌まれた液体を味わう。
度数の高い酒が唾液で加水されて、開いた芳醇な香りが鼻に抜けていく。
舌の上で転がす。手の中の、女の指がわずかに震える。
更に深く味わおうとしたところをすっとかわされた。
「お口に合ったかしら?」
「確かに、悪くない。いい杯で飲めばなおさらだな」
不覚を取った。逃げられたことが、いや下心を読まれた自分が情けない。
動揺のあまり言わずもがなの野暮な世辞まで口走ってしまったことが悔やまれる。
相手はただの美女ではない。うぶ娘連中相手の感覚で、決まったなと判断したのが誤りだ。
人間界に長く身をおいたせいでだいぶ勘も鈍っているのだろうか。
「そう、気に入っていただけてよかったわ」
そ知らぬふりで、グラスを置いた女が答える。
だが一瞬触れた舌先を意識した証拠に、その箇所を舐めるのを見た。
「逆上していても、さすがに抜かりはないのね。
貴方が、あのサキュバスの食い物にされていくのを見るのは忍びないわ」
随分と余計なお世話だ。
「食い物とはどういう意味だ。逆かも知れんぞ」
文字通りの意味よ、と女は笑った。
「吸い尽くされて、骨抜きにされて、貴方の誇りまでもぼろぼろに挫かれて」
女がさっと翻した手の指先に注意を引く。
蟲が一匹、尖った爪の先で弧を描いて飛んでいる。蜂だった。
「見て。貴方が随分とご執心の、あの盛りたがりの小娘もまた一つの女王蜂に過ぎない……。
深遠な考察などなく、飢えを満たすことだけ。持てる力に溺れて。
目の前の蜜を追う、働き蜂どもの命で生きながらえて。
たかが一匹の虫けらに、絶対の権力を見て崇め奉る。それがどれほど滑稽なことか
魔王の、ベリオールの影を無意識に追い求めている貴方にはわからないかしら?」
流し目が妖艶な光を放っている。
爪が首筋から肩へと流れていく。嫌なものに触れられたようにデミトリはぴくっと顎を引いた。
構わず顔の近くに寄せられた唇が甘い口調で毒のある言葉を投げかける。
「もう少し賢い男だと信じていたのに。残念だわ……。
貴方は考えたことがあるのかしら。もしも自分が魔王の覚えめでたければ…と。
たとえば貴方が、魔王の後継者に選ばれていたならどうなっていたか…と」
「ふん、くだらん…どうなっていたと思うのだ」
努めて平静さを装いはしたが、その言葉はデミトリの胸の奥深いところを鋭く突いた。
表情を隠すように顔を背けた吸血鬼の横顔を、女は黙って見つめている。
視線が一瞬、背後に消えた扉のほうへ流れたのを、目ざとく見つけて
「吸血鬼にはその川は渡れないわよ」
とからかうように呟く。
蜂の羽音が喧しい。
その音が、抑制を失わせた。
乗馬靴の脛から取り出した短鞭で蜂を叩き落し、ついで容赦なく女の顔に先端を当てた。
どこかで、そうすれば美女の仮面が剥がれ落ち、邪悪な本性が現れるのではないかと期待して。
きゃっ、と悲鳴をあげてあっけなく女が崩れ落ちた。
何かの間違いかと思わず錯覚するほど、温和な笑みを湛えて見上げている。
鞭の当たった耳を押さえている。白い顔は綺麗なままだった。
その覚悟があるというのなら、仕方がない。動揺を隠し、感情を抑えた声で告げる。
「おふざけはこれまでだ。跪け。床に。貴様のその唇に、許しを請わせてやる」
尻を突き出した姿勢で床に這わせた。
鞭の先端で裾を捲り上げ、ガーターベルトの隙間に差し入れる。
ストッキングを止めていた片側の金具がはずれて、跳ね上がった。
絹地が張った腿の上に柔らかい陰をつくって弛む。
鮮やかな色の血がすっと内腿を伝って流れ落ちる。体液が赤いのだ。
「気に入っていただけるかしら、貴方なら」
無駄口を叩いたことの代償に、ぴしり、と一打ち、尻を打擲し止める。
うっ、と女が息を詰めた。
音だけが高く響くように加減をしたつもりだった。
だがさっと微かな赤い痕が白く滑らかな皮膚に浮き出す。
さきほどは思わず手が動いたが、屈辱を与えることが目的ではあっても、
美しく整ったものにむやみに傷をつけることは彼の本意ではない。
そのように考えること自体が、無駄だとジェダは言いたいのだろうか。
ふと触れた瞬間に膝に肌の柔らかみが伝わる。
その素肌に触れたくなる欲望を抑えて、わざと爪先で脇腹を押す。
何をされてもひるむことがない。強い目の輝きが衰えない。
苦痛も恥辱もこの女にはあまり堪えないようだ。
腰を屈めてむき出しの腕に触れ、撫で下ろしてその片手をとった。
その指の付け根からほそく伸びた指先まで唇で触れる。
「他人の目にどう映ろうとも構わんと言ったな。見たいものがある。君の姿だ。
この指で、広げて、愛撫して、君がいくところを見たい」
女の瞳が揺らぐことなくきらきらとした光を放つ。
「そうしたら、ご褒美がいただけるのかしら」
「考えておこう」
本当はその部分には興味がない。見たいのは溺れる女の表情だった。
鞭を置き、椅子に掛けて脚を組む。書斎机に伏せた格好のまま脚を開かせる。
スカートの裾を翻して捲り上げ、腰を突き出す。振り返って男の視線を確かめている。
盛り上がった白い山を撫で、二つの丸みを掴んで広げてみせる。
女は下着を着けていなかった。その部分に毛がない。
長い爪の先が、そっとその輪郭をなぞる。貴婦人が口紅を塗りなおす動作のようにさりげなく。
左右の淵から血を塗りこめる。指先がゆらゆらと揺れる。
指に、赤い蜜が流れ出してくる。女が身震いをし、あっ、と小さな声を漏らした。
これ以上は入れられないわ。爪が…。
こちらの反応を覗い見た、その目から視線を逸らさずに、続けるよう促す。
二本の指の間に薄い唇を挟むようにして、ゆっくりと摺り合わせるように指が動いた。
挟まれた赤い唇の片側だけが覗いているのが扇情的だ。
腿の内側を流れていた血が膝の裏に回りこみ、
縫い目のようにふくらはぎの中央に一筋の線を描いて流れ落ちていく。
「もっと近くに来て……、いきたいの。一緒に。もうできない」
血の滴る濡れた指を舐める。その視線を意識して、
「そう、貴方の何より好きなものよ。心ゆくまで味わえる……」
ここが、約束された楽園への扉なのよ。脚を更に広げてゆっくりと腰を揺らして見せる。
赤い涙を流し震えながら中心で誘っている妖しい花。
大きく広げられた部分から、更に溢れだした粘度の低い液体が、
ぴちゃん、ぴちゃん、と音を立てて直接床に滴り落ちる。
足元を濡らす血の雨の音。飛沫が、ぬかるんだ道をつくっている。
「…ここに来て」
温められた血蜜の香りが狂おしいほどに吸血鬼の本能を掻き立てる。
観念に相応しくない生々しい匂いが。
胸にくすぶっていた熱と疼きが垂直方向に落下する。
主の意思を待たずに、器官同士が、磁力で吸い寄せられたように距離を詰める。
表面張力で盛り上がっている。ぎりぎりの瀬戸際まで。
その液体同士が触れ合って零れ落ちるまではあとわずかだ。距離も時間も。
自分の呼吸音が耳に大きく響いている。
待て、今ならまだ引き返せる、引き返せ、と脳裏で止める声がある。
ほとんど頭痛になりそうなほどの激しい警鐘だった。
だがしかし、これこそが愛でるべき花の色ではなかったか。
緊張が最高潮に達した瞬間、引き締めていたはずの手綱がするりと手元から逃れていく。
その扉に向かい倒れこむような一歩を、彼は踏み出した。