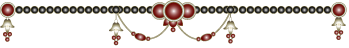女が起き上がり、体勢を逆転させた。
上になった淫魔が勢いをつけてのしかかる。
「ぐぁアァッ!」
勢いをつけて根元まで捻じ込まれた。
目が眩むような衝撃が貫く。痛みというよりも全身が痺れる重圧感だ。
「あぁ…あなたの中気持ちいいわ。これが、全部入ってる。繋がってしまったわね。素敵よ…」
ずるずるとそれを捻る。たまらない。乳首を噛まれて悶絶する。
「やめ…て、くるしい」
最奥までのろのろと貫かれ、そうしてそろそろと後ずさりする、それを延々と繰り返される拷問だった。
体を密着させたまま、花弁が巻き込まれるかと思うほどに奥深くまで突かれ、
そのまま時が止まってしまったのかと思うほど、少しずつ、気が遠くなるほどの時間をかけて
大きな龍の鎌首にずるずるずるずると抉られながら花口まで戻される。
「いい? 生意気言っていられる元気が残っているのなら、これを数えるのよ。声に出して。
ほら今何回目かわかる? 四回目よ。次は?」
「あぁ、はぁ、はぁ、ご…かい…め」
無限に思われる時間が、引きずられる全ての内襞の全ての細胞にまで
その感覚を染み渡らせずにはおかない。呼吸し脈打つほんの些細な動きにも、
擦れあう内部が反応しあって焼け付くような激しい刺激になる。
拒みたいのか、感覚に酩酊しているのか、自分でもわからないままに目を固く閉じ首を左右に振る。
振り払おうとしても、そこに、集中していく。激しくせめぎあっている。新たな熱が生じていく。
募る感覚にたまらず身を捩れば、その余波がまた己が身を苦しめる。
*
「どうしたの、聞こえないわよ」
「…うぅ…ぁうっ、っ」
奥に達するたび、ずうん、と染み渡る鈍い衝撃が、秘めた心までも揺さぶる。破城槌のように。
二桁に達する頃終わるかと思われた戯れが、その倍になっても三倍になっても止まない。
集中が途切れそうになるのを女の声が呼び戻し、内なる葛藤から放さない。
相変わらずじれったいを通り越して狂いそうになるほどのスローペースで弄ばれている。
「さんじゅう…く…っ……よんじゅ…」
「意外とがんばるわね」
膝ががくがくと震え、わずかに浮いた腰が崩れ落ちそうだ。
尻の肉に、今はしとどに濡れた敷布が、触れるたびに一層冷たくなっていて
いつまでも慣れることがない。
時折、ぐうっ、とか、うおぁっ、とか喉の奥から娘らしからぬ声を上げながら、脂汗さえ滲ませて、
――あとどれだけ持つだろうか。あとどれだけこの責めに抵抗できるだろうか。
どこかで明晰な意識が冷静に計っている。
かつて魔王に敗れ去ったときの苦さが、不気味な実感をもって胃にのぼる。
もうそれほど持たないのがわかっていた。限界が遠くない。
肉体が悲鳴をあげながら、すでにとっくに降伏して極まる快感にぐずぐずとだらしなく泣き出している。
じゅぷっ、と音を立てて泡だった愛液がなおも太股を伝って溢れ出しているのが情けない。
いっそ一思いに、一気に終わらせて欲しい、欲しい、それが…
それが。
ああ、ああ、もう、はやく。これ以上。
……だめだ。
たまらない…!
あと何秒かで、この次の、その先の、瞬間には、
きっとこの胸が叫びだしてしまうだろう。
その前に終わらせて欲しい。
お願いだから。
一際深い鋭い突きが襲う。そのまま動かない。
「ぐくッ……はぁ、ハァ」
髪を振り乱して悶える娘を見据えながら、淫魔の腰がうねる。
「あ、ぁぁぁ……――」
もう何度目か、遠のきそうな意識に女の声が呼びかける。
「ああ、ああ、あなたが縋りついてくるわ。必死で。いいわ。素敵。
その目つき。そんな目で見られたら、先にいってしまいそうになるわ」
――恐れないで。優しい闇は決してあなたを傷つけたりしないわ。
肌と肌を触れ合わせればわかる。溶け合ってしまいそうなほどに懐かしく温かい。
知っているでしょう、あの快楽を。私たちは共に夜に生き、闇に輝き、刹那の快楽を愛するもの。
全てを忘れて、今この一瞬を満喫して。そこにこそ意味があるのだから――
髪が乱れ、別々の方向を向いた乳房が揺れている。深く突き動かされるたびに
喉下まで不気味に甘い感覚に抉られるようだ。女の声のお陰で今や不安の正体が明らかになった。
呑みこまれそうな闇が、そこに惹かれている自分の心が、恐ろしい。
そこに至れば全て奪われ、支配されてしまうからなのか。
「これはどう? ねえ、どう? 聞かせて。そのかわいい声で。いいでしょう? 気持ちいいでしょ?」
そう言われると、意地でも声をあげたくない、気力の欠片がまだ残っていることに自分でも驚かされる。
ご丁寧に腰の下に枕を敷いてより結合が深まるように調整され、
力の抜けた両手首を掴まれたまま、腰を打ちつけられている。女が猫なで声を出す。
「ねえ、いい加減正直に言っていいのよ。こうされたかったでしょう? こうやって」
内側から臓腑を食い破られるような激しさだ。
「こうやって、抵抗できずにすべてを私に捧げて」
「い…や…」
甘く蕩けるような官能を湛えていた女の顔が突如サディスティックな笑みに引きつった。
「まだそんな口を利くなんて。そんなに涙をいっぱいにためて。いいんでしょう。
フフフ。悔しいの? 悲しいの? 言ってごらん」
知っているから。その先を。乱れて狂ってしまう自分を。
思い知らされた力の差を。嬉々として跪く自分の姿。それもそれすらもこの私なのか。
だめだ、もうそれ以上は。絶対に。
娘が息も絶え絶えに呟く。
「……お願い。もうだめ。知っているんでしょう。知っていて……そんなこと」
「もちろん、知っているわ。お上品で、どうしようもないほど意固地なお嬢さん」
動きを止められて、内側がきゅんと収縮する。
っん…うッ…。眉根を寄せ力なく首を振る。
「…いいのね。もう、我慢しないで」
特に反応の鋭い部分を探り当て集中的に押し上げられると、体がびくびくと痙攣した。
「っくぁぁッ、ぁ…ぁ…は…あっ、ああッ!ぁんッ」
突然たがが外れたようなよがり声になる。
「そう、ここが弱いの、これは?」
「ぁあ、っ」
「大丈夫。わかっているわ。これでしょう。ここが。好きなのね」
ン…ンン――あとは嗚咽になる。
「あら…もういっちゃうの?」
涙が頬に流れ落ちた。嗚咽をとめることができない。もう自分を保っていられない。壊れてしまう。
洟を啜り上げられる。
「ふふ、いいのよ。壊れてしまえばいい。私の手の中で。何も心配することなんてないのに。
これを望んでいたでしょう?」
考えるよりも先に、反射的に首を振っていた。
「わかっているわ。それを認めることができないのが、あなただから」
静かに女が呟いた。
「何も言わなくていいから後ろを向いて。お尻を上げるのよ」
細い腰が震える。そうすることが、この局面を乗りきるただ一つの方法だとでもいうように、
黙って言われたとおりに動いた。口を聞かずに従って、肉体的な責め苦や愉楽を乗りきっていけば
そうすることで、内面の危機さえも乗り越えられるかのように。唇がわななく。
膝をついた姿勢が、屈辱感を高める。背後からの結合が一層奥深くまで追いたてる。
「ぐく…う…あっ、あッ」
握り締めた白い布に、涙と洟の滴が降り注ぐ。
やがて気づかぬうちに自ら腰を振ってしまうだろう。あの視線に射られていないだけましだ、と思った。
淫魔が後ろから深く貫いたまま娘の体を抱き起こし、鏡に向かって開いてみせる。
「ほら見て。ありのままの姿が映っている」
とってもいいわ。自分でどんな顔しているかわかる?
羽交い絞めにされて、体が少し浮き上がる。太い杭に串刺しにされた姿が。
「あぁ……」
体が震える。その内側すらも意識しないままにぶるぶると震えて
中を苛む欲棒に縋りつき、握り締めてしまう。そうしてさらに硬く、心までも抉られる。
「あなたみたいな自惚れやさんは鏡を見るのがお好きでしょう? 目をそむけないで見るのよ」
横を向いた顔を顎の下を掴んで正面に向けさせる。
涙に滲んだ視界に映る、紅潮しほころんだ顔、胸を弾ませ喜びに打ち震える可憐な娘の姿。
狩られるための獲物、美味で傷みやすい新鮮な供物。闇の支配者に謹んで捧げられるもの――
それが、自分の姿だとは。それを望み、涙と愛液をとめどもなく滲ませているとは!
そして……そう。その結末はもちろん誰よりもよく知っている。
支配者の牙を受けた娘は、無限のエクスタシーに身を震わせて歓喜のうちに自ら命を捧げるのだ。
「信じられない? まだ罠だと思っているかもしれないけれど……教えてあげる。
あなたには媚薬や魔術など必要なかった。あなた自身の業が深いから自分から望んで堕ちていくのよ。
それが熟していくのを見つめているだけでいい。もともとあなたのなかにあるものが芽吹いて花開くまで」
その言葉を裏付けるように、赤く口を開いて受け入れている部分に指を伸ばし、
膨れ上がった蕾を摘み取る。
「…く…ぁぁッ…だ…だ、め…!」
とろりとした蜜を溢れさせる。ビクビクと体を震わせながら力が抜け
更にきつく深部へと呪われた屹立を誘い込もうとする。
もう強いるものは何もない。それが何より効いた。
意思に反して奪われる。嬲られる。圧倒的な力の前に屈服する。という言い訳を封じられて
浅ましく求めているのは自分なのだ。嫌というほど見せつけられ、思い知らされて、なお衝迫は止まない。
打ちのめされてなお、淫楽が一つの頂に結実しようと悶えている。
懸命に踏みとどまろうとしたところを女が見計らったように突く。
「――んぁッッ、っっ」
その現実の前では目も脚も閉じることが叶わなかった。
肉体は信用できない。さんざん思い知らされたではないか。この視界も。
今見えているものは全て淫魔の幻覚が見せているものだ。
目を閉じて。固く閉じて自分の感覚だけを信じるのだ。感覚だけを。
突き動かされ、蹂躙されるこの感覚を? 信じるなんて。
当てにならない。簡単に屈して快楽に泣き叫んでいるこの体。
耳を澄ますと、しんと静まり返った静寂のような気もするし、途切れも無く恐ろしい絶叫が
あたり中に鳴り響いているのにそれが遠い昔から聞こえているので
もう全く感じなくなってしまったような気もする。
自分の意識が、信用できない。当てにならない。
そもそも、こんなに情けないものだったなんて。
ああ、溶け出してしまう。そんなふうに、しないで。そんなふうに、かき混ぜないで。
私の感情を。私の思考を。
言葉を失う。
もう。
あ…。
ん。
女が再び自分の体の上にいる。びちゃびちゃと淫らな音を立てながら喰われている。
指が女の尻を掴み、引き寄せながら後ろから女の秘蜜を探る。そこからも熱い液体が流れだしている。
こうして交じり合い混じり合っていたら、いつか一つに蕩けてしまうだろうと思う。
指が吸い込まれていく。肉襞ごしに、今も自分を抉る熱い楔の硬さが感じられる。
頭の中では絶叫している。もう抑制がきかない。
動きが激しくなる。しがみつく。咳き込むような激しい発作のような呼吸。
「ああ、そんなにあせらないで。私も我慢できないわ」
「…いっちゃうの?」
目を閉じたまま、微かに頷く。本当にいく時は声が出ない。涙が滲んでいる。
「目を開けて、私を見て」
顎を掴んで命じられる。――これで最後よ。言って、それを望んでいたと。
あぁ…ゆるして…もう。お願い…だから。
恐る恐る目を開けた。淫魔の瞳に覗き込まれ、それだけで達してしまう。
その瞳。なにものも映さない深い湖のような色。
どれだけ多くのものがその底に引き込まれ沈んでいったのか。
口を大きく開き、息がうまく吸えないかのようにぱくぱくと開閉する。
「…っ」
瞳の焦点が合わなくなった。新たな涙が頬を流れ落ちる。奥歯ががちがちと鳴る。
闇の中に墜落する。深く深く身も心も沈降していく。
もう二度と浮上できない海溝の底へ。
震える体を強く抱きしめて、淫魔が呟く。
「良い子ね。ご褒美をあげる。あなたの中に注ぎ込んであげる、たっぷりと。私の毒を」
叩きつけるように体が跳ねる。どぷっと音を立てて弾け、最後まで抑制されていたものが解き放たれた。
「――――ッッぐクッ」
注ぎ込まれた娘の喉の奥が鳴った。虚ろなまなざしが、淫魔の表情を映している。
力を失った指先がわずかに動く。拒むこともなく全てを呑みこんでいく。
――そう。そうよ。受け止めて。最後の一滴まで。植えつけてあげる。虚無の種芽を。
あなただけが受け止めることが出来る、この私の思いを。
力の抜けた女の体が、娘の上に重なる。
眉を寄せた、その表情に、彼女が見せようとは思わなかったものを、確かに見たと思った。
燃えるような熱さではなく染みいるような温かさの快楽がある。
内側からこみあげる感情すらも超えて、ただ触れ合っている皮膚の感覚だけで
こんなにも落ち着いて満ち足りた気持ちになれるとは。
解き放たれ、すべて流れ出してゆく。言葉を失って温かい海にただ漂っている時。
女の肌に赤く浮かび上がる接吻の痕跡に触れる。猛烈な嫉妬に襲われた。
敵わぬのなら、せめて、自分の印を刻み付けたい。指先で触れ、噛み付いた。
ふいをつかれ抵抗できずに、女が呻く。吸血鬼の力はない。ただ歯形がつくだけだ。ギリギリと噛み締める。
女の顔が苦痛に歪み、やがて官能的な表情に変わる。
今の自分では白い肌に傷をつけることもできないのか?
やるせない気持ちになってそのまま柔らかい肌を噛みしだく。
その腕に抱かれていると、眠気を誘う甘い香りがした。
五本の指を絡めあう。長い髪が一つに溶けあって白い寝台の上に流れている。
果てしない虚脱感に包まれていた。
懐かしい記憶が巡る。限りある肉体を捨て去った時。そして魔王に完膚なきまでに叩きのめされた時。
かつて、この眠りを知っていた。もう随分長い間ゆっくり眠ったことなどないような気がする。
このまま心地よい波に揺られ、漂って、溶けてしまっても構わないような気がしはじめていた。
その果てに、この眠りが得られるのなら、
認めてもいい。
傍らの女の寝顔を見つめる。全てが罠であっても構わない。
もしも全てを奪われたら、甦るだろうか? この私は。三たび甦ることが出来るだろうか?
三度目は恐らくないだろう。
いや、決して。
奪われることなど、断じてない。
――甘やかな闇の香りに、血の欲望が目覚める。
はっと起き上がり、鏡を覗き込むと二人の女の姿はなかった。鏡は何も映さない。
空虚な寝台が映っているだけだ。
蝋燭の炎が柔らかい光を投げかける。部屋の中に、悪夢の残骸はどこにもなかった。
指に、いとわしく絡みつく薄緑の髪を除いては。
*
薄緑の長い髪を梳かしていた時、鏡の中に閃くものを見た。
立ち上がって窓辺に向かい、待ち受ける。黒い蝙蝠が彼方の森を越えて訪れるのを。
「来るならもっと早く教えてくれればよかったのに。私が欲しくてたまらなくなったのならいつでも歓迎するわよ」
艶のある黒い翼を震わせ蝙蝠が消えた後に、闇の貴公子と呼ばれる男が
夜の女王の露台に現れ、長身を優雅に屈めて謁見を願い出る。
「これはまた、身に過ぎるお言葉、痛み入るな。ちょっと尋ねたいことがあってお邪魔した。
例の悪趣味な夢は、君の仕業か?」
「何のこと? 知らないわよ。あなたの見る夢なんて」
女はいたずらっぽく笑う。
「私の夢を見たの? どんな? いらっしゃいよ。そんな夢なんて及ばないほどの思いをさせてあげる」
腕を取ると、偶然を装って彼の股間に触れ
「さあ、こちらにいらして、お嬢さん」
と笑った。
「やはりそうか。君も随分暇と見えるのでお慰めに参上した次第だが、
そういうことなら早々に帰らせてもらったほうがよさそうだな」
吸血鬼は渋い表情を隠そうともしない。
「待って。せっかくまたこうして会えたんだから、ご機嫌を直して。お願いだから。あなたが欲しいの」
速攻で得意技に持ち込もうとする淫魔には呆れたものだ。
しかし今宵ばかりはこれ以上の舐めた振舞いを許さない心積もりがある。
「なんだと?」
「聞こえたでしょう」
「もう一度そのありがたいお言葉賜りたいものだな」
吸血鬼の不敵な態度に冷たい情熱と甘い憤りが込められている。
「……」
無言のまま身を翻して室内に戻ろうとする女の腕を掴み、抱え上げて、横抱きにする。
すぐに首筋に白い手が絡みついた。
唇を奪ってなし崩しにしようとする女の意図を素早く読みとり、髪を掴んで引き離し、首を遠ざけておく。
その手は食わない。
「まだだ。さあ、言ってみせろ……その口で。私が欲しいと。言えば、存分に後悔させてやるぞ」
赤い瞳が、瞬きもせず生贄を射すくめる眼光を放っている。
珍しく女が先に、殊勝に目を伏せた。
「あなたのが欲しい」
吸血鬼がにやりと笑い、舌なめずりをする。
「……ちょっと違ったようだぞ」
「――ふふ。いいじゃない。同じことよ」
面をあげ、目を半ば閉じて含み笑いをした女の艶やかさに酔わせられる。
頬を寄せ、そっと囁く。
わずかな隙を狙い伸びてくる淫魔の舌を、顎を引き、額をつけ、巧みにかわしながら。
「礼をしに来てやったのだ。あの夢の。……だからそれはもっと後で聞かせてもらおうと
思っていた言葉なのに、興を殺がれたぞ。まあ、いい。
この目に映る全ての場所に喜びを与えてやろう。
感覚すら忘れていた、君が自分のものとすら知らなかったすみずみに至るまで」
「見えないところにはくれないの?」
「それは君の心がけ次第だな、我が女王」
そうして、首にかかる腕にその身を委ねる。
――確かにそれは既視感のある光景だ。
体の上で身をくねらせ踊る、美しい女を眺める。目を閉じ仰け反った姿。
その喉が勝利の美酒を飲み干すように蠢いている――
だがあの夢は不吉な予兆などではなかった。お前の意図とは違ったかもしれないが。
モリガン、と初めてその名で呼んだ。
腰骨を掴み引き寄せて更に強く結び合い、更に深く絡ませる。指と、唾液と、体液と、
視線とを。
しばしの沈黙があった。
「何を考えてるの」
「……君のことだ」
「ねえ、私のこと考えた? あの夢の中で出会う前に、私を夢見た?」
「知らないのなら教えてやろう。吸血鬼は夢など見ないものだ」
「あら、そう? 魔王の称号は違うのかしら」
「違うな。既に目の前にあり手に入れたら終わるようなものは違う。
夢は追うことに意味があるのだろう? 叶うか否か結果だけではつまらん。
意外だったか。君には叶わぬ望みなどないだろうからな」
からかうような口調に、さあ、望みもしないことはたくさんあるわ、と淫魔は溜息をつく。
額に垂れ落ちた髪を掴んで問いつめる。
「この私はどうなの? 夢のない吸血鬼様」
「君か……」
乳房を弄んでいた手が離れ、近づけた頬を撫でる。
滑らかな動きで姿勢を低くし、腰を軽く浮かせながら
あの瞳が覗き込む。目を合わせた者を引き込まずにはおかない深く暗い水面が。
「私も手に入れたら終わってしまう、獲物の一つ?」
「フン、また心にもないことを」
「ねえ、お願いがあるの、もう一度…」
「まだ終わってもいないうちからもう次のおねだりか?」
「違うの。真面目に聞いて。もう一度、呼んで。私の名前を。あなたの声が好き」
皆、私の名を知る間もなく果ててしまう。恍惚の表情を浮かべて。生き延びたものはいない。
誰一人として。誰も皆自らの欲望に溺れて滅びていった。
「切羽詰って私を呼ぶあなたの声が、たまらなく好きなのよ。ねえ。いいでしょう。私を喜ばせて」
ああ。嘘つきめ。とうに承知だったのか。私が幾度お前の名を呼んだか。夜毎のお前の悪夢の中で。
「ふっ…呼ばせてみろ、さあ」
促すように強く突き入る。
やるがいい。あの時のように。滅びても構わないとすら思えたあの時と同じく。
早く。
私を追い詰めろ。
淫らな魔女よ、お前には感謝している。この身に滾る血の歓喜を思い出させてくれたことを。
感じたことがあるか。一度でもあるのか、今なお心の中に思い起こすだけで焼き尽くされるような絶頂が。
お前にかかっては皆養分に過ぎぬ。限度を知らない渇きが周りのもの全てを枯らしてしまうだけだ。
気づいただろう。虚無の味は私にとって目新しいものではない。
闇の甘さを知っているだろう、とお前は問うた。知っている。そこに何もないことを。
期待させて何もない。その不毛な憧れこそお前の好むもの。お前を増長させるもの。
哀れな――。
未だ至福の時を知らぬまま、幾千万の男と交わろうとも決して得ることは出来ぬ
命燃え尽きる瞬間を求めてさまよう、哀れでかわいらしい女。
いつかこの手で葬ってやろう、お前の想いを。
そしてお前を。
「モリガン――ッ」
葬ってやる。
礼には及ばぬ。それが譲れぬ我が心。
2005.10
menu