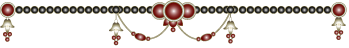熾火のように暗い欲望が彼を苛んでいた。決して甘い感情ではない。
M……。その名を呟けば、感傷を誘うどこかノスタルジックな響きが
狡猾な舌先のようにそっと忍び込み彼を内から弄ぶ。
いつまでも澱のように絡みついて、油断すれば精神までも果てなく毒されていきそうだ。
これが淫魔の本領か。
先代の魔王も考えたものだ。今にして改めてその偉大さを思い知る。
後継のあの女は秋波ひとつの色仕掛けで敵をその野心ごと挫くこともできるだろう。
甘い言葉に乗せられ駆け引きめいたやりとりに一喜一憂している場合ではない。
もしも、実力で遠く及ばないとしたら――?
考えたくはなかった。力で敵わないのに、どうして打倒することができる?
結果は見えている。自滅するだけだ。
これで終わりか。魔界を統べる力など望むことがそもそもの間違いなのか。
デミトリは闇雲な自信家なのではなかった。自ら恃むところがあるからこそ
大いなる意志とでもいうべき流れの存在を感じている。信じている。
何事もその流れを味方につけなければ上手くはいかないことを、経験で知っている。
やってきた好機に上手く乗ることはもちろんだが、それを呼び寄せるまでの器量を備えるべく
努力を厭わない。自分が再び甦ったことには何らかの意味があるはずだから。
その野心の底にはかつて人間であった頃の名残か、今なお掻き立てられる郷愁と憧憬がある。
あえて理想と呼ぶことはしない、秩序と調和とが支配する永遠の静謐。
そこに、わずかな不協和音も存在しないわけではない。
ほのかな不安を呼び覚ます、短調の響きのうちならばなお美しい、儚い輝き。
それらはそもそも普遍の美とは両立しえない、彩りとしての束の間の乱調でなければならぬ。
猥雑さというものを彼は好まない。
葡萄酒が育った土地や気候を雄弁に語るように、血からはその人物の由来、感情が読み取れる。
純粋な、苦味を知らない処女の滴は特にお気に入りだ。
ひとたび精液を啜った体、破瓜の痛みと肉の欲望を知った血はそこから腐敗が始まる。
その腐臭を好む通人気取りの輩も多い。上手く制御できさえすれば
確かに黄金の輝きと禁断の甘さを誇る極上の貴腐となる可能性を秘めている。
だがそれはあくまで稀なことなのだ。
朝日に散る玉響の夢ならばそのひと時を愛し耽溺することもできよう。
それが、調和を乱し、果ては秩序を瓦解させる危険さえ孕んでいるとなれば……話は全く異なる。
恐ろしいのはその虚無だ。知らぬ間に蝕まれ、内部から喰い尽くされる。全てを崩壊させる罠。
だが、そうと知ってもなお惹かれてしまうのは己の弱さ故なのか。
一層激しく、絶望的に魅せられている。苦い敗北を味わって以来、破滅への恐れと、
それに相反する感情が強固になっている気すらするではないか。
こんなにも過度に繊細で気持ちが揺れ動くのは、あるいは、昨晩啜った娘の生き血のせいか――
声も立てずに涙を流し、腕の中で細い体が、未知のエクスタシーを迎えるようにがくがくと痙攣して
目を見開いたまま逝った。名をなんといったか。聞いたような気もするがもう思い出せない。
あの味は覚えている。少女らしい夢見がちな、甘い感傷の多い味だ。もう少しドライでもいい。
意外に垢抜けない村娘などのうちに虚飾を拒む乾いた味わいがあるものだが――。
とにかく、と彼は無理やり迷いを振り切ろうと試みる。
あの女が意識していようといまいと関係ない。
これが「魔王」の仕掛けた罠・戦いならば、避けては通れぬ宿命ならば。
それが万象の摂理というのなら――
望むところだ。受けて立とう。たとえ呪わしき神の与えた試練だろうとそれを乗り越えてみせる。
城に夜が渡り、悪酔いのようなとりとめもない思いは巡る。
*
一人物思いに耽っていた吸血鬼は、寝室――とはいっても本当に眠りにつく時には
棺桶の中だから逸楽のために用意された部屋だ――の隅の大きな鏡に見入った。
ふとそこに何かが息づく気配を感じて。
鏡の中から一人の人物がこちらを見つめている。
ほっそりとした体。血の気の薄い肌。ゆるやかにウェーブのかかった色の濃い金髪が鎖骨にかかる。
濃紺のスリップドレスを纏い、下半身は半ば隠れているが四肢がすらりと長い。年のころは十七、八か。
一見温雅で清楚な令嬢の風情だが、濃いまつげに縁取られた琥珀色の瞳が冷めた光を放ち
意志の強さと気位の高さを感じさせる。薄い唇がへの字に曲がって不機嫌な表情ながら、
内に秘めた暗い情熱に吸い寄せられるような美しさのある娘だ。その姿はどこかで知っていた。
吸血鬼の姿が鏡に映らないのは魂を持たないからだという。
ある意味で正しく、またある意味で間違っている。
そもそも人智の及ばぬところから魂を定義づけても意味がない。
実際言えるのは吸血鬼本来の姿を映し出す鏡が人間界にはないということぐらいだ。
所詮、人は見たいものしか見ないのである。鏡の中に限らず、見出したいものをそこに見つけ
これこそ探していたものだと思うだけではないのか。
皮肉な笑みを浮かべ、映らないはずの鏡像と向きあう。
普段の青年貴族の姿とは大分異なっているが、それが自身を反映したものだと直感で悟った。
ならばこれは。人間界における魔力を失った我が「魂」とでもいうか?
勝手にするがいい。今となってはそもそも人間の形すら、かりそめの姿にすぎないのだから。
また違った貌の、己が姿にむかって片目をつぶってみせると、娘が冷たいウィンクを返した。
部屋の空気が振動し、蝋燭の炎が激しく揺らめいて消えた。
煙の匂いと生暖かい風の流れを感じたその時、鏡の中の娘の背後に別の女の顔が浮かび上がった。
思わず息を呑む。徐々に全身が明らかになるその姿は、見紛うはずもないあの淫魔だ。
どこぞの乱宴に招かれた後なのか、今宵はロココ調の小姓のなりをしている。
闘牛士のようなぴたりと脚線に沿った真紅の膝丈のパンツ。薄緑の髪が一つに束ねられている。
白いフリルのブラウスの大きく開いた胸元。首筋から谷間に至るまで、肌を飾るアクセサリーのように
愛咬の跡をいくつもつけている。あるいはそれが今宵屠った獲物の首級がわりなのか。
「マキシモフ公はお留守かしら」
聞き知った澄んだ女の声が耳を打つ。鏡を見つめたまま振り向かなかった。振り向いて目を合わせたくなかった。
「……なんてね。ご無沙汰したわね。フフフ、お見通しよ、そこのお嬢さん。
それでかわせると思ったら大間違い。残念だけど、覚悟を決めてもらおうかしら。
この私に狙われて逃れられた者はいないわ」
一歩、また一歩とその声が近づいてくる。もう、すぐ後ろにいる。
「こんな格好で」
頬をつねられた。
「待っててくれるなんて。いけない子ね。ね、あなたもそう思うでしょ?
何も知らないうぶなふりしてみせても無駄よ」
無理やり引き上げられた口角から指が侵入し、歯を探る。本来の力が失われていることを確認するため、
というよりは、獲物自身に去勢された事実を示すためなのだ、と感じた。
鏡の中で瞬間、視線が絡み合う。
娘は唇を噛み締めて、きっと前を見据えた。搾り出すような声で言う。
「私に触らないで。下がって。あなたに用などありませんから」
精一杯気丈にふるまってみせているのが明らかだ。
ふうっ、と煙草の煙を吹きかけるような吐息が頬にかかる。
乱れた夜会の熱狂と酔いの残滓か、ねっとりとした妖気と不思議と心地よい香気とが混ざり合って漂った。
「かわいい唇で、つれないこと言って。そんな手管どこで覚えてきたの? ねえ」
量感のある乳房が背中に触れた。熱い吐息が髪を揺らす。顎の下を爪で掻かれる。
寒気が走った。感覚が研ぎ澄まされ、些細な動きにも敏感に反応してしまう。
よりによってこの女を前にした今この時に、肝心の自分自身が身も心も常になく頼りなく、
見かけどおりに、いやそれ以上に傷つきやすいことが腹立たしい。
哀れな娘の顔はあせりと怯えを隠せないでいる。
「でもね、知っているのよ。いつも私のことを想っていてくれたでしょう。
かわいそうに、美しい夜を愉しむことも忘れて、眠りにつくこともできずじりじりと昼の光に灼かれて。
あなたの気持ちが嬉しかった。だからこうして来たの。感じられたのよ。私を呼んでいるのが。
ねえ、教えて。腕に抱いた女が私だったらと夢想したことはある? あの日から、私を想って何回いったの?」
淫らな囁きに思わず耳を塞いだ。
「やめて。やめて…そんな話聞きたくない。これ以上私を侮辱することは……ゆるさない」
「うふふ。赤くなったわね。まあ、いいわ。お話はおしまい。お楽しみにいきましょうか」
後ろから腕が首の周りに絡みつき、そのまま抵抗する術もなく仰向けに寝台に引き倒された。
立ちはだかった女が腰に手をあてて、足元からこちらを眺めている。
何かを言い返そうとしても舌が凍りついたように言葉が出ない。
後ずさりしながら必死に蹴りだした脚を、女は容易く掴んで取り押さえてしまった。
細い腕なのに強い力だ。その場に動けなくなる。
女は足首を掴んで引き寄せると、その足を愛おしいもののように自分の頬に押し当てた。
驚きに一瞬抵抗を忘れた娘の、揺れる瞳をじっと見つめたままで
淫魔が笑みを浮かべその素足に唇をつけた。
「っ…」
引き締まったくるぶしが引き攣れ、小さな五本の指が縮み上がった。
白いあなうらに写った女の紅がかすれた血のようでもあり、乾いた泥のようでもある。
親指が赤い口に含まれていく。温かく湿った感触。指の間に舌が入り込んだ瞬間
股間から脳天にきゅっと痺れが走った。このまま腰を落ち着けてはいられない、
むずむずとした気持ちが悪いような、いいような、中途半端な状態。
寒さに震えていた時に、生温かい水溜りに尻餅をついてしまったような……。
足の指先が音を立てて吸い上げられる。
膝の裏側がぶるぶると震えた。足の付け根がじーんと麻痺してくるような感覚がある。
女はそんな娘の反応などお構いなしで、手馴れた作業を進めるように
スリップドレスの裾をつっと捲りあげ肉付きのよい火照った太股を露呈させた。
そのまま、股間へと手が伸びてくる。体を固くして次なる侮辱に耐えようと身構える。
下着の上から触れられたくない部分に触れられて、ひっ、と息をつめた娘の喉の奥が鳴る。
女の指先にも湿った感触が伝わったはずだ。何も言わずに笑っている。
「遠慮しなくていいのよ。何でもかなえてあげる。あなたが期待することをしてあげる。ほら……」
手をとって導く。自分で見たことはないその場所は布の上からでもぬるりと滑った。
明らかな形象で表にあらわれていない分、計り知れない底無しの淵がそこにあるような
予感がして恐ろしかった。懸命に声を張り上げる。
「用はないと言ったでしょう。思い通りにはならないから」
動揺を悟られぬよう手を振り払い、顔を背ける。くっつけて立てた膝が震えてぶつかり合う。
「あくまでしらを切るつもり? ふふふ。本当に知らないとしても、
あなたは自分の気持ちに気づくのが怖いだけ。目覚めさせてあげる。身も心も。
自分からそんな姿でいて、しかも私を誘おうなんて、本当に侮りがたいお嬢さんね」
嘲笑されて、望んでこの事態を招いたわけではない、と強く思う。
「せっかくだからその体を見せてちょうだい。脱いで」
ふくらんだ胸の先に一層敏感な部分がすでに痛いほどはりつめている。
薄い生地ですら重くひっかかりを感じるようだ。鋭い視線を避けるように両手で胸を庇う。
その視線に心までも見透かされたくないから。
「強情なのね。あなたらしい。でも、泣いても許してあげないわよ」
女は寝台に上がってくると娘にのしかかる。
肩を掴んで押し返し、魔の手から逃れようとする娘を組み伏せると、その胸のふくらみを乱暴に掴みあげた。
「やめて、痛い」
まだ固さの残る乳房を握り、なめらかな絹の上から咥える。蛇のような長い舌が音を立てて先端を舐める。
「うっっ」
固く目を閉じ、刺激に耐えようとする。だがそんな狼藉に、どういうわけか何かが呼応し始めている。
それだけでどうにかなってしまいそうなほど一気に燃え上がり、両手から、全身から、抵抗する力が失われる。
一方の乳首だけが執拗に舐め上げられ、もう一方を触れるか触れないかの微妙な距離で掠るように
手のひらで円を描きながら撫でられている。その対比が娘には耐え難い。
「ッ…ぅ…」
同じ勢いで責めたてられれば、なんとかやり過ごす道をつかめそうなのに、
早くも我慢がきかなくなってくる。苦しげな呼吸を続けるのが精一杯だ。
「どうしたの」
「は……、ぁ…っ…」
「なあに。はっきり言ってごらんなさい」
大きく膨れ上がった先端を爪の先で弾かれ、一際鋭い快感が突き抜けていく。
「…う…くっ!」
「気に入ったの、これが。こっちもして欲しいでしょう?」
うっかりと喘ぎ声を上げたりしないよう、歯を食いしばり固く唇を結ぶ。
「ンンッ」
「して、って言ったらしてあげるわよ……あら、言えないの?」
「……」
「どうなの?」
つん、つん、つ、つん、と責めが続く。舌先も、微妙にポイントを外して焦らせている。
娘の長い睫毛が、滑らかな頬に暗い影を落とし心の震えを映すように揺れる。
ひとしきりいたぶって反応を楽しんでいた女は
固く閉じられた口がついに開かれないままであるのを見てとると
「あなたが強情っぱりだというのはとてもよくわかった。そういうところもたまらなくそそられるの。
でもね、もう我慢しなくていいわ」
首筋に落ちた後れ毛をかきあげてから長い髪を束ねていたスカーフを外した。
暴れる娘の鼻をつまみあげ、息をするために開いた口に布をかける。
「んっ」
舌を押さえられ、言葉がうまく伝わらなくなった。
冷たい視線に見下ろされる。
「これで、もう言いたくないことを言う必要はないわよ。何か言いたくなったとしても聞こえないもの」
娘の一杯に見開かれた瞳が微かに哀願の色を帯びる。
震える体。唾液に濡れた生地が肌に張り付いて乳首の隆起を目立たせている。
肩紐を掴んでひきずり下ろし、露になった乳房に再び舌を這わせる。
音を立てて吸い上げ、歯をたてる。つまんで引っ張りあげる。唾液に濡れた先端に爪が食い込む。
「…、く……っん! ん、んぐっ…うう…」
口を覆われると、不思議と抑えていた声が出た。言葉にならない叫びが。
肩にかかった娘の指が、次第に必死で縋りつくような力になったことに満足したのか、体を離し
女がブラウスを脱ぎ捨てた。
不敵な白さを湛えた柔らかな肉が、外気を吸い込むように広がり出て
きゅっと上を向いて収縮する先端までさざなみのような速い鼓動を伝えている。
娘の手をとって引き寄せ、その胸に触らせる。わざとらしく身をくねらせ、悩ましい声をあげてみせる。
「あ…はァ…、あぁん…つめたいわ……あなたの指」
強張った指に女の乳首が意思を持って起き上がり自ら絡みついてくるようにすら感じられた。
指を曲げると手の中にしっとりとした肌が蕩けだしそうな熱を伝える。
女の酔ったような瞳に見つめられ、その反応に戸惑う。
「ねえ、どうしてそんなに冷たいの。あなたの指も、あなたの心も。
どうして一緒に燃え上がってはくれないの? 感じるでしょう、このときめきを。
わかっているはずなのに、こんなに切なく求めている気持ち」
擦りつけられる、ぴんと張った乳首の先が、娘の同じ部分を挑発する。
こごった尖端が柔らかく形を変える土台の上で、それほど強い力のかかるはずはないのに
びりびりと目の奥まで痺れるほどの刺激をもたらした。人肌のぬくもりが確かな重量を持って
生娘の体を埋め尽くす。速い波が襲ってきて足元を攫われそうになる。
首を振り激しく抵抗した。女の媚態と、自己の感覚に。
思わず目を閉じた。溜息をつく。ああ、あぁ…。また大きく、息をつく。
呼吸が苦しい。
たくしあげられ腰の下で皺になっているスリップの裾にまで、あふれ出た愛液がしみをつくっている。
言い逃れのできない欲情の痕。
腰を抱えて下着をするりと尻の下から抜き取られた。裸の肉に麻の敷布が冷たく触れる。
脚を持ち上げられたまま、視線が突き刺さる。その呪縛からなんとか逃れようと腰が動く。
触れずにじっと見られていることがかえってその部分を強く意識させる。
閉じたいのに閉じられない唇が、塞がれた口のかわりに、女が望むままのことを告げてしまいそうだ。
だらしなく涎を垂れ流して。
馬鹿な。こんなはずではなかった。非力であることの悔しさ。こんなに脆いとは。もう涙すら浮かんでいる。
こんな定石どおりの責めに何よりも自分自身がされるがままになっていることが許せない。
憤りを込めて睨みつける。睨みつけようとでも意識を保っていないと、すぐにも攫われてしまいそうだった。
罠だ。これは淫魔の……。このまま、なす術もなく餌食になるなんて。
「ふふふ、そんなに怖い顔して睨まないで。美人が台無しよ。もっと素直になって。
今日はあなたに素敵な贈り物があるのよ。見せてあげる。あなただけに特別に」
淫魔の目がぎらぎらと妖しく輝いている。
「せっかくだから、感想を聞かせてほしいわ」
ぐっしょりと濡れた猿轡が外された。吸い込む空気が冷たい。
脳に酸素が送り込まれ意識と視界と感覚とが鮮明になっていく。
身に着けていたものを全て脱ぎ捨てて、女が向き直った。
膝立ちになり、わずかに腰を前に突き出している。股間を覆っている手が、開いた脚の間をするすると這いながら
引き締まった腹部に向かって上っていく。
「――どう?」
酷い夢だ。綺麗な女の体なのに、その股間にはおぞましい野獣の器官がそそり立っている。
月の光を受け傲岸なまでの清らかさを映す肌の下で、そこだけが赤黒く異質な鈍い光を放っているかのようだ。
「気に入ってもらえたかしら?」
誇らしげな笑みを浮かべる女の細い指が、裏側から筋をたどってつうっと反り返った先まで撫で上げた。
透明な液体が指に糸を引く。濡れた火口が小さな泡つぶを一つ吐きだしてぴくっぴくっと息づいている。
思わず視線がひきつけられてしまうのを意識するように、くいくいっと指先で尖端を動かしてみせる。
「うふふ、なかなか素敵な大きさでしょう。これはね、あなたの誇り高さなの」
自在に形を変える蝙蝠の翼にも似て何で出来ているのかわからないそれは、確かに並みのものではなかった。
爪の長い女の指でも、丸めた輪の中にはとうてい収まらない太さがあり、
優に臍を覆い隠すほどの長さで、なだらかな女の下腹の曲線に張りつく勢いを見せている。
「わかっているでしょう、これを受け入れて欲しいの。あなたの中に」
卑猥なしぐさで腰をくねらせる。大丈夫よ。ゆっくり、優しくしてあげるから。
「そんな…」
語尾はかすれて消えてしまった。それは予想を超えた事態だった。
鞭のように、ぴたっぴたと凶器が頬に打ち付けられる。
「まずは、お口で味わってみる? とっても甘くてくせになるわよ」
思わずあげた悲鳴に、淫魔がおかしくてたまらないという様子でくくっと笑った。
やはり自分が間違っていたのか。全て見透かされている。対抗できるわけがない。
そんなものを、そんなものでこの自分を嬲り楽しむつもりか……。
悔しさよりも先に、恥辱に耐えられない心が、くじけて降伏に逃げてしまいそうだ。
だがそれで悪夢は終わらないのだった。
瞬きすら忘れていた目にじわりと涙が滲む。
「泣くことはないじゃない。考えてもみなさいよ。私だから優しくしてあげられるのよ。
闇の住人たちならどうするかしら……? たちまち八つ裂きにされてしまうわ。
かわいそうに、きれいな服も髪も顔も体も台無しよ。
このかわいいおっぱいに、獣の歯形がついて、きれいな乳首は噛み切られて
それからここも、きれいな色をしてみずみずしく潤っているところも
無理やり押し広げられて、引き裂かれて、血まみれになって、泣いても叫んでも誰も助けてくれない。
ばらばらになった肉片までも、屍鬼に喰い漁られて。素敵な棺桶で眠ることも叶わない。
ふふふ、でもそういうのもお好きだったかしらね。残虐で冷徹な闇の帝王にはその方が、
より相応しかったかもしれないわね。本当は。うふふ……。
私の慈悲で、今日のところは上のお口は勘弁してあげる。
だけど、かわりにこれを自分でいれてもらうわ。あなただけのものなんだから。さあ」
「な…」
絶句し、唇を噛み締めた。これ以上この女の前で醜態を晒したくない。痛みならば耐えられる。
こんな嘲弄を許してはおけない。だが……。
この程度でうろたえたりしてはならない。唇がぶるぶると震える。
なんとしてもこの挑戦、受けてみせなければ……。
揺れる体を起こし、細い腰の周りに皺になって絡まっていたドレスをかなぐり捨てた。
女が横たわっている。白く美しい裸体だ。限りない聖性すら帯びた体。
この寝台に横たえて、目に映る全ての部分を思うままに愛でた数多の記憶の中のどんな肉体も敵わない。
それは、この、おぞましい狂起のためではないはずなのに。意識を逸らすことができない。
処刑台にあがるような緩慢さで女の体を跨ぎ、そこにむかって膝を進めた。
叫ばずにいられるだろうか、と自問する。この頼りない体と繊細な神経が恨めしい。
左手を伸ばし、それを掴んだ。手に余る太さだ。右手で自分の股間を触ってみる。
ぽってりと膨らんだ唇の、裂け目の更に内側にどろどろに濡れた粘膜が
口を開け息づいている。だが、これは……。
とても無理だ。想像するだけで股関節までおかしくなりそうだ。
腰を低くし、指で広げた入り口に尖端をあてがってみる。手で触れた時には感じなかった熱さに驚く。
思わず手を放すと、引き起こしていたそれが秘裂を擦りあげ、また反り返って寝てしまった。
「あァッ…」
一際敏感な部分をはじき上げられて思わず、声を抑えることができなかった。甘ったれたか弱い娘の声。
こんな、今からこんなことではとても持たない。懸命に呼吸を整える。
思い切って中心に指を挿し入れてみる。ぬるり、とそこが自分の指を受け入れた。
細い一本の指でも、骨の硬さや関節のカーブをひしひしと感じる。
これを少しでも広げないことにはどうにもならない。息を少しずつ吐き出しながら、
ぬめぬめと滑る底無しの沼を探っていく。
なんとか人差し指が奥まで入った。入り口が狭いところにもう一本中指を加える。
きつい。関節が当たってじんと響く。あれはこんなに硬さはないはずだが。
締め付けられる二本の指を中で広げる。開いた指の間にまで襞が絡み付いて隙間なく埋め尽くされていく。
指先を曲げる。抉られる感覚が、脳を麻痺させる。く…! こんなもので済むはずがないのに。
膝立ちのまま片手をついて頭を低く下げた姿勢で、全身の慄きを必死で堪える。
そこにあることを知らなかった器官が脈動し、また奥深くからどくりと流れ出してくる。
高くあげた自分の腰の、脚の間から糸を引いて垂れ落ちていくのが見える。
こみ上げてくる涙を女に見せたくはない。首を振る。垂れ下がった髪が女の乳房を掃う。
「いつまでも一人で愉しんでないで、覚悟はできたの?」
鋭い声とは裏腹に、女の手が膝の裏を優しく掴み撫でさする。その感触に何故か涙がこぼれ落ちそうになる。
毅然と顔をあげ、女の挑発に応える意思を示すために、舌を伸ばして、そのくびれた部分を突き舐め上げた。
びくりと更に勢いを増すのが感じられるようだ。口に含む気にはどうしてもなれない。
「あぁ!…ん、そう来てくれると思っていたわ」
女が淫らな呻き声を上げ、満足そうに髪を撫でる。
再び、根元を掴んでぐいと引き寄せる。片手でだらだらと泣いている花弁を広げ、あてがった。
力を込める。鈍痛があるばかりで全く入っていかない。腰を前後に揺すり、滑る裂け目を探る。
ぬる、とわずかに譲る余地が感じられる場所がある。体重をかけて思い切って沈める。
奥歯を噛み締め、叫びを押し殺す。抵抗を打ち破ったと思った。ぎりぎりと歯軋りをする。
かたい。先の鈍い太い杭に肉を引き裂かれる苦しみだ。だが、充分耐えられる。
淫魔の眼光に射られている。銀の銃弾に心臓を貫かれる苦しみだ。だが、耐えてみせる。
そうだ、耐えられる――それで滅びはしない。
かつて、私は負けた。敗北を味わわされた。己の弱さからだ。
一度目は、か弱い人間であった時、限りある生を失って。二度目は魔王の力の前に屈した時。
だから、己の弱さと限界は嫌というほど知っている。だから……、三度目は許さない。許せないのだ。
少しずつ、少しずつ、進めていく。女を睨みつけ、意識を支えながら。
痛みと、屈辱と、我知らず昂ぶっていく感覚を鎮めようとしながら。
奪われはしない。もう揺るがされない。淫魔の操る悪夢などには。
こんなはずではない。欲しければしたいようにすればいい。好きなように蹂躙するがいい。
だがそんな形でこの私を手に入れることは出来ない。声をあげたりしない。屈しない。絶対に。
最初に目を合わせてしまったのがそもそもの間違いだ。
もう二度と目を逸らすことが出来ず、その深淵に引き込まれてしまう。それが手口なのだ。
おぞましい狂喜がじりじりと着実に内部を侵している。ああ、ついに我が領内に侵略を許してしまった。
そこに収まるのが当然とでもいいたげな、この化け物に。なぜ受け入れてしまったのか。
肉体が淫らな魔に侵されようとも心まで染まりはしない、ということは一体全体可能なのか。
などと頭の片隅で考える。これまでの自分ならば、鼻で笑い飛ばしていた。そんな戯言を誰が真に受けるかと。
犯されていくのは一器官に過ぎないと、今はまだ考えられる理性がある。
かつて魔王に敗れ去ったときの苦みが、不吉な予兆のように脳裏に浮かぶ。
――だが結局のところ心すらも一つの器官ではないのか?
遅かれ早かれ侵略を許す、だらしなく制御のきかないものの一つなのでは?
ようやく苦行の終わりが見えてきた。
根元を握った指三本分が残ったところで、それ以上角度を変えても進まない。肩で大きく息をする。
なんとか醜態を晒さずに収めることができたと思うと、奇妙な達成感と征服感が沸き起こった。
ぎっちりと塞がれている内部も麻痺しているのか、痛みや動揺はもうそれほど感じない。
精一杯の虚勢を張って、横たわった女を威嚇する。
「どう。入れたわ。…あなたの言うとおり。これで…これでご満足?
あなたみたいな、いやらしい…淫魔の気まぐれになんてほんと…つきあいきれない」
ぱん、と頬を張られた。淫魔は酷薄な笑みを浮かべている。
「優しくしてあげてるのよ。忘れないで。嫌々つきあわされてるなんて態度はよくないわ。
元はといえばあなたが望んでいたことよ。自分が悪いのよ。これはお仕置きごっこなんかじゃない。
あなたが、自分の敗北を認めるかどうかだわ。そして負けるというのは、この運命を受け入れることよ。
認めるのよ。それを望んでいたことを。ここまで持ちこたえたのはさすがだわ。ほめてあげる。
でもね、あなたのその意地が身の破滅を招くこともあるわよ。
ふふふ。これからじっくりと思い知らせてあげる」