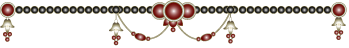うつし世と、かくり世の狭間を彷徨う者にとって、本来冥界は親しい場所だった。
薄暗闇の光が、ものの輪郭を柔らかく照らす。
どんな境界も滲み、半ば溶けている。
闇の濃さも穏やかな深みになってまどろむ。永遠の待機の間――
そんなところにいる救い主というのも、随分おかしな話ではあるまいか?
そしてそんなところに赴く帝王というものも。
「よくお出でになった」
微笑を浮かべて冥府の王は彼を迎えた。
あのような別れ方をして、再びこのようにあいまみえる時が訪れるとは思っていなかったのだ。
魔界の覇権を握った吸血鬼は、表すべき以上の敬意を表して、応えた。
冥王が自分に与するつもりなど毛頭ないのは分かっている。
今の力と勢いをもってすればジェダを倒すことも不可能ではない。ジェダ自身の言うとおり、この時に
倒すべき敵は始末しておくほうがいいのだろう。しかしデミトリはそうする気になれなかった。
すべて片付けてしまったら、この世に何が残るのか。
先延ばしにする事柄はあってもいい。待つ時間はあるのだ。いずれ、また……。
もうそんな話はいい――。
「なんでも手に入れられると思ったら間違いだ……」
長い沈黙の後に、冥王が呟いた。
「君に指摘されるまでもない。よく、わかっている。過ぎた夢を見ればその代償も高くつく…」
「貴方のことを言ったわけではないのよ」
聞き覚えのある声に向き直ると、かの女の姿がそこにあった。
薄闇に佇む恩寵のごとく
眩しいほどの髪が輝く。血の気のない青ざめた肌の色。透き通るような瞳。
確かに見知った姿――まぼろしのようにその肖像を眺める。
「君に…また会えるとは」
「ご機嫌麗しく……なかったようね。陛下。疲れた顔をして。貴方らしくもない」
腕が首筋に絡みつき、引き寄せる。温度を感じない吐息が頬にかかる。
その距離を確保するように、腰に両手を当てた。抱き寄せるためというよりは、
それ以上内部に浸透されないように。
思いを見透かしたように、微かに笑った形に口角が上がった。
「大丈夫。もう貴方を貰おうとは思わないわ。貴方を奪ったりしない」
「奪われるだけのものが残っているとも思わないが……」
ふっと強い瞳の光が和らぎ、腕の中で細い胴が捻れた。
虚像のような姿だが、鮮やかに紅い唇が柔らかく、湿った腔中は唾液が後をついてゆるくまとわりつく。
長く冷たく別の生き物のような舌が探るように動いている。
「何故その姿で、私を惑わせる」
「ふふ。見えるものを信じなくなったの? 偶像崇拝はおしまいにしたのかしら」
顎を引いて上目遣いの視線が誘う。
「来て。でも……意地悪は嫌よ」
「それは、聡明な君の、示唆なのか?」
目を細め、突き出した唇からふっと小さな息を吐いて笑うと
女の長い爪が首筋をかすめ、冷たい指が襟元を緩めて素肌に滑り込む。
緊張した胸をゆっくりと撫で下ろし、また撫で上げる。
ふいに荒々しく抱きしめられ、
冷めているくせに、しっとりとした重みのある胸が気持ちを押しつぶすように圧し掛かる。
「かわいそうに、本当に魂を、貴方の心を抜かれてしまったのかしら。あの、サキュバスに」
至近距離で、挑むように赤い光が凝視する。
その瞳を見ていると、呑みこまれそうな闇を、つきぬけた虚空を感じる。
自身がたまらなく不安定なものに感じられる。
「……」
目を伏せて、呻いた。一方で、その感覚が好ましく思われる。
頑なになって、抗うことはない。
その不安定さがはかない期待を抱かせる。
「そう見えるのか、君には。ならばそうなのだろう。……君だけだ、何もかも知っている…」
「そうよ……。ふふ、やっと分かってくれたのね。今になって」
奪いたいのなら奪うがいい。奪われて構わない。
同化されても構わない。できるというのなら、むしろそれを望みたいくらいだ。
自身が容を失って流れ出す時を。そんな時があるのなら。
屹然たる意志などなくていい。
馴染み、混じり合い、溶け合って、沸き立つ河の小さなうたかたの一つになってしまえばいい、
地獄の業火に焼かれずとも灰になってしまえばいい。この身も、この思いも。
もうそうはなれない。二度とそんな運命は訪れない確信がある。
手をとると指を口に含んだ。視線をそらさずに、舌がくすぐるように巧みに愛撫する。
思わず息が乱れた。
「大丈夫よ」
指を吸いながら音を立てて引き抜くと、瞼に口付けた。
そのまま引かれ、導かれた手の指先がもっと温かな別の唇に触れたのが分かった。
濡れた肉が、口を開けて吸い付くように人差し指に絡みつき、
つつっ、と小さな音を立てて、指を吸いあげ、呑みこむ。
力が入る手首を、女はそのまま放さずに、ゆっくりと動かした。
熱く煮えた果肉が半ば崩れ流れかけている。
冷たい指が彼を握り、いざない、河口へと導く。
進めばその思惑に感染して自分も崩れ始めるのか。溶け去ることができるのか。
あぁ、と冥王が長い溜息をつく。
ちゃぷちゃぷと小さな波音を立てて小川が逆巻いた。
次第に温度と粘度が高まり、ぬるい沼地に落し込まれたような感覚に包まれる。
背骨から首筋がぞわぞわと上がる水位に埋もれて、天地を見失った。
「あ…くっ、っ」
泣き出したいような恐怖と歓喜の錯乱した感覚に捉われ、言葉が出ない。
足元を掬われて、身構えたはずが、予測する転倒の衝撃もなく、そのままいつまでも静かに落下し続けている。
止まっているようにも思われるが、微かに聞こえる空気の流れが、沈みゆく空間の広さと奥行きを告げる。
翼を広げようとしたときに、それが、自身の末端が既に溶け流れ去っていることに気がついた。
天地もなく、光と闇の境もない。
瞼を閉じても開いても、全く変化のない、闇というよりも、無だった。
闇には濃度と匂いがあるものだから……。
*
無に落とし込まれたのか、それとも存在する闇と光を自分が感知できなくなっただけなのか。
こうして、身が溶け、己が解けていったら……
いや、未だ残る意識のほうこそ実体で、肉体はこの世に在る際のひとつの形象でしかない。
思考を放棄して、時のない無限の間に自らを投げ出して、もう二度と回収しなかったら。
この身に流れる無数の血は、どこかへ還っていくのだろうか。
頬に触れた髪の感触が、時間とものの存在を、再び知らせた。
柔らかな女の肉体。確かな感触が異なる二つの物質の境界線を示すように外にも内にも続いている。
目を閉じたままで、冥王の瞳の光を、輝く長い髪が溢れる波のように四方に広がるのを感じた。
畏れに静かに慄く体を、包み込むように女が抱きしめる。髪をかき上げて額に口づける。
その唇を冷たく感じるので、自分が熱を失っていないことがわかる。
閉じた瞼の熱が吸い取られる。瞼の裏に焼きついた情景ごと、記憶ごと吸い上げるように。
薄い皮膜が別離の痛みに震える。
吸血鬼が音も立てず、傷口から流れる血のように涙を流しているのを冥王は知った。
「魂を……、抜かれたのではない。私が自ら望んだのだ。望んでそうしたのだ。
だが、そうならなかった。そうならなかった。だから……」
「……」
「私の力が、私を……裏切った。私の気持ちを。私の、真の願いを。
そんなことがあるだろうか……?」
「私に聞いているの? ……運命が貴方を裏切ったりしないわ」
納得がいかないような表情に、女は穏やかな眼差しを注ぎ、冥王の声が低く届いた。
「本当だ。自分の心だと思っているものさえ、君の自由ではない。
だからそんなに、きつく縛ろうとするな。律しきれるものではない」
――私は器を築いてきた。私が名を与え、混沌が意志になる。
だが、容を与えてやっても、そこに収まろうとしないものがある。
それはそのものが無意識のうちに選んだ道筋なのだ。
選択がなされ、君がここに来たのも……
冥王の述懐を、アリアのように聴いた。その旋律が、響きが心地よい。
あえて、その意味するところを深く捉えることはしたくなかった。
細い髪を撫でていると、精妙な楽器を爪弾いているような心持ちすらする。
響きを生み出している唇の縁に、入り口の形状を確かめる時のように触れる。
「この姿もその器か。しかも、私のために創られた……。そのくらいの自負は許されていいんじゃないか」
美女は開いていた口を閉ざして、渇いた笑みを浮かべた。
髪をかき上げて、胸元を開く。
救世主の、たっぷりと寛容な広い胸が内側から発光するような艶を帯び
眼差しに応じるごとく、ゆっくりとした呼吸にあわせて揺らいだ。
濃やかな視線の愛撫を受け、青白い肌に熟した桃の色をした乳首が起ちあがり
水分を得て膨らむように急激に濃度を増して葡萄酒の色に染まる。
実際に、液体が滲み出ているのだった。
女の細い手が、量感のある乳房を寄せて手首を捻ると
薫り高い血液が勢いよく噴きだし、紅い飛沫が吸血鬼の頬を生温かく濡らした。
虚をつかれたような顔を、髪を掴んで引き寄せる。
無言のまま促され、デミトリは冥府の滋養を浴びた。
牙を立てずとも豊かに溢れ出す真紅の乳汁が、喉を侵略し
乾いた地平を潤すように湧き続ける。
柔らかな乳肉が搾りあげるように捻られその先端が張って舌先に抗する。
無心に吸い上げると、包み込んだ内壁が柔らかく圧力を高めた。
荒々しく揉みあげる動きと、強制的に噴出させられ、きつく吸われる頂点の刺激が、女を昂ぶらせる。
苦しげでいて、甘い声が紅い唇から漏れ出ると、絶え間なく続いた。
*
「こうして、このまま君の中に果てなく堕ちていったら、何処にたどりつく?」
「いつかは志も溶けて、闇の混沌に還るもの」
還るところがあるのなら、闇の混沌ではなく土に還りたいものだ、と吸血鬼は考えた。
だが、既に知っている。その道が滅びに至らないことを。
――還るのだ。そうあるべき姿に、ものの本来の。
「あるべき姿、など……ない。今あるものがそのままだ」
――何故ないと考える? その姿を私は知っているのだ。だからそうではない形が耐え難い。私には。
ないのなら、創りだそうとは考えないか? 君は無から何かを生み出そうとはしなかったか。
自己が無限に増殖していく感覚。どこにでもあり、どこにもない。それは幻覚ではない。現実なのだ。
「もう、夢を見ない。彼方にあるものを求めなくてもよい。あえて追わずともよい。
それを捨てて、この世を得た。私が在ることが、答えだ……。そうだろう?」
死神は黙ってまばたきをした。
――君は私の答えなど必要としていない……。
デミトリは、最後の甘えは突き放されたように感じた。
「死神よ。もしも、もしも、だ。頼んだら…、この私を、救済してくれるか?」
その問いが皮肉や軽口ではなく、真摯に投げかけられたものであることを冥王は察知した。
凍りついた慈悲の手が呪われた帝王の体を抱き寄せる。
「……。もっと早く聞きたかった。その言葉を」
「それが、答えなんだな、君の……。もう私はそれに値しないと」
常に冷静なジェダの目が、ほんのわずかな間、動揺したように見えた。
何かを抑えているようにその声が震え、珍しく言葉を探すように言いよどむ。
――君が自分の夢を……憧れをついには克服し、無にしたと、無に還したと考えるように、
私もまた君を帰し……失ったのだ。デミトリ。君は私を必要とせず、自ら望むものを得た――
「でも、貴方の運命は変わっていない。逃れられない」
「どうやって逃れたのだ。魔王の呪縛から」
「私は…憧れというものを抱いていないから。
貴方自身が縛られているのよ。縛られていたいのよ」
それから、女がほがらかに目を上げた。
「貴方は私を、吸血鬼の虜にして、と言ったらしてくれるのかしら?」
「してやろう。それが君の望みならば」
そうデミトリは返事をした。
女が高い声で楽しそうに笑ったので、つられて笑った。
一瞬さっと真面目な表情になったのを見逃さず、また言わずもがなのことを口走ったと思い始める。
赤い爪の先がからかうように吸血鬼の肌を掻いて、滲み出る血を舐めた。
「時には懲りないのもいいことよ」
「確かに。おかげで冥感を得られた……」
境目は霞み滲んでいるが、決して混じり合うことはない。そうして互いの温度を感じていた。
波のように、形を持たずに一刻一刻に揺らぎ、限りなく近づきながら、
しかし水と地の、空と血の、此方と彼方の境は消失することはないのだった。
「こうなることも、知っていたのか?」
「ふふ……思っても見なかった。いつ吸ってくれるのかと思っていたのよ」
「あんなに悦んでいたのに」
「そうよ。だから濡れたのよ」
手の中に掴んだ胸は、確かな重みと温かさがあり、しっとりと湿り気を帯びていたが
もう血を流すことはなかった。
「君には心から礼を言う」
細く伸びた首筋に唇をつけて痕が残るほど吸った。牙をたてずに。
……ぁ。
肩にかかる長い爪の先が肉に食い込んで震える。
「いいことを教えてあげる。貴方は望みを手にすることができるわ」
「望み?」
「この世界が滅びる時が来る。貴方が帝王として君臨している間に」
「この私が敗北する機会がまだあるということか……? それは楽しみだ。一体何に?」
女は謎めいた微笑を浮かべて吸血鬼を見つめ、答えずに首筋に残る痕を撫でていた。
「構わん。どうせ一度滅びた運命だ」
拗ねた子を諭すように、襟元を整えてやりながら、
「投げやりになることはないわ。そして甦るのが貴方の定め。幾度も繰り返している……。
貴方と、次に会うときはこうはいかないでしょう」
「君にはまた会えるのか?」
「いつの夜か、いつの世にか、会うこともあるでしょう。
――おやすみなさい」
唇が瞼を閉じさせ、束の間の眠りを与えた。
目覚めたとき女の姿は既になく、デミトリが彼の地を去る時刻にも冥府の王は姿を現さなかった。
*
夕べの暖かな光が、夜の訪れを告げる前に輝きを増す瞬間がある。
長い影が薄れることなくどこまでも伸びて、時に過酷な光から主を護っている。
二つの世界を手に入れてみると、その後の暮らしは意外なほど静かなものだった。
そうあるべき世界、と冥府の王は語った。
自分にとってのあるべき世界はこのようなものであったと思えるほどに。
休息が必要なのだと思っていた。
いつまでも沈まぬ陽が、じりじりと瞼を灼いて容易に眠ることができないと。
ふいに腕の中の身体が見えない衝撃を受けたようにびくりと身を反らせた。柔らかな体を強張らせて。
不死の者特有の血の気のない肌が赤く染まり、怯えた表情をしている。
昔から仕えるお気に入りの一人だった。
自分は何かを口走ってしまったのだったか……?
「ああ、……もう下がっても構わない」
「我がきみ…」
「気にするな。お前のせいではない。ゆっくり休むがいい」
「他のものを呼びますか?」
「いや、いい。一人にしておいてくれ」
女の手を握る。またな。
「……、お傍にいてはお邪魔でしょうか……あの」
いつになく頼りなげな表情を見せている。
「……ああ、いや」
「申し訳ありません。もう、お会いできないような気がしたのです」
「……おいで。悪い夢を見ることがあるのか?」
「いいえ。ここに参りましてからはありません。いつも、我がきみを感じていますから」
「幸せなことだな」
「しあわせです」
そう言って頬を赤らめる。
「そうか。よかったな。よかった……」
僕(しもべ)は余計なことを言わない。
ぼんやりと、その豊かな髪を撫でた。闇の中に淡い香りが揺らめきながら立ち昇る。
冷たい肌が心地よい。不安など何もない。
こうして。いつまでも。
自分の元で幸せだという。
言葉の通り、その肌に触れているだけで内なる安らぎが感じとれるようだった。
鼻腔からふっと落ち着いた息を吐いて弛緩していく体が、徐々に重さを増してもたれかかる。
何かから与えられて幸福なのか。望んで得られることが幸福なのか。
恒久の静けさ――熱く激しい焔の中で燃え尽きてしまいそうな交歓とは違う。
限界まで駆り立てられた焦げつく絶頂感とは違う。
幸福を与えてやれることもまた、幸せなことだ。
改めて考えてみることはなかったが、意外にも自分は満ち足りていた。
こうしてゆるやかに、またひとつの滅びに熟していく時に……。
寄せた頬が濡れている。
黙ってその涙をぬぐってやると僕が呟いた。
「嬉しいのです。お心が、感じられました。この時を愛おしんでくださるお気持が」
「ふふ、そうか」
耳朶をゆるく咬み、望みを口にする。
彼女はあるじを不思議そうに眺めた。そういう"お戯れ"だろうか。定められた答えがあっただろうか?
思いあたることがなかったので、僕はまっすぐな視線で見上げ、ただいつものように
あるじを慕う心を込め素直な想いを精一杯に述べた。
「我がきみ。わたくしの全てはあなたのものです。お気の済むように、可愛がってくださいませ」
早急なおとないにも、充分な潤いに満ちた密接な歓待が応えて、奥の間へと迎え入れた。
熱のこもり始めた肌を、腰骨から尻たぶまでゆるやかに撫でながら、内なる繊細な起伏を味わう。
張り詰めた肉を掴んで引き寄せるとくぐもった呻き声が長くなる。
水面に映る灯のような、二つの瞳が深い壷底の振動を伝えて揺らぎ、滲んでいる。
「欲しいか? ……欲しいな」
あぁ…、と乱れた吐息の間から懇願の色を聞き分けて、その愛らしい唇に指先を当てる。
「褒美をやろう」
ちろりと指を舐め、手のひらを這って、辿りついた手首の内側に、僕はとり憑かれたように激しく口付けた。
ふと、手を振り払ってその体を再び強く抱きよせる。
細い顎に似つかわしくない太く鋭い牙が、首筋の厚い肉の層をものともせず、深く食い入った。
血の欲望に濡れた魔の双眸が輝きを増して、あるじの霊血の恩恵に浴すべく貪欲に啜りあげていく。
ああ……そうだ、もっと激しく、吸え……。
もっと。この血の全てを。
*
お前を倒せるのは、私しかいなかった。私を倒せるのはお前しかいない。だからはやく来い。
はやく、私を眠らせに来い。私を闇に沈めて
狂おしい夜の果てまで連れ去るがいい。いつもしていたように――
唇が離れ、咳き込んで、僕の身がぐったりと力を失い仰け反った。牙から滴り落ちる血が、白い肌を彩っている。
濡れた唇を舐め取ってやり身を起こすと、栓を抜かれた形のままに開いた花口がとろりとした蜜汁を吐き出す。
名残を惜しむように小さく呻き、確かな温度を持った体液が、敏感な箇所を伝い流れ落ちる感触に
力の抜けた体を微かに震わせている。その有様を眺めて初めて、吐精していたことを知る。
今度攫った生娘には血を望まず、子を産ませてみようか。
吸血鬼の血を受けた人の子には、その血を絶つ力があるという。
限りある命のものに、本当にこの身を眠らせる力が宿るだろうか?
僕の名をその耳元で、エルジェベト、と今は懐かしい故郷のアクセントで囁いてみる。
ゆるやかに治まった呼吸に微かに鼻を鳴らすような音色が混じる。
このように手の内にあるものを、なぜ呼んでみるのか。
その響きを発する動き自体に感応するものがあるからか?
掴んだものが、確かにそれだと、確かめたくて?
呼びかけに響き応える存在の正体を、なお検めたくて?
もう二度と呼ぶことの出来ない名前がある。
その語感にはよく親しんだはずなのに発音することができない。封印された呪文のごときあの……。
応えを待っていると、その毒に捉われてしまうから。
思い出してしまうから。官能が鳴り響く、時のない場所へ、遠い昔に
既にその応えごと吸い込まれてしまった。
万物と通い合うときに、唯一の血、無二の願いを叶えてやった。
……だから口にはださない。
だが、ひとたび精神を傾ければ、今もこの身に流れる血がさざめいて、
その名を求めている気がする。
どれほどの時を経ても薄れたりはしないのだ。
もう、それを思い知るために無限の時を渡る必要はない。
ある晩に、ふと感じる。豊かな夜が満ちてくるのを。
あの夢が訪れて、新たな光と共に己が実らせたものを知らせる時が来る。
そうしたら、あわてて目を開け目覚めようとしたりはせずに
抱きしめるのだ。己の運命を、再び掴んだ幸福を、
最期まで放すことのないように。
それが、熱い舌を絡ませて、忘れたはずの音を告げ、響きを教える。
陽の光が、瞼の裏を赤く灼いて、感覚を失うその前に抱く腕に力を込める。
このように手の内にあるものを、どうして検めてみるのか。
美の条理、無限の時、充足の密度――すべて確たるもの、疑いのない十全さ。
耳鳴りのするほどに、まばゆい日々。
もうそんな話はいい。
それは、同時に存在できなかったのだ。この光の下では。
消し去ることの出来ない
暗い破滅の夢、決して忘れぬ闇の夢がこの血潮に潜んでいる。
私の鼓動のうちに今は安らいでいればいい。
昼と夜の境目がないように、光と闇の境目もない。
眼を見開いていても閉じているのと同じほど、漆黒の暗闇が
この輝かしい無限の果てに続いている。
落日のない栄光に
陽が沈むことのない永遠に倦んだなら、目を閉じて
優しい闇の夢に、果てなく堕ちればいい。
あの灼熱の暗黒が再び訪れるのなら、
私が眠りにつく時刻を告げに来い。私を永遠に眠らせに来い。
お前の父がしたように。
お前の血が脈打つ、我が心が朽ちるまでに。
2006.12