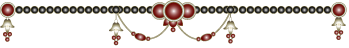忘れられない夜にして。
――甘い囁きを交し合ったのは、そう遠くない日々だ。
深さを増す闇に、幾重にも連なる追憶の紗幕。鮮烈な数多の感触。
穏やかな波に揺られて、とろんとした目で見つめあい、涎を垂らして怠惰に溺れる。
「もう、気持ちよくて、おかしくなっちゃったみたい。ずうっとこうしていたいわ。ねえ」
「ん」
「あなたと」
珍しくも甘ったれたサキュバスの独白に、ハッ、と呆れたような笑みが浮かぶ。
「なぁによ」
「とっくにおかしくなってるからな、私は」
くっついた腰に脚を絡める。
「あ…ふふ、そうだった?」
力を加えて押し返す。
う…ん。
ゆるんだ唸り声が漏れる。その首筋を撫でながら、呟く。
「ね、本当に、おかしくなっちゃったのよ」
「あぁ……」
「聞いてる?」
「ん…ん。……聞いてる」
頼りない声だ。瞳の焦点があっていない。
「じゃあつづき」
「今?」
聞いていた証拠にすぐに反応が返ってきた。それで彼女は寛容になる。
「ふふふ……あとでいいわよ。あのね、あなたにお願いがあるんだけど」
「つづきはお願いのうちに入ってないのか……。何だ? 聞いてやる、なんでも。聞くだけは」
「私より先にいかないで」
「約束するのはなかなか難しいな……。毎度となると」
「ああ、あなたは何回でも甦るものね」
「そういう意味じゃなかった?」
「……どういう意味か知らないけど、まあそういう意味よ。たぶんね。フフ。この間夢を見たの」
「君も夢見る乙女の一人だとはな」
「時にはね……。ふふ…あなたの夢。素敵だったわ」
「ふ、ますます疑わしい」
「でもね、期待しているようなものじゃないわよ……。
あなたが、私を眠らせてくれるの。傍にいて。ただそれだけ」
……それだけなのよ?
握った手を撫でて、蕩けていた吸血鬼の眼差しが一瞬鋭い光を放つ。
「本当に」
「……わかっている」
お前を眠りにつかせてやる。
もう醒めることのない永遠の夢の中で終わりのない歓びを与えてやろう。
ふふふ、素敵。そうして。あなたならできるわ。あなただけができる。
瞳の赤い光が揺れている。
「約束してくれるの」
「誓いのキスが要るのか?」
見つめあったままで、鼻先が触れあう。戯れに押し合いながら軽く交わすつもりでいたのに
一度触れたら離れることができなくなった。上下の唇を互い違いにかみ合わせ、動きもせず瞬きもせず
鼓動だけを感じている。どちらかが動いたら時間ごと消え去ってしまうかのように。
ん…ぅん。
微かに鼻の奥を鳴らして唇を離し、悪戯っぽく微笑んでみせる。
「つづきしたくなった?」
「まったく、どうしようもないな、君は」
「んん、だって、どうしようもないくらい欲しいのよ…、あなたが」
「どうしようもなく、可愛い……」
ちゅっと音を立てて触れられた部分が熱を持って痺れる。
あッ、ああ…。ほら、わかるでしょう。こんなに……
「これにも誓わせようかしら」
目覚めかけたところをぐいと握られて、彼は怯まずに笑った。
「どこにしてほしいのか教えなさい」
そう言いながら、もう素早く指先が背後から腰を滑り丸みをつるりと撫でて狭間に差し掛かる。
「ん……。っふふ。お願いきいてくれるから好きよ。大好き。ぁん、すごい、びんびんしてる。大好き」
「君の言いたいことは、よく、わかってる」
「あはは。そう。あなたのが好き。素直だもの。あなたは別よ。意地悪だし」
「私は、君の肉体など知らなくとも、変わらず君を讃えただろうに」
「どうかしら。じゃあ、私が、アーンスランドじゃなかったら? そんなに執着しなかったんじゃないかしら……」
「その質問は、私にしているのか、それとも自分自身に?
ふふ、君はもう永遠の喜びと幸せを得て、満ち足りた時を過ごしているだろうよ」
「吸血鬼のお城で?」
「全てを手にした者の元で」
「そうね、そうかもね……。でも、だったら今とあんまり変わらないわ」
「君はまだ私の全てを知ったわけではない……私がどれほどの愛情を注いでやれるか、
知らないだろ。モリガン」
一瞬、息をつめた表情を確かめて、腰の下の窪みをそっと撫でる。
「そうかもね……、でも、もうこのままでもいいわ」
「このまま?」
「そう。何もしないの」
「いつも先に協定を破るのは君だ…」
「そう?」
「そうだ」
なじるように耳孔に息を吹きかける。
「いつでもそうだ…」
背筋がぞくぞくと、それと分かるほどに震えている。
っあ……。
滑らかな肌を辿って一息に快楽の源にのめり込む。指先を浸し、馴染んだ深みを開く。
指の腹で、細かな襞目を広げるように探りながら、その心に触れていたいと願う。
熟した果肉が崩されてあたり構わず芳香を零す。震えとは異なる揺れに腰が浮き立つ。
「気が変わったのか?」
「もう…! あっん。やっぱりして。ん、キス…して」
「……どこに欲しいんだ?」
「……あなたが、気に入っているところにしてちょうだい。私の」
頬を撫でて、見上げた瞳に唇を近づける。
睫毛を掠めて、さっと閉じられた瞼に口づける。睫毛の根元にそっと舌先で触れる。
柔らかな繊毛が寝た粘膜の際、薄く繊細な亀裂の縁が震える。
「目を開けろ」
おずおずと開かれた目が、わずかに覗く舌先を間近に捉えて大きく見開かれ、怯えた表情になる。
ッ、ッぁ……。
最も感じやすい箇所を犯されて、大粒の涙をいくつも零しながら爪が食い込むほどに抱きつく。
「んぅ、沁みる……」
舌が離れても止まらぬ涙に吸い込まれそうな緑の瞳を潤ませて、すねたように視線を逸らせたままでいる。
構わず、髪を一束捧げ持ってその先に接吻した。
目が合うと、細い髪の一筋ごとが恥らって身を捩らせたように手の内からこぼれ落ちる。
それから、最も親しい薄桃色の唇に――。
薄く柔らかく温かいそれらが、どれほど優しく包み込み、いかに激しく煽り立てるか
すでに何度も味わった。知り尽くしたはずなのに触れるたびに違う味がする。
切なげな吐息をつきながら、誘うように反らせた白い首筋には
鼻先だけを近づけて立ち昇る血の香気を愉しむ。
「フフあんまり調子に乗るなよ……怖くないのか」
「怖くないわ。いいわよ、咬んで」
「間違ったらどうする? ふふ、君も知っている通り、案外堪え性がないぞ。私は」
「いいの。……ァあッ」
柔らかい乳房を荒々しく捻りあげられ、さっと乳首に喰いつかれて声が上ずる。
「痛、いったぃ、っぁ、あふれちゃう……、あ、」
「んん、溢れちゃうと困るんだな君は……。
もうさっきから溢れて垂れてだらだらで、随分困ったことになっている」
「わかってるなら、なんとかしてよ、ね……」
「ここにも欲しいな……? ここは、後でたっぷりキスしてやる。君の…大好きなほうで。
君が自分では触れられない奥に。何百回も」
重なり合う花弁の溝を舌の先で抉るように通過しただけで
その感触の、熱く甘いとろみにたちまち精神ごと吸い込まれ溺れかける。
「あっ…、はっ、いやッ、いま、今してよ、待てない…」
「きれいなおみ脚たちには敬意を表さなくていいのか?」
言いながら、もう自分自身が持ちこたえられるかが疑わしい。
花蜜の流れの跡を追って柔らかい内腿の皮膚を痕が残るほどきつく吸う。
「ッ…っん。ぁ……。もう、されちゃいたいの、めちゃくちゃに。きて……きてッ、」
「もういい。わかったから……」
蕩けて口を開けひくつく火芯に突きつけたところで、堪えかねて背筋が震える。
熱く膨れた先同士で幾度も濡れた接吻が性急に交わされる。心ならずも離れていた時を埋めようとするかのように。
「…はぁ……、いい…。あぁん」
ずぶりと先端を埋め込むと、たちまち波間に呑まれるように最深部まで誘われた。
「あああッ。ん。んんっ。は…いってきてる。ァ…、あなたが。あぁ…、ぁあ、」
熱に浮かされたように口走り、うっとりとした表情を浮かべる。
「これでご満悦か?」
瞳を見据えて問いただす。
「意地悪なのが好きだと、言ってもいいぞ」
「……大好きよ……あなたの、そういうところも。大好き。ねえ、もっと、意地悪して。もっと酷いこと…して」
首筋を引き寄せ、髪を握り締めながら、高揚して潤む瞳と掠れた声が懇願する。
「酷いことか。こうやって、このまま何もしない、とか。……すると、君の中が、たまらずにひくひく悶える」
「ぁん――。ふふ。いいわ。ああ…、待ち遠しくなっちゃう……」
互いの最も甘口の弱みを把握して、絡みあう視線が擦れ火花を散らす。
競うのは、自分が灼き切れ溶け崩れる速さだ――そうなったのはいつの頃からなのか、かつては確かに逆であったのに。
「あぁん、いじわる。すきなの…もっといじめ…て」
「……、ハ…だめだ。私が我慢できない」
「ふふ…あきれた人。ひどすぎだわ」
「だから、言ったじゃないか、堪え性がないって。ああ、……このまま、もう」
尻を掴んで広げ、がっちりと奥まで食い込ませる。突き当たってなお、形が歪むほどに深くのめり込む。
極みの軸を捉え留めおこうとするように豊かな蜜波が断続的に水圧を高め噴きこぼれる。
同時に弛んでいた唇から吐きだされる短い息が、なおも熱っぽく昂ぶりを告げる。
「ッん、うッ、あ、―ぁ、だめ、もう…」
「待て……、私をおいて行くな」
「あっ、……ぁ、そんな声で囁かれたら、…それで逝っちゃう」
その名を呼ぶ。唯一つ念ずるに値する呪文のごとく。
耳朶をきつく咬み、澄み渡っていながら深く底知れぬその淵に身を投じる。
一打ち一打ちが、自ら棺の蓋を釘打ち封じるようなものだった。
冷たい眠りの底で甦りを待つあの永い時。
そこへ向かう秒読みが始まっていようとも、構わずに。
一方が滑り落ちかかるのを引きあい、絶妙な均衡を保ちながら
絶頂の長い尾根に留まり続けて、どれほど経ったのか。気がつけば
炸裂する閃光のような鋭い快感ではなく、見えない光線に長く曝されているような
温く痺れた酔いの裡にもつれあったまま沈んでいる。
乳首を優しく噛みしだくと、顔をしかめて熱い瞼がぴくぴくと震える。
「う、ぅ、ん」
微かに身を捩る動きに境界の感覚が甦る。
突き当たった先が吸い込まれ容易に引くことができないような磁力が渦巻いている。
退くたびに強く引き戻される。
「……、ぁ…、あ……デミトリぃ、ね、抜いて。もう。ゆるして。これ以上したら……」
「また、そんなこと言ってるのか?」
「ちがうの……ほんと、だめ。で…きちゃう。……」
白い頬を上気させ、息を切らせながら恥らって目を伏せた顔を眺める。
「なに?」
「今、したら、できちゃうわ。あなたの……」
快楽が極点に達する時、本能が精を選んで種を残そうとするのか、最中に淫魔が排卵することがあるという。
血を分け合って種族を増やす吸血鬼同士の交感では、子を孕むということがない。
人間との間に子を成すことも可能だろうが、あえてそうしたことはなかった。
望めば無限の時を得、授けることができる者にとっては、命を引き継ぐことの意味が自ずから異なる。
淫魔に受胎させる。
思ってもみなかったことだが、たちまちその誘惑が脳裏を占めた。
「孕ませてやろうか。このまま」
「……でも……。本当に、できちゃうの」
「わかっている。私の精を……我が不滅の命を授けてやる」
「何を言ってるかわかってるの?」
サキュバスの子に、雄種はあっても父親は存在しないのだった。
受胎すると他の精を欲することはなくなる。
幸か不幸か、究極の快楽を与えて選ばれし者は死に至るまで吸い尽くされるよりほかはない。
吸血鬼の永遠の命をもってしても、その定めからは逃れられないだろう。
至上の夢を得る代償とすれば……安いのか、高いのか。
「わかっている。そして、君は私だけのものになるのだ。私の元に縛り付けて二度と放さない」
「……わかってない。無理よ、そんなこと」
「無理かどうかは試してみるがいい。……私の全てを、与えてやるから」
その瞳から涙が溢れ出した。嬉し涙か悦びの涙か、哀しみの涙か、表情からは窺い知れなかった。
嬉し涙だと思うのは自惚れが過ぎる、数え切れないほどの男がそう言ったに違いない。全てを捧げると。
哀しみのためと思うのは、更に愚かだ。淫魔に慈悲などないのだ。
悦楽の涙か。さもありなん。愛撫には必ず応えるその身体。
だが、なぜこんな時にまで自分は皮肉な見方しかできないのか。こんなにも溶け合い、なお繋がったままで。
こんなにも、愛を交し合ってもう余すところなくお前をこの手に感じられるのに。
揺さぶると、その涙がとめどもなく湧き出して頬を濡らしていく。
口付けで塞いだ唇が苦しげに蠢く。何かを訴えようとするように。それを知っていて、わざと解放しなかった。
「いやか?」
「だって、だって……約束したのに……ッあ、いィ……ァ、ちょっと…」
行き着いた先の、押し上げられて、極まる頂点のその先にまで熱が充ちていく。
丸く開ききった花弁に優しく珠の当たる感触が徐々に間隔をつめる。
「私の子を孕むのは、いやか?」
「っん……」
肩に巻きつく腕が力を増し、一層強く押し付けられた。
「ぁぁ……だって、おかしくなっちゃう……。きっとおかしくなっちゃうわ。もう止まらなくなって、
あなたじゃないと満足できなくて、全部、欲しくて、欲しくて、……離れられなくなってしまうわ。
……あなたが、尽き果ててしまうまで」
あだに揺らめく声には既に困惑よりも期待の色が勝っているようにも思えた。
「だったら、今と大して変わらないじゃないか……。
私を蕩尽するのはそう単純ではないぞ。我が思いは簡単には尽きたりしない」
ゆっくりと引き延ばしながら抑えていたものが、身震いをする。
絡みついた襞の重なりがその意志を支えるように表裏を返しながら更に厚さを増した。
惹き合う強烈な親和力に感応して心まで震えがくる。
「あぁ……、本当に……君が、私を掴んで放さない」
瞳の表面に激しい情動のうねりと高まりを映したさざなみがよぎる。
「お願いだから、このまま」
「もう君のお願いを聞いてやれる余裕はなさそうだ……」
「待って、うごかないで。感じるでしょう」
「……ああ。ああ、…」
「このまま、ちょうだい。あなたを。全部。……きて。欲しいの。いっぱいに、して。あなたで」
「してやる……してやる。……我が胤を宿すがいい。……モリガン、お前の全ては、この私のものだ」
深く誘われた先の愛しくたおやかな形を検めようとしたときには、もう全身が包み込まれていた。
堅く抱き合ってほとんど身動きもとれず、長い息をついて、満ち干きを感じあう。
接したままの中心に、彼方の回帰線から押し寄せ溢れかえる悦びを。
至福の瞬間瞬間が数え切れないほど立ち昇り、巡っていく。
この上もないほどの、柔らかく繰り返される無限の接吻に
互いを呼ぶほかには意味のある言葉を発することができなくなり、絶え間なく快楽の呻きが漏れた。
「う……、ぁあっ、モリガン、モリガンッ」
穏やかな幸福感と息を継ぐ間もないほどの激しい絶頂が、連続して肉体を振り切る。
生命の水を注ぎ込まれた器が何度もびくびくと慄く。魔物の牙にかかった贄のように。
「ん……んっ…! あなたの、熱いわ…。いい…ぃ…。溶け、ちゃう」
瞬間の焔が奔るような眩しい歓喜に呑み込まれて、そのまま身を委ね
極みに到達してからも、際限のない情熱が衰えることなく静かに沸騰し続けている。
強く結びつき溶け合った部分から魂と押し合った混沌の焔の泡沫が流れ落ちていく。
意識の果てが淡く霞み発光するのを感じる。
何度目か分からなくなっても噴き上げるものが止まらない――
どこまでも滑らかで熱く、迸る血の薫り立つような胸に顔をうずめ、激しい鼓動を聞きながら
気がつけば己の血までも吐き出して、想いのすべてを注ぎ尽くすまでに。
――いつも君を求めていた。久しく、夜も。昼も。知っていただろう?
モリガン……。欲しかった。君こそが我が望み、我が願いの全てだった。
こうしている今でもまだ君が欲しい。
君に全てを与えてやりたい。私の、命も。
支配したいからではない。
もう、そうして何かに勝ちたいわけではない。
ただ片時も離れていたくないだけだ。ただ傍にいてくれたら。
本当はずっと以前からそう願っていたのに、わかっていたはずなのに。
何が躊躇させていたのか。嘲笑われるのが、悔しくて? 疎まれるのが恐ろしくて?
それを認めてしまったら、最後のような、敗北し、誇りまで失われ、
無にも等しく吹けば舞い散る塵のように自分が跡形もなく消え果てる気がした。
だがそのことを恐れなくてもよかった。
何かを捨てなければ得られないと、だから譲れないと、どうして思っていたのだろう。
こんなに容易いことのために。
「君に今まで言わなかったことがある……」
そうして、その耳に注ぎ込む。
二度と解けることのない冷たく堅い永遠の血の絆の代わりに、
移ろいやすく乱れた吐息に今にもかき消えそうな言葉を。
「……知ってたわ、そんなこと。最初からわかってた。でも……嬉しい。
嬉しいの……あなたが、そう言ってくれて、幸せなの。
ああ、温かい、感じるわ……。あなたの血が、命が、私を内から抱きしめているよう……」
モリガン、私の元に来い。
終わりのない歓びを与えてやる。
こうやって。いつまでも。
抱いていてやるから。
行くな。このまま留まり、二度と、私の元から去るな。
お前が幻でも、もう、構わないから。
*
長い長い絶対的歓喜の時を経て、持てるもののすべてを注ぎ込むと
熱い肌が、沸々と蕩けた血の芳しい霊酒となって
口内に流れ込み、舌を灼き、飲み込むことも敵わないほどに横溢する。
知ってしまった。その味を……。
身震いがする。不気味な寒さが襲う。
やがて訪れる静寂の前の、囁きだけがいつまでも残っている。
愛してるわ、デミトリ。
私の忠実な僕、
私の永遠の虜。
――この感覚は知っている。
お前が夜毎見せた甘い幻の終幕だ。幾夜も幾夜も。繰り返し味わった。
全てを捧げ絞りつくされたあと、あの柔らかな夜は訪れず……、
そしてお前は冷たく凍りついた石のままなのだ。
今もなお。
いつか目を覚ました時に、お前がいるような気がしている。
白い寝台の上にその熱い体が横たわり、怠惰に蕩けて香り高く息づいている。
この腰の上にかかる甘い重さが闇に弾み、脳まで浸して追い詰める。
その吐息に耳を灼かれ、緑の湖に溺れる。
もうゆるせ。
耐えられない。
全てを捧げるから、捧げたのだから。もう私を眠らせて欲しい。何より愛しい私の悪夢。
そうしてその温もりの中に、いつまでも溺れていたい。克服したくない暗闇の夢。
石像を抱いて感じる不可侵の冷たさ。
自らの与える永遠とはこのように冷たく凝固した無数の瞬間の総体であったのか。
つかみどころなく流れていくことはなく、飛び去ることもない。
甘く蕩け形を変えて柔らかく腕の中に崩れてくることもない。
触れるといつも指が冷たいと言っていた。
その磁器のような肌は熱を帯び、上気していて、優しく彼を滾らせ一層の高揚へと導いた。
硬くすべらかなその胸に、耳をあててみても熱い血が巡っていたことがあるとは思えない。
あれほどに、溢れる思いを注ぎ込んだのに。
今この身に流れる血潮を全て流し込み、精も涙も枯れ果てるまで捧げたなら、
あるいは、熱い肌を輝く瞳を再び感じることができるのだろうか。
まだまだ足りないとでも?
だが、既に
捧げたのだ。この身と魂の限りを。滅びても構わぬと。
それが、誤りだということか? この力が。お前を得ることが。
何よりも、お前を求めたことが――。
そのはずはない。
あの瞬間を得た。溶け合い、全てを感じたあの無限に思える間。
永遠も一瞬も、時に属さないところでわかちあえる。
そこに到達したのなら、共に昇華されたのなら、
残されたこの像をなんと呼べば良い?
過ぎ去った願いの残骸に過ぎないものを。
ならば、このわが身をなんと呼ぶ?
人の目に映る魂を無くして久しい亡骸を。
お前がもう息づいていないように、この私の血があれほどに滾る時はない。
私が与えた誓いの通りお前は眠りについた。私を残して。
そうして初めて、お前の願いの意味を理解したのだ。
お前は私を信じてはいなかったということか?
いつか、私が去ると思っていたのか。我が思いも力も尽き果てると。
だからこうして私に足枷をしているのか。追憶と堕落の沼底に引き込む重石のごとく。
冷たい肌に、唇で触れる。あの日のように。
閉じた瞼の下に、水滴が零れている。触れると熱をもって温かく、その輪郭が霞み、揺らぐ。
それは、自分の視界が涙に滲んだだけなのだとわかっている。
意固地なまでのこの冷たさ。
終わりのない歓びには始まりもなく、この胸の思いと共に永遠に凝結した。
だがそれこそが、我が支配の絶対を示す、磐石の礎なのだ。
ならばもう、心を震わせてお前を夢見ることはしない。
こうして私は、お前と世界を手に入れた。そのように見果てぬ野望は終わりを迎えた。
そのように、愛しき夢に別れを告げた。