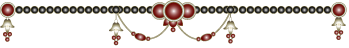あなたに素敵な贈り物があるわ、と闇夜に淫魔が誘いかける。
甘い声に惑わされず、ただ一度でも抵抗できる者は果たしてどれだけいるのか。
狂おしき闇の調べに、耳を塞ぐだけの勇気があるものは。
「サキュバスのキスにはいささか食傷気味なんだがね」
「あら…、随分な言い草じゃない。多分、あなたがもっと好きなもの。
純潔の乙女の血と言ったら、いかが。目の色が変わったかしら…? ふふふ」
無垢の花嫁なのよ。まだ幼くて清い体のまま寡婦になってしまった――。
「男はどうしたんだ」
「花婿のほうは……戴いちゃったのよ、この私が」
――ふと見た窓辺にこの世のものとも思われない美しい淫魔が佇んでおり、
たちまち取り付かれた男は新床に花嫁を残して
その場で魂まで奪われ吸い尽くされてしまった――ということなのだった。
悪びれた様子もなく語る、淫蕩な隈が刻まれた白い頬をデミトリはまじまじと見つめなおした。
「しかし、君も随分罪なことをしているな。恨みを残して死んだ者が吸血鬼になったりする。
君につきまとったりするかもしれんぞ。気をつけたほうがいい」
「あら、そうなの?」
緑の目が瞬いて、そういう吸血鬼の顔を覗き込む。
「心当たりでもあるのかしら、フフッ。でも大丈夫よ。みんな、思い残すことはない幸せな表情をしているわ。
それはそうよねえ……最高の夢の中で永久の眠りにつくんですもの」
「わざわざ出向いてか、君もご苦労なことだ……」
「ね、狩りは嫌いじゃないでしょう? 行きましょうよ。早くしないと飛び降りちゃうかもしれないわ。
すごく可愛い娘よ。今なら白とブルーのおリボンもつけてあるのよ。
陰気な黒服に変わる前にぜひあなたに召し上がってもらいたいわ」
軽率に口車に乗せられるのは抵抗があったが、瞳を輝かせた淫魔を失望させるのも気が引ける。
何より差し出された贈り物とやらに少々興味をひかれるのも事実だった。
そもそも初夜とは血塗られたものなのだ。
*
犠牲者はまだ若い男だった。淫魔の弁明通り、呆けたような笑みを浮かべて
弛んだ口元からむき出しの下半身まで、得体の知れない夜露に濡れて横たわっている。
無様な姿――それでもお前は、さぞや幸せなのだろうな、と皮肉に眺める。
自分の妻も、人生も投げ出して。ほんの一時の気の迷いから全てを失うことになろうとも。
最も、それがお前の運命だったということか。
定めとはえてしてそのようなものだ、もがき逃れようとしても流れには逆らえない。
気を高め機が熟せばそれが己についてくるものだ……。
通り過ぎようとして、その場に吸い寄せられるように再び視線を戻す。
「とどめはさしていないから…ああ、まだ温かいわ」
淫魔の指に触れられると、哀れな生贄はそこだけは立派に主張した。
見せ付けるように、するりと白い肌を晒すと、男の股間に顔を近づけ
不気味に赤い舌を覗かせてぴちゃぴちゃと無邪気な音を立てる。
初めのうちこそ、乱れた髪の間から視線を投げかけて吸血鬼の様子を覗っていたが
やがて、その存在も忘れたように熱心に頭を上下させていく。
顔を上げ、口を放すと息を喘がせた。勢いなくどろりと滲み出したものが、唇の端から零れる。
「んん、なかなかいいお味…さすがに生きがいいわね」
握った手を放さずに、視線をこちらに向けて微笑むと、
背後に手をついて猥らに脚を広げ、指の先で蜜滴を光らせた花唇を無造作に左右に開く。
その隙間に挟み込むように、だが呑みこまず側面にあてて擦りあげ、恍惚の表情を浮かべる。
「はぁ…、ぁん…ん」
腰を浮かせ、先端にまで達すると、めくれ上がった花弁をひっかけて小刻みに揺さぶる。
頬に血の色を浮き立たせ、敏感な一点で昇りつめようとする。
滲み出た樹液と溢れる蜜とで、上向きの杭が滑って不規則な動きになる。
あん、
尖った乳首を摘んで捻っていた手で焦れたように掴みなおすと、一気に腰を沈める。
好き勝手に貪られている生贄への、哀れみなのか羨みか名付けようもないまま
居たたまれない思いに捉われて、デミトリはその光景から目を背けた。
そんな様子を視界の端に捉えて、からかうような声が更に高くなる。
「あ、ァあ…んん、また、おおきくなってるみたい……もっと、奥まできて欲しいわ…。
ぁぁ…、もうイきたいの。でも、このままじゃイけない……。ね、ここ…触って?」
乳房を寄せて悩ましげに身をくねらせる。
「なんなら、あなたも来てくれる……? こっち…」
目が合うと、デミトリの忍耐がそろそろ限度を迎えているのを察知したのか、さっと矛を納めて微笑む。
「ふふ、あなたのおやつは隣で待ってるわ、吸血鬼さん。さ、行って、どうぞ遠慮なく召し上がれ」
不本意なことながら、その言葉に解放されて彼はようやくその場を離れることが出来た。
処女の血を愛する吸血鬼にしてみれば、肉体そのものの味わいはあくまで副次的なものだ。
特に早摘みの純粋な新鮮さが魅力であるような娘においては、むやみに体を弄ると、
犯される恐怖と苦痛で生まれる澱んだ苦味が生き血の旨味をことごとく損なってしまう。
ごく稀に、闇に共鳴する血が愛撫に蕩けて濃厚さを増す例もあるが、ほとんどの処女はそうならない。
一生に一度しか採れない血の希少価値に比して、肉そのものへの執着は自然と薄らいだ。
本当にこれと見込んだ珠玉ならば、まず純潔の血を存分に味わい、新たな命を与えて城に迎え、
時間をかけて熟成させることもできる。そこまでの素材はそう多くはない。
すでに躾の行き届いたお気に入りは一通り揃い、充実のセレクションといえるものだった。
無意識のうちにサキュバスの媚態に煽られてなのか。今は若い娘の肌をも嬲りたい衝動を感じる。
灯の消えた寝室に、茫然自失の態で娘はいた。
虚ろな眼差しで闇に浮かぶ魔物の姿を見つめる。最早目に映るものを実感として受け入れられない様子だ。
寝台に座って、娘の顎を掴んで仰向かせた。
触れられて、はっと脅えた娘の体が固くなる。恐怖に引きつった喉。
稀に見る可憐な娘だった。悲痛な表情が美しさを際立たせている。
吸血鬼の花嫁の一人として城に迎えられる資格も充分にあった。
小さな唇が震えながら祈りを捧げている。
「君のお相手は魔女に連れ去られてしまったようだな」
滑らかな肌の感触を手のひらに感じながら首筋から肩へと撫で下ろす。
純白の下着の胸元に手がかかると更に身が固くなった。
「おゆるしください…」
脱がせかけた手を止めて、ゆっくりと頬を撫でる。
長い睫毛が震えるのを眺めながら待ち、手のひらが涙を吸い取って
頬の温度と同じくらいになじんだ時、そっと軽く唇の端に口をつけた。
次にそこからたぐりよせるようにして柔らかい感触を味わう。
「あぁ…んむ」
小さな声があがった。新たな涙が頬に零れ落ち、唇を濡らす。
その液体を吸う。ふっと力の抜けた体を抱き寄せ、ある程度の力強さで締め付けながら
萎縮した舌を追いかけて絡めとる。
呼吸を荒げ、張りのある胸が苦しげに揺れた。
このまま無下に散らすのは惜しいと思った。新たな命を授け、新たな歓びを教え、花開かせることも出来るのに。
淫魔の気まぐれで、このような運命を辿らされる娘。
情け知らずの淫魔に大切なものを永久に奪われてしまった者――。
思いがけない娘への共感が生まれる。
抱きあげると、娘は抗わずに縋りついてきた。潤んだ瞳が見上げている。
唇を触れ合わせたまま、太股の間に探りを入れようとしたが、ぴたりと合わせた膝と白い腿が侵入を阻む。
胴をしっかりと抱えなおして優しく脇腹を撫でながら、薄い包装を解いて、突き出した尻の間に逆の手を滑り込ませる。
今度はさしたる抵抗もなく柔らかな膨らみを帯びた花実の部分に到達することが出来た。
中指の先で軽く突かれて、観念したように太股の力が弛んだ。
閉じた瞼の下から涙が溢れ出している。
レースの隙間をくぐり、じかに触れた箇所は熱い涙に潤っていた。とめどなく零れ落ちる滴が指を濡らす。
はかない花びらの縁をゆっくりと辿ると娘の嗚咽が切なく高まった。
想い人と結ばれずに生娘のまま死ぬと精霊になって冥府を彷徨い続けるともいう。
すぐに会えるだろう。ちゃんとあの世に送ってやる。そう心を決めた。
目を閉じているように告げ、力のない細い腕を首にかけさせてから、一気に貫いた。
固く、歓びを知らない蕾が綻ぶ。異物を押し返そうとするような内部の抵抗がきつく娘自身の縛めとなっている。
仰け反った白い喉が震える。娘の腕が肩に絡みつきしっかりとしがみつく。
声にならないまま、男の名を呼んでいるのがわかった。
その口を柔らかく塞ぐ。こみ上げる思いが感じられる。けなげな娘が哀れで愛おしくなった。
わななく果実のような唇を小刻みに吸い、慈しんでいると
やがてたどたどしく、小さな舌が応えようとする。
愛おしさのあまり、細い首筋に牙を立てた。
うぐッ、と娘の背骨が反り、腰が落ちる。
吸い上げると、固い内壁が弛み弾力を増した。細かな漣と温かい潮が腰の上まで押し寄せるのを感じる。
その血は濃密なものだった。長熟に耐え、深みを増すことの出来る芯の強さがあった。
本当にこのまま城に連れ帰っても良いと思えた。
だが、すでに決めたのだ。思いを遂げさせてやると。この血と交わすのはただ一度きりだ。
喉を滑り、流れていく鮮やかな余韻を堪能しながら、長い痙攣の間その体を撫でてやった。
すがりつく指の力が弱まり、娘の肉体は急速に色と温もりを失った。
淫魔が冷ややかな笑みを浮かべて座っている。
その存在を失念するほどに没頭していたとは。
「随分と優しくしてあげてたじゃない、可愛い獲物には。
飲みしか興味ないなんていって…出されたお料理はやっぱり残さず召し上がるのね」
「…君に何がわかる。ずっと眺めていたのか。淑女のすることとも思えんな」
「誰のおかげでおいしい思いができたのか、忘れないで欲しいわ」
「君のおふざけには付き合いきれない」
「あらもうあなたも共犯じゃないの。デミトリ。ねえ、信じる? 本当はあなたが欲しかった、って言ったら…」
禍々しい笑みだった。
「だったら最初からそう言えばいい。わざわざこんなことをする必要はなかった。
おイタはそのくらいにして城に帰りたまえ、と言うところだがな。この娘の血が、君に贖いを求めている……」
「っは、なにもそんな持って回った言い方する必要もないわ」
強気な口調を崩さない淫魔だったが、
本性を現した闇の姿の吸血鬼に長い鉤爪で髪を梳かれ、
破瓜の血に濡れてそそり立つものを認めると、微かに身を強張らせた。
「そう固くならなくてもいい……モリガン、ここに来い。優しくしてやるから。…今宵は格別に」
「ぅン…」
「さっきの勢いで、腰を振ってみせてくれないのか」
「ぁぁ、だって…、いつものあなたより……ァあ、こ…んな、…き…つくて」
「君にはきっと気に入ってもらえると思っていたよ……。普段ご婦人方には披露しない、この姿も」
これもな、と声を顰めて付け加える。
「…今、突き当たってる…君の、奥の、奥の、入り口まで。わかるな? ここだ…。ここを…
どんな風にしたら、一番早く君の悔恨の涙が味わえるかな。壊れるまで突いてほしいか?
それとも、狂えるほど焦らされたい?」
「あん…、やさしく、してくれるって…言ったじゃない」
「優しいだろう、私は。君と違って。それに大事なことは忘れてない」
尖った爪が、竜頭を摘む動作で凝った乳先をくいくいと巻き上げる。
「ィ、あッ…、ぁ。ン、…。ぁあ…」
「……いけなかったんだろ、さっきは、な?」
「ン…ッ」
背けた頬に赤みが差す。
「ふふ、答えなくてもいい。かわいそうに、こんなにして」
ぷくんと膨れた一粒がつつきあげる度に硬さを増して舌の上に返る。
滑らかな肌に埋め込み均すように扱く。乳肉の震えがやがて全身にまで広がっていく。
喉の奥に消え入った声の代わりに、きゅんと縮み上がった内襞がすがりつき求めている。
駄目押しに腰をしならせ、行き詰まった先端で圧すると瞬時に中が極まった。
ッァ……。
仰け反る体を言葉通り優しく捕らえると、蕩けたサキュバスがくたりと腕の中に落ちてきた。
濡れた瞳の内に妖しい輝きが増している。
普段の姿に戻ったデミトリは引き寄せられるようにその瞳を見つめた。
揺らめく光にちろちろと、滾る思いに包まれた過敏な情緒の尖端を舐められているようだ。
唇が虚ろに開く。見つめあったままで唇を合わせ、痺れるような唾液を飲み込む。
唇を離すと、熱を帯びた下腹に響く低い声が漏れる。
「んふ、ねえもっと。もっと。優しくなくていいからきてよ……。もっと、奥まで…あなたを感じさせて」
「んぐ…く…ぅッッ、ぁ…」
即座に腰骨に叩きつけるように打ち込まれて、蕩けていた体がたちまち弾力を取り戻した。
髪がふわりと広がり、抑えた呻き声が零れる。
その両脚が絡みつき更に腰を引き付けようとするのを、足首を掴んで引きはがす。
肩まで持ち上げねめつけてから、腰を落とす。泣かせてやる。お前を。
ぎりぎりと軋みそうなほどに圧し込み、追い上げているのに、ふてぶてしいまでの微笑みは口元から消えない気がした。
喉もとと同じ感触がする滑らかな膝裏の窪みを撫で、揺さぶりをかける。
「これでは? どうだ…」
「ぁぁ……、あなたが、びくびくって脈打ってるのまで、わかるわ……。あっっ、イイの…。
はァ…ん……、おく……熱くて、溶けちゃいそう」
腿の肉に弾ませるようにしてそのまま反復する動きに、艶めく声と豊かな襞目がいつになく従順につき従う。
「ん…っ、ッッ、い、かせて…。いい、そのまま、注ぎこんで、欲しいの、デミトリ、あなたが…」
足の指の先までが細かく震え悶えている。その一つ一つにちゅっと音を立てて接吻してやりながら囁く。
「君は時々、たまらなく可愛いことを言ってくれる…。だがな、まだゆるしてはやらん」
「あぁ。ぅぅん……ぃっちゃ…いっちゃう。……ぁ、ぁ、イぃ、く――。ん…んっ…」
どこか遠くの岸から流れてくるような、ビブラートのかかったその旋律を鼓膜と舳先とで聞きとどけてなお
身を攀じりわずかにかわそうとする最奥を頑強に制したまま、責め苛み続け――
「ぁ…ン…よすぎる……だめ…。っ、ゆるして、ゆるして…よ、もう――も…ぅ」
ついにはすすり泣きになり宙にかげろう響きを、吸血鬼はかぐわしく利いた。
血に優る毒の甘さに溺れ始めて、とどめきれず溢れだすものと共に
胸の奥深く秘めた思いまでが飛沫になって迸る。
モリガン……。
「…ン、ぁ……、は……、っ、っ…」
滾る熱さを深底に受けて、その度に小さく息を喘がせながら、最奥で呑みくだすようにこくっこくっと喉が動く。
その熱に溶けた眼差しが彼の名を呼んでいる。その柔らかな内奥が彼を抱きこんで息をつく。
致死量を超え解毒することの叶わぬこの酩酊。
ああ、……。
だが……、ゆるすものか。お前が、完全にこの手に堕ちるまでは。
*
「あなたのこの体は、ついに花開くことなく実ることもない純潔の血で出来ているのね。ふふ。
とってもセンチメンタルで素敵じゃない? あはは…」
「何がそんなにおかしいのか私には全く理解できないが」
笑い転げるサキュバスを横目に、吸血鬼は取り澄ました表情を変えない。
「こう考えたらどうだ。全ての処女の体に、本来私のものである血が流れている、と。
……それをもとに還すだけだ」
口をつけずともその味わいはすでに知っている。
全ては、この手のうちにあり、そして生娘でなかった女など存在しないのだ。
「うふふ、でも、世の中にはあなたが未だかつて味わったことのない、
ついには征服しえない血があるって…思うこともあるでしょう?」
挑発するつもりの問いかけを
デミトリは聞いていないふりをして黙って流した。
2006.6