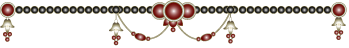自らの真の望みを知るものは少ない。
闇の香も葡萄酒もほどよく開いた時刻に、露台に降り立つ面影を認めて吸血鬼ははじめて知った。
その訪れを久しく自分は待っていたのだと。
照れ隠しのようにいかにも義務的に差し出された彼の手を黙殺して
身を起こした女は、黒い翼をたたみ夜風に煽られた長い髪を直しながら胸をそらせた。
夜の最も華麗な部分を凝縮したような、緑の光を放つ瞳は
太陽も月も必要とせず、陰が濃さを増すほどに、妖しく際立っている。
「あなたがそうして独りで月を眺めているのは、手の届かぬものに憧れて
報われない思いに焦がれているから……かしら?」
世の男という男は皆、自分に魅了されるものとはなから決めてかかっている。
精力を奪いとり、味わうことは、かの種族サキュバスの本能的狙いであり愉しみなのだ。
仇敵が後継者と目し、養女として手厚く保護した女。
進むべき覇道に立ちはだかる、避けては通れぬ最後の障壁。
この女への興味が、それ以上のものになりかけていることをデミトリは改めて知ったのだった。
もつれ絡み合う幾つもの夜を重ねて、危険なほどの執着に。
当人は、はかりごとなどとは無縁の様子を見せている。何物にも縛られず、刺激を追い求め、
興奮に包まれて――ただ屍の数が闇の輝かしさを磨き上げていく。
吸血鬼との微妙な緊張関係を、察知した上で面白がっているのか。
あるいは、堕ちていく者の列へと宿敵を屠りさるのが目的か……。
ひとまず、決して歓迎していないが仕方がない、という表情を向ける。
帰られても困るので、思いがけない偶然に驚いただけだ、という方向に修正を加える。
無視されてなお、わざとらしく差し伸べたままにしておいた腕をおもむろに組みなおして
鷹揚に口を開く。
「違うな……。ここまで来た距離を確認するのだ。あれは、私が人間であった時と同じ月だ。
変わらずに冴えて美しい。それが忠実に知らせてくれるのだ。これが夢や幻ではないと。
今宵は欠けることなく満ち足りて、我が人生のみならず、この世こそは私のためのものだと知らせてくれる。
その証拠に、……移り気な夢魔までが、我が窓辺に舞い降りてきたではないか?」
「運命の女神は気まぐれでも、意外と情が深くて、健気な信者にはお慈悲をくれることもあるらしいわよ。
私は違うけれど……ふふ。まあ、今夜のおめでたい魔王様のご機嫌を損ねないように
せいぜいおとなしくしていようかしら」
様々な思惑を潜めてギャラントリーに身を包み、夜の滑らかな肌触りを共に感じていると
演じている情人の役割が、いつのまにか乗り移ってしまったように錯覚しかねない。
そのような時は常に、冷たすぎるほどに冴えた血の本質が淫魔の秘技に警告を発してきた。
わかっている。まだ自分には余裕が充分すぎるほど残っている。
だから、血を吸わずとも、こうして相手の手の内におちたそぶりで、甘く容赦のない挑戦状を受け取った。
互いの弱みを暴き立て曝け出す。その攻防も、他では得られぬ歓びだ。
共にあらゆる美味や珍味を渉猟し愉楽の波を渡る航海に出て、
息を喘がせ抱きしめあって、極限の淵まで行ってみる。
二人とも、まだ帰ってくるつもりがあるから、それ以上は進まない。
いずれは全てを賭け雌雄を決する時が来る。
彩り豊かな時を味わえる敵を持ったのだから、幸運には感謝してじっくりとその過程も愉しむべきだ。
――そうして、いつまで続けられるだろうか?
帰ってこなかった者も、初めからそのつもりではなかっただろう。
気がついたときには、元きた道を戻る術がなくなっていたのだ。
*
「人間だった時のこと覚えてるの?」
「君は男を知らなかったときのことを覚えているか?」
「そんなことあったかしら……」
考えるふうでもなく、ゆっくりと瞼を上下させて、淫魔が見つめ返した。
「覚えてないわ。いちいち」
「思い出したくないのかな」
「いいえ、ただ……思い出せないの。
どうでもいいわ。覚えていたからって積み重ねるようなものじゃないもの」
「君は、哀れなのか、ある意味とても幸せなのかな。
ふふ、私は覚えているがね。人間であった時のことも、女を知らなかった時のことも」
「だからそんなに夢見がちなのね」
「私が最初に知った女性は、サキュバスだった。今思えば……あれは君だったのかもしれない」
「はっ、なにそれ。つまんないわよ。あなたらしくもない。もっと気が利いたこと言ったら?」
「覚えてないんだろう?」
「それは、私のほかにもサキュバスはたくさんいるわよ。私の生まれる前にも、たくさんいたでしょうね」
「そうだ、あれは君だった」
感慨にふけるような吸血鬼にどう応えればいいのか、モリガンは戸惑った。
「あっそう。……それで? 彼女と過ごした最高の夜を今でも思い出す?」
「どうかな。忘れがたい夜なのは確かだが」
「ふふ、まあ思い通りにいかなくても……初めてだったら仕方ないわね。私なら、逃さないわよ。
特にあなたみたいなたちの悪い男の子は嫌と言うほどおしおきして、二度と放してあげない。
……だから私じゃないわ」
「なんでそんなにむきになるんだ?」
その言い方が癇に障った。まさしく思い出に侵された腑抜けの口調だ。
「初体験がサキュバスだったなんて話はちっとも面白くないわ。しかも絶対私じゃないのに。
教えておいてあげる。初恋の君だとか死に別れたママに似ているなんて言われて嬉しい女なんかいないわよ」
「初恋? ふ、そういう話ではないのだが……、まあいい。この話はやめよう。
悪かった。今宵に相応しくないことは確かだ」
「そうよ。あなたが何匹のサキュバスをご存知か知らないけれど。
私の知っているヴァンパイアはあなただけなのよ。……少なくとも、今息があるのはね」
「ふふふ。その実、君は一人も知らないのだ。血を吸われた経験は、ないんだろう?」
「ないわよ。もちろん」
「それでは、本当の意味で吸血鬼を知っているとは言いがたいな。……いくら夜を共にしても」
闇の貴公子が含み笑いをする。
「ヴァージンを捧げる覚悟ができたら、いつでも知らせてくれ」
「別に、あなたと"本当の意味のお知り合い"になんてならなくてもいいけれど。もし仮に将来
献血の慈善事業に興味を覚えたとして、訪ねるべき一番お薦めのヴァンパイアはあなたなのかしら?」
「まあ、まず間違いなく、この世で君の取りうるベストの選択だろうな。保証する。紹介状も不要だぞ」
「本人が保証するって言っててもねぇ。私の人生でする最後の、最悪の決断には違いないわ」
「ふふ、その通りだ……。さすがによくわかってるじゃないか」
モリガンは上機嫌な様子の吸血鬼を横目で眺めた。
正面から闘っては勝ち目がないと踏み、敏くも彼女の性質を理解して別のアプローチを取ってきたか――。
純粋な興味が湧いていた。この世に自分の知りえない快楽がまだ、あるだろうか。
そんなものが存在するとして、それと引き換えに、この鼻持ちならない吸血鬼の僕として永遠に繋がれてしまうとしたら?
最高の快楽を味わうために、命を投げ出すことも厭わない幸せな愚か者は後を絶たない。
いっそ死んでしまうのなら、この世に飽き果てた先に、目指すものがあるのは悪くない。
燃え尽きてしまうことは何も怖くない。
だが、その後に延々と続く時間はどうだろう。
果てもなく、終わりのない時。考えただけで気が遠くなる。
全てを委ね、絶対服従の歓びに満たされれば、時の重みなどつゆほども感じずにいられるのだろうか。
どんな倦怠も追いつかぬほどの幸福の絶頂に、ぽかんと浮かび上がったままで。
あるいはゆったりと静かなせせらぎに身を浸して流れ行くものものをぼうっと見送っているような感覚で――
「万が一、気が変わることもあるかも知れないから、考えておくわ。でも……、狭い棺桶で寝るなんてぞっとしないわ」
「慣れればとても快適なものだ。君の身長に合わせてオーダーしたバスタブに浸かっていると思えばいい」
「ねえ、ダブルサイズの棺桶はないのかしら?」
「くくく、君らしい発想だ。お望みなら用意させるぞ、クィーンサイズでもキングサイズでも。
ところで、それは横に並ぶのか、それとも、上下に重なる仕様か?」
「あなた明日にでも作らせそうな勢いじゃない? フフ……」
たわいもない会話が途切れて静寂に慣れるころ、ふっと空気の色が変わって、時の流れが緩やかになり
急に濃く、重く一つ一つの呼吸が、離れていても感じられるようになる。
そのリズムはよく知っていて、意識せずとも同じ波長を描くように、気付いたときにはなっている。
確かめなくてもわかっているのに、一度は触れ合わせて、それぞれの呼気と吸気を合わせてみずにいられない。
そうしてやはりそれだけでは済まなくて、速まる鼓動を、高まる衝動を、擦り合わせてみることになるのだ。
「震えているな……モリガン」
夢魔の手に握られたままのグラスをとりあげて、吸血鬼が指摘する。
動悸がするのは少し酔っているからだろうが、酔っているのは酒にではない。
「そうよ。ほら、わかるでしょう? どきどきするのよ。久しぶりだから」
「久しぶりってことないだろう。毎晩お盛んな君が」
「あなたとはお久しぶりだと思うわよ。ああ、記憶力のいいあなたは、いつしたか覚えてるのかしら?」
「もちろん。ちょうど百日前になるな」
「……適当に言ったわね」
「適当ではない」
「まさか、毎日数えてるの? 考えられないわ。ちょっとあなたかなり普通じゃないわよ。まあだから
いつまでもリベンジとか考えてるんでしょうけど。適当じゃないんなら、何したか覚えてる?」
「なあ、何をしたか本当に覚えてないのか、君は」
「どんなにスペシャルなご馳走でも、お味はいつまでも続かないし、一晩経ったらメニューの順番なんて思い出せないわよ」
「まだ暑かった。ほろ酔い気分で半脱ぎになった君がそこにひっくりかえって私を誘った。早くきて……」
「そんなこと言ったかしら」
「いろいろ言ってたぞ。もう我慢できない、欲しかったの、あなたの大きいのが、とかなんとか」
「うふ、なぁに、それがあなたの妄想なの?」
「……私の夢想はもう少し洗練されたものだと思わないかね」
「そうかしら……たとえばどんな? 言ってごらんなさいな」
「たとえば、か……。いや、ちょっと口にするのは憚られる。私には羞恥心がだいぶ残っているのでね」
「羞恥心って、そのいやらしい顔つき、なんとかならないの。かなりだらしないわよ」
「とにかく、適当や妄想ではない。君が私を欲しいと思う周期があるということがわかってきたんだ」
「それはそれは素晴らしい発見だわね。……ね、したくないの?」
「……どうだか、確かめてみろよ」
ためらうことなく、無邪気に触れ、耳元であやしく囁きかける。――ねえ、びくびくってしたわよ。今。
「食べられちゃいたいのかしら……」
「ふふ、あんまりいじめるな。もう少し夢を見させてもらいたいものだな。夢魔の君たちならお手の物だろう?」
「ああ、ごめんあそばせ。忘れてたわ。吸血鬼っていうのはロマンティックな生き物で、
中でもあなたは特別夢見がちな、恥じらいを忘れない紳士ですものね。フフッ……」
「勝手に笑っているがいい……。そう、お手柔らかに頼むぞ。下手をすると次に会うのは百年後ということになりかねん」
目を見開いたまま、伸びた舌先が開かれた口内を探る。
「あなたの、声が好き。闇の姿でも変わらない」
それは、人間であったときから変わっていないものの一つだった。
容赦なく襲いかかる甘い感触に掬い取られて、言葉も、思考も、途切れがちになっていく。
悩ましく息をついて、囁く唇が――
「あなたの舌も。可愛げのないことばかり言ってるわりに、温かくて器用でお利口さんだわ」
――ひとしきりじゃれあって舌を解く。唾液が零れるのも構わず。
「表に出ていないところが好き……」
そういって、無言で主張している箇所を押し返す。唇を尖らせたデミトリの表情を観察するようにたっぷり眺めてから、
「んぅん……そこも、そんなに嫌いじゃないわよ。……特に、私の中でいい子にしている時はね」
「そんなに嫌いじゃない、か」
「そうよ、ふふ、一番は違うの。それで、……譲れないあなたの魂はどこに隠しているの?」
「魂か……。今はここにはない」
言葉の意味を確認するように、無言で見つめあう。
「もう、奪われてしまった……」
どんな言葉を吐くよりも、互いの吐息の熱が、逼迫した瞳の光が、何より饒舌に語っている。
舌と舌の先が細かな動きで捩れあって相手の感触の上に自らの欲望を告解する。
どれだけ欲していたか。
その激しさとは対照的に指と指が柔らかくなだめあうように絡む。
身体の隅々まで魅力的な曲線をそのまま見せつけるようなサキュバスの着衣は
下僕の蝙蝠たちが形を変えたもので、夜の女王の素肌をぴたりと覆い護っている。
その気になれば、瞬時に霧が晴れるように消失し、生まれたままの姿が露になる。
戯れに通じた女主人は、彼の手に脱がせる愉しみを残しておいた。
薄皮を剥くように、肌と張り付いた生地との隙間にそっと指を滑りこませていくと、
役目を終えた黒衣たちはどこへともなく見えなくなった。
夜気に晒され、暴かれた部分が多くなるほどに、その肌は熱を帯びて艶めいた。
吐息にも曇ることはなく、愛咬にも傷つかない。
手をつけるより先に、全て脱がせてしまおうと思ったのに、
柔らかくこぼれた胸が、接吻をねだる唇のようにその先を尖らせて
微かに触れた手のひらを突き追いすがってきたので、かまってやらざるを得なくなり
そこで、彼の試みはしばし頓挫した。
最後に黒い翼を自ら消し去って、魔界の頂点に君臨するサキュバスは無垢の娘の姿になり、
降りかかる接吻を浴びて滴に濡れながら、しとやかに吸血鬼の腕にもたれて
その闇のマントに包みこまれた。
「……は……ン……、ねえ、連れて行って。あなたのベッドに。……棺桶じゃないほうよ」
「あなたなら、私を楽しませてくれると思っていたの」
「そうか? それが本当なら、君の期待が及びもつかないほどよくしてやる。
だから言ってみろ、どんな風にされたかったのか」
横たわった女の瞳から目を逸らさずに、冷たい手が左右に開かせた膝頭を撫でている。
夜の柔らかな空気がぬかるみの熱を静かに奪っていく。それでもそこからほてりと水が引くことはなく、
逆に深みを増してゆくのだった。
「それとも、直接聞いたほうが早いのかな、このあたりに」
「たぶんね」
「ふふ、それはわかっている。急ぎたいわけではない」
下腹に頬をつけて、茂みの生え際をからかうように撫で、細い毛に指を絡ませる。
「君のお口が、頼みごとをするのを聞くのは好きなんだ」
開かれた部分には触れないまま浅い臍の窪みを舌先で嬲られて、モリガンは艶やかな肌を震わせた。
「感じられる……君の血の内に、淫靡な香りが開いてくるのが」
制止するのか扇動するのか定かではない夢魔の手が男の頸筋から額を撫でるように動く。
「んふ、つれなくされるほうが、燃える性質なのかと思っていたわ……」
「ふ、まあそれも間違いではないがな」
その言葉とため息に応じて、デミトリは身を起こした。
闇のあわいに静かにたゆたっていた乳丘を捉え、下からじわりと力を加えて揉みあげる。
「あアッ。ん、……。そこ感じやすいの、知ってるんでしょ……もっと優しくしてくれなくちゃだめよ。
優しく、初めての女の子にするみたいに、そっと、そうっとよ……ぁあ」
「ああよく知っている。君が弱いところを責められるのが好きなのは」
くびり出された胸肉を膨れた赤い乳首ごと尖った牙で挟みこみ、ゆっくりと加減しながら舌の裏側で弄る。
「イ…やァッ、だ…め、もう。あっ、あっ、んっ、や、ぃ、いっちゃう、そ、そこ……。ぁアあ、っ、っ、んん」
「ここだけでイっちゃうのか……。モリガン、君は本当に、素晴らしく淫らなお嬢様だな……」
「ヒ…や、イく。いく…………。ぁ」
夢魔の肢体はどこも感覚が研ぎ澄まされ、開花されていて、言葉どおり激しい反応を見せた。
「さて、お嬢様は何を召し上がりたいのか、お伺いするとしよう」
「……何でも出してくれるの?」
「言ってみろよ」
「ふふふ。……ぁ、熱いのがいいわ」
「熱いのか……」
「んん……フフッ、ボリュームがあって……」
「このくらいではまだまだ足りないものな?」
埋まったままの指が擦りあわされ、期待と渇きを掻きたてる。
「あぁ。……私の指を吸っている。君の、よくばりさんのお口が」
「ん……ふふ。そう?」
「お嬢様のご希望は、私のみたいなのか? ……そこをぜひともお聞かせ願いたい」
「みたいなの、じゃなくって」
「じゃなくて?」
「欲しいの。あなたの……」
「何だ……?」
思わせぶりにすぼめられた唇と、なまめかしく半ば閉じられた目を、交互に紅い眼が見据える。
「うふ。やっぱり言って欲しい?」
「言えよ。いいから。……言って欲しい」
「挿れてよ……。あなたの」
「私の?」
「もう……」
吸血鬼の先の尖った耳に噛み付いてやってから、夢魔は、……おちんちん、と楽しげに吹き込んだ。
「おちんちん、挿れて欲しいのか。私に」
「んん、いれてほしい…の。ねぇ、はやく…。二度は言わないわよ」
薄ら笑いを浮かべて、じゃれあっていた息が更に熱っぽく掠れる。
「なら、……どこにだ? ん? どこにいれてほしいんだ?」
唇が塞がれて、押しつけられた唇と熱い昂ぶりが、濡れた狭間を二つ同時に圧していく。
それで何かが切り替わったように、夢魔の腕が男の身体を引き寄せて切なげに訴えた。
「んぅ…あ……、きて。きてッ。もう、あなたの、好きなところでいいから、中にきて」
ブレーキをかける猶予も、選択する暇もなく、ずぶりと腰が沈み込む。
「あ、あ、んんんっ。……やっ、んく、く……」
優美な曲線を描いて反り返った先が伸び上がるように細道の天井を擦り、
深部に収められる感触にサキュバスの声が裏返った。
密な襞波を漕ぎ分け、押し開いて窒息しそうに甘美な圧力に抗する。
「ほら、……ほら。入れてやったぞ。君の好きな、おちんちん。こんなところまで」
「ぁ、あ。……。あ……すっごく、だめ……。だめ…ぇ……ん」
堰を切ってひらき零れていく官能に慄く身が、確かな抵抗のある体に支えられて、その中で存分に攀じれる。
「あぁ……。確かに、すっごくだめ、だな、これは。もうたまらないほど、ぐちゅぐちゅに蕩けきってる…」
「あぁ。んふ……。でしょ。いい……。すっごく、だめ。あん、すごく素敵。ん……。ああ、っ」
大きく開かれた花弁の縮れ捲れた縁を示すように指先が触れていく。
「ぐちゅぐちゅに蕩けているのに、こんなに、きつく私を咥えこんで、放そうとしない」
「あふ、っ、ゃ」
摘み上げられた芽がひくひくと引き攣れる。
縦に振られると、深奥と同時に、剥きだしにされ哀れなほどに充血した部分が頑なで重い力に轢かれ
その直撃を受けて足場を失い瞬く間に脆く崩れていく。振れ幅が大きくなるにつれて、呼吸が深まった。
ずるっと沈み温む腰を更にもう一段埋め込み、密着させたまま真上に引き上げ、直接恥骨に打ち当てるように震わせる。
常に誘うような笑みを湛えていた眼差しが、遠くを望むように変わる。
やがてデミトリは合わせた頬が滑り、濡れているのに気がついた。
「……、もう、泣いちゃってたか」
「ううん……」
「そんなによかったんだな」
「ちが……う、けど、だって……。あなたの、当たるとこ…が、……んッ、う、だめ……」
「ふふ。当ててるんだ、モリガン。……君の奥の、だめなところに」
「んん! ……、そんな…」
「そんなの、だめ、か? 最高にだめ……だろ。何しろ君が泣くくらいだからな……」
赤い舌に頬を舐め上げられ、弱みを突き上げられて、サキュバスは悶え慄いた。
「いやっ……本当に。だめだったら……ぁ。あぁ……ぁ。……」
再び、腰を後退させると、長いストロークの満ち干きに変える。
大きく張り出した先鋒が無遠慮に腔洞を押し拡げ、逃れる余地がないことを思い知らせるように
羞恥と歓喜に充血した秘襞の最後の連なりに至るまでを、ゆっくりと均し巻き込んでくみ敷く。
抜き出すたびに、とろりと白く濃厚な蜜汁が幾筋にも流れる縞模様となって昂ぶりを彩り、
更なる深みへと誘った。
「…………すごくぃい、気持ち、いいの。だめ、もうだめ、ぁう、お、奥、きて。ぁ……」
衰えを知らず鋭く高まり同時に熱くどろどろと崩れ続ける内圧に翻弄されながら
柔乳を掴みあげ重い情念ごと塗りこめるように、加速する。
蛇腹が伸縮するごとく狭間をぬい、繰り返し擦られ捩れる感覚と、深奥の中心を突き貫く
別々の快感に一度に襲われ、戦慄の涙と溢れ募るぬめりと滲む汗とに
夢魔の裸身はくまなく浸けこまれた。
「もう、いきたい?」
「ああ、も、ちょっと。あ、でも、や、あ、イいいぃ。それ、や、あ……いぃ」
「どっちなんだ」
「んう……」
「どうやっていかせて欲しいのか言ってごらん」
尖った乳首を爪の先で突かれ、激しい疼きに苛まれながらも
モリガンはその手を制した。
「……待って、やめて。……あなたので、して欲しいの。深くきて。奥に」
「それで逝きたいのか」
「ん。して……。イっちゃいたい…の…」
「いっちゃいたいのか……」
「ああっ、もう。ああ、だめ……。もっと、突いて……あ、もっと、して。して欲しいの。あなたのでいっちゃいたいの。
きて。ああっ、あああッ。そう、そう。あんイく、……ん、ん、ん、だめ……あ、あぁ……ん!」
「モリガン……ここに出されたいか?」
「ん。ん。欲しいわ、ああ」
「言えよ。なかに……」
「ちょうだい、ちょうだい。あ……、んんっ、だして……いいわ……。私の……なか。熱いので満たして欲しいの」
熱に浮かされたうわ言のように、やっと押し出された甘い主旋律も、デミトリを満足させるには充分ではなかった。
「目を開けて、私を見てみろ……誰にやられているかわかるな?」
目が合い、声を発する前に、見開かれた瞳が揺れる。
「ぁあん……きて」
震える指が彼の顔を愛しげに撫でる。その手首を捉えて、デミトリは囁きかけた。
「わかったら、なかに射精してください、と言え」
「っ、……」
「言えないか」
「ん……っ、んんんっ」
感覚から逃れようとでもするように、最後の抵抗をするためか、あるいはこみ上げる悦楽に心底から歓び悶えて
小さな叫びが漏れる。
「いや……! だめッ、デミトリ、……」
促すように、深く貫いた先の角度を変化させると、ふらりと均衡を失って淫魔がまたしばし小さな頂きに達してしまう。
「ふふ、ついに言えなかったな。モリガン。君にも出来ないことはあるのか」
涙を浮かべて、とろんと蕩けた瞳に、わずかな憤りの色が鋭さを失わずに閃く。
「可愛い私の虜……。お前が言えなくても、いやがろうとも、そうしてやる」
薄い血の色をした柔らかな唇を、開いた口腔を塞ぐと、苦しげに呻きながら、腕と内壁とが夢中で絡みついた。
「ぁん、ぁ、ぁ、あぁあ、ぁあ、きて、ぃい、っ、、ぁっ……ィく、うぅ…ん…」
ラストスパートをかけ急激に極まる絶頂まで、サキュバスの歓喜が即座に追いつき連なった。
「……おいで」
しかと夢魔の肉体を抱き寄せる。最後にそこに捉われた腰が弧を描いて終極に埋まる。
激しく震える身と小刻みに収縮する心の奥に届かせるように
もてる限りの望みを遠慮なく全て注ぎ込む。射ち込まれるたびに、その肢体が大きく波打つ。
「あああッ。ああ…………! っ……あ、だめ……ふ……ぁ」
太い胴管を奥まで呑み込み限界まで拡げられた花口から
たちまち白い精汁が溢れ滲んで絡み合ったままの四本の太股を染める。
すすりあげようとする内襞の奔走も待たずあとからあとからとめどもなく滴が垂れ落ちた。
「ああ……はぁ、まだ、きてる……。ぁあ。ぃい――」
「好きなだけ呑め……」
「はぁ……。ん…………。ぎゅっ、て……して。デミトリ、ぎゅって……。あん。
ああ。感じるわ……。あなたの鼓動みたいに……まだ熱くて、……溺れちゃいそうなくらいに溢れてるのが……」
「く……、もう全部……君に搾り取られた気がする……」
「すぐ起きないほうがいいわよ。こうしていて、ダーリン。うふふ」
*
意識を取り戻したときにも変わらず夢の姿があった。
どのくらいたったのだろう、数秒か……数時間か、とデミトリは考えた。
「そのドレス、君にとてもよく似合うな」
「ああ、これ。いいでしょう? ふふふ。これは私も一番気に入っている格好なのよ」
と同じシーツの隙間に眩しい裸身を横たえた夢魔が答える。引き寄せられて
その素肌に纏うものは太い二本の腕になった。
「まだ消えないでいてくれたんだな」
「ご迷惑?」
「……まさか。そんなわけない」
「あなたがそういうのなら、もう少しだけいてあげる」
そういって滑らかな頬が摺り寄せられた。長い睫毛が触れる。
それからしなやかな脚が巻きついて彼の脛を挟み込んだ。
かすかに熱の残った肌の香りを味わいながら
「モリガン……」
と呟く。自身に言い聞かせるようにもとれた。
「本当は忘れていないんだろう。なぁ……? 忘れてないからここに来たんだ……」
薄く開いた瞼の下で、掴みどころのない光が微かにきらめく。
「ん。勝手にそう思っていれば。そう思っていたいのなら」
「私のことを考えてくれたんだな。君の、寝室で。
……夜毎のつましい収穫や拙いもてなしに飽き足りず、眠れぬ暁を迎えるたびに……
思い出してくれたわけだな。私のことを」
「ふふ、あんまり変な妄想ばかりしてると本当におかしくなるわよ」
「甘き瞑想に耽っていて、美しき夢魔が現実に襲い来るのなら……悪くないじゃないか。上出来の運命だ。
……笑わないのか?」
「笑わないわ……そうよ。だってそういうものなのよ」
「次の機会には、君の夢の詳細を聞こう」
「覚えてたらね」
「モリガン」
吸血鬼の赤い眼が熱っぽく見つめた。
「君の夢が追いつかないくらい良くしてやる。だから、覚えていろよ」
「ま努力してみるわよ、忘れなければね」
「……覚えていろ、と言ったんだ」
「気の利かないこと言わないで。もうそんなせりふ聞きたくないわ」
「覚えていられないのなら、もうこのまま君を帰さずにいようか」
溜息をついてみせながら、淫魔の内部に緊張が走ったのがわかった。
「サキュバスの話をしただろう? ……あの夜の夢魔が君ではないことは、もちろんわかっている。
いくら君でも、この私を忘れるはずがないからだ」
「なに……何が言いたいの?」
「私が殺したんだ。彼女を。閉じ込めておいたら死んでしまった。
あの頃の私はまだ、他に術を知らなかったが……」
乾いた唇が、細い手首の内側に浮き出た血管をなぞる。
「君を傷つけてやったら、取り返しのつかない傷をつけてやったら、忘れられるはずがないな?
今夜のことも、私のことも、――永遠に」
尖った歯の先が薄い皮膚を掻くのを、モリガンは息を呑んで見つめた。
面倒な事態になる前に、帰るべきだったかもしれない。
だが真剣な瞳の色か、そのうちに微かに残った微笑のせいか、その手を振り払うことがためらわれた。
吸血鬼の顔はどこか見覚えのある少年の面影を映しているように感じられる。
――そういう目をした純情な少年ならば、実際数え切れないほどいたのだ。
彼の昔話が本当だろうとそうでなかろうと大した問題ではない。おそらく初めから作り話なのだ。
問題なのは、そういう形で表された感情は確かに存在しているということだった。
この男もまた、自分を前にして負い目を感じ、そのことに傷ついているのが、意外なことのように思われた。
震える牙が青ざめた肌を突いて、小さな痛みを与える。
「覚えているがいい……」
モリガンはただそういう男の目を黙って見つめ返し、その髪を撫でた。
そんなことをしなくてもいいと、教えてやろうか。
「デミトリ……」
呼びかけられると、吸血鬼は急に冷めた表情になって手を放し、恥じ入るように顔を背けた。
その間に、消え去るがいいとでもいうように。
抱きしめようとすれば、甘すぎる夢の肌触りに抵抗するごとくその心が閉じていこうとする。
「ねえ、デミトリ、こういうのはどう? あなたの夢は私が預かっておいてあげるわ。
あなたを私にちょうだい。あなたが欲しいの……。何もかも忘れて、私に委ねて。
いつまでも、愉しい夢だけ見ていればいいじゃない? 私がずうっと、ずっと大切に可愛がってあげる。
ずうっとこうして、甘く、熱く、蕩けているの……眩暈がするほど素敵だわ……。
だから、あなたのその魂を私にちょうだい。それとも……もう、私にすべて捧げてくれたのだったかしら?」
深い息をつき、彼の小さく重い声が答えた。
「勘違いをしているようだが、……モリガン、私はな……、君になめられて喜ぶような腑抜けに成り下がって
生きていたくないのだ。嗤いたければ嗤え。そんな呆れた顔せずに」
「うふふ、ちょっと感動したのよ。あなたのそういうところ……、頑なで、生硬なところ。
悪くないわ。こっち向いてよ」
閉じられた唇に、自らのそれを触れ合わせ、温く長い息を吐きかけながら、
「好きなの。そういうところが。だから、欲しいの。揺らがず固く高い志で私を熱く燃えさせてくれるものが欲しかったのよ。
もう一度、あなたの誇りを見せて、デミトリ。あなたのものにして、私を」
さもなくば、その場で殺しあうしかなかった――どちらにしても、背を向けることは出来なかった。
自身を説き伏せ奮い立たせて、覚めぬ夢の奥行に踏み込む。
結局のところ大して違いはないのかもしれない。行き着くところが同じなら。
仕掛けたのか仕掛けられたのかも定かではなく、尽きせぬ悦楽の海に溺れている。
動きを止めて、見つめあい、互いの起伏を仔細に味わう。
潜めた呼吸が時々不規則に揺らぐ。
手にした果てなき美悦の名を呼ぶと、うっとりと濡れた瞳が瞬いて、舌の先と淫らな囁きが耳孔を擽る。
「んく……ぁん、ぁ……、ね……気持ちいい…でしょ、私の……なか……、××んこ」
「君には、二度とそういう言葉を口にして欲しくない……私以外には」
「……あなたって、かわいいわ。もっと……もっともっと堕としてあげたくなるわ……」
「やってみろ……それも満更でもないと、どうして知ってるんだ?」
「ふふ、気持ちいいことは嫌がらないものよ。誰でもね」
うねりが、骨まで砕くような激しさに変わる。
その勢いに押し流されそうになりながら、夢魔が声を忍ばせて肩を咬む。
「ねえ、デミトリ……。お願いが、あるの」
「今度は……ちゃんと言えるか?」
「あぁ……、してほしいの……。あ……だめ。もう……。イく。お願い。一緒に……きて。
ぁあ、きて。好きなの。して……あなたのものに。して、デミトリ……」
耳を疑う。差し出された首を、あれほどに望んだまたとない機会を。
「……そう、私をあなたの虜にして」
「いい覚悟だ……おいで。私の、愛しいしもべ」
その喉の白さとこみ上げる思いとに目眩めいたほんの一瞬に、
絶妙な均衡が破られ、後は自ら圧倒的な快感の奔湍に身を委ねた。
*
それは罠だったのか。まんまと計略にかかってしまっただけなのか?
別れ際に離したばかりの唇が、甘い溜息をつきながら彼に問いかける。
「そう、私……なにか言ってたかしら?」
たっぷりと、夢魔がまばたきを五回するほどの間見つめあってから、
噛み付いてやりたい衝動を抑え
「よく覚えていないな」
とデミトリはそ知らぬ顔で答えた。
目を細め、ふふっと満足げな笑みをもらして、夢は闇の彼方に帰っていく。
2007.04