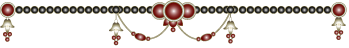シャンパンフルートの細長いグラスを思わせぶりな仕草で指の間に挟み
すっと撫で上げて優しい動きでクリスタルの表面に指を絡める。
薄い縁を親指の爪の先が擦る。
握った手の中で泡が溢れて弾ける。
途切れることなく、ばら色の水面で飛沫をあげている。
その動きを、見るともなしにぼんやりと追っていた。
ふと見入っていたことに気がつかれ、かすかな動揺を覚えて
わずかに開いたままだった口からようやく小さな声を出す。
「そこ……、そこをずっと掴んでたらぬるくなる」
「え? ああ」
と初めて気がついたかのようなふりをしてあやしい笑い方をする。
「じゃあ、教えてよ。どこを掴めばいいのかしら」
「知っているくせに。だいたい、その手は何回使ったんだ」
「あなたが初めてよ。
……乾杯するなり物欲しそうな目でそこじゃなくて脚の付け根を握れ、なんて言う人は」
「そんなこと誰も言ってない。そもそもグラスの話だぞ」
あっけに取られた顔を見て、更にサキュバスが図に乗ってしまった。
「だからそう言ってたのよ、あなたの目が。……それ、戴いてもいいかしら?
こたえてよ。……フフ、もうお返事もできない?」
触れ合う箇所の温度を感じながら
どちらから手をつけるべきか、と一瞬彼は逡巡する。
泡が消えるのと、この夢が消え去るのとはどちらが先なのか。
「そんなに焦るな。私は逃げないし、まだ時間はたっぷりある」
調子に乗って動く手首を掴んで引き剥がす。
虚をつかれたような表情をする。
「もうちょっと待てないのかな、いい子だから。ここを持つんだ。
これは後でも味わえるだろう? ……モリガン、楽しみは後にとっておくものだ…」
*
そうして、彼は来た。
背後から腰を掴まれ熱い体温を感じる。
見つけたいものをそこに探しあてて、指の腹が確かめている。求めている徴を。
触れればわかる。どれだけ焦がれていたか。
触れなくてもわかる。もうその熱が近づくのを感じただけで、膨れ上がった蜜腺が溶け崩れている。
そこをかすめるように行き来する。
っ…。
声を抑えても体が勝手に反応してびくっと震える。
面白がっているに違いない。かすかな力で撫でながら指先が次第に邪まで執念深い性質を表していく。
そのままいいように蕩けさせられるのも癪だった。
「…ん…ふ、したかったの…? こんな風に。だったら、そう言いなさいよ…正直に。
やりたくてたまらなかった、って……。
ねえ。言って」
言われて初めて自身の気持ちに目を向けてみて、驚いたとでもいうように
動きが一瞬鈍くなる。迷っている様子だ。その心は既に知っている。
巧妙に隠したつもりでも、目を見ればそこに色濃い願望が表れている。
知っていることをあえて言わせ、意識させてから、おもむろに許してやることにする。
「言ってもいいわよ、デミトリ。あなたの本当の気持ちを」
「こうやって、思い通りに……」
「思い通りに?」
「したかった。私の手の内に閉じ込めた君を、
何もしないうちから、こんなに……滴らせて、鼓動を早めて、震えている…君を、
……楽しませ、歓ばせて」
何かを堪えるように低く抑えた声に反応して
深い底でその入り口があえぐように開いたり閉じたりしているのがわかる。
薄い縁の円周を中指の先が辿る。最初は穏やかな直線で、
やがてヘアピンカーブを描いてくるりと一周する。欠けることのないように力を入れずに。
「フフ……ん…ン…っ」
揺れる体を、胴の周りに巻きついた腕がしっかりと抱える。指先に熱がこもる。
「泣かせて、叫ばせて……」
二つの指が慇懃に迎え、わずかに起ちあがった形を示すようにミリ単位の動きで軽く扱きあげる。
「悶えさせて」
「……ぁ、ぁん…!」
「やりたかった……。
嫌というまで…酷くて、激しくて、できるだけ残忍なやり方で君を……
殺してやりたくてやりたくてたまらなかった…!」
――ッあ。
思わず跳ねあがる体を両腕で痛いほどに抱きしめられる。
その手が胸を掻き毟り、心臓を握りつぶすように、あるいはその衝動を抑えようと、わなないている。
「は、……言ったぞ。正直に。お望みどおり」
かすれた囁きが耳を打つ。瞳が興奮に潤んだ。
「すてき。して。その通りに」
腰に巻きついた腕を撫で握り締めると、ふっとその力が緩む。
振り向いてその冷たい頬に口づける。
吸血鬼は黙ったまま怒りを抑えたような引きつった笑いを浮かべていた。
「してよ。……あなたにそうされたい。私に触れながら、そんなこと言う人初めてよ。
心の底で思っていてもそうそう口に出しては言えないことだわ」
応えようとする愛撫が、非情な言葉とは相反する濃やかで優しい感触が
欲望を更に増長させ、甘やかす。
両頬を挟んで唇を吸われる。
ゆるやかな動きが舌先に執拗に絡みながらその苛立ちを告げ、息を詰まらせ苦しめる。
もうそれだけで快楽を酌む杯がいっぱいに満ちその縁に曲線を描いて盛り上がる。
身震いした瞬間に、たちまち決壊して内腿を流れ転がり落ちていく。
鉄の匂いがする赤黒い血を何より好む魔の触覚が
熱に疼いて蕩けた箇所を探してその身を浸そうと捩れている。
あ…ぁ…、ん。
直接触れていない深みにまで感覚が反映されて
もうその細く狡猾な舌が届くはずのない膣奥で跳ね、くねっているようにさえ感じられる。
意識するほどに激しく熱く調子づいて。
不安になるほど甘く柔らかく、のらりくらりと気まぐれに戯れているようでありながら
正しく地形を読みとって進むべき方向は誤らない。
過敏な弱所をそっと優しくいたわるふりをして、ひとたび気を許せば勝ち誇って制圧する。
もがく腕も囁きも絡め取られ、喉と臍の奥からしゃくりあげるような泣き声だけが粘膜に響いて伝わる。
ああ、これでは、完全にやられてしまう。今日は。彼がその気になったなら抗う術がない。
そして、その気でないわけがないのだ。もう立っていられない。頭の芯からよろめいている。
「あん、待って…。殺す前にはちゃんと飲ませてくれるんでしょ……半(デミ)ボトルでは、足りないわよ」
「…君の最期の願いは聞き届けてやろう」
腕をとって導かれ、熱く滾った情熱に表れたその心を握り締める。
「どうしたい?」
ぶら下がった耳飾りと魔物の牙が触れ合い、かちかちと音を立てている。
「ふふ」
応えずに撫でさする。呼吸が早まっている。
「言え……君の声を聞きたい。今度は君の番だ……私を喜ばせるようなことを言ってみろ。
こういう時にいつも君が言っているようなことを」
「多分あなたは喜ばないわ。ばかばかしいと思って」
「そうとも限らない」
指の間に乳首を根元から挟んでゆっくりと距離をとっていく。徐々に引かれた重さと切なさが強まる。
「あ…ふ…」
身を捩り逃れようとしても、かたくなにその距離を宙で保っている。
「好きなの。あなたと、こうするのが。何よりも」
「ふん。そうか」
「信じてないのね? でも本当よ。あなたが欲しいの。もういいでしょう」
「私のが、だったな?」
「うふふ。それだけじゃなくて、あなたが。私のものになってよ、観念して」
「君のものになった男の末路は…幸せな余生を送るとは思えないな」
「人聞きの悪いこと言わないでよ。ちゃんと末永くかわいがってあげるわよ。たっぷりと」
「君の望むものが、この私から得られると思うのか」
「思うだけじゃなくて知ってるわ。あなたが自分では気がついていないことも」
「君の言うのはこれだろ」
引き寄せられ、触れ合った。既に沸き返る蜜が表面を覆いつくし、くちゅくちゅと絡み合う。
「あっん…。フフ…きて。は、あぁ。うっ」
「モリガン、残念ながら逆だ。君が私のものになるのだ。
これだけのことなら、こんなものなら、いつでもいくらでも与えられるのに」
先端で撫で回されていた部分がわずかに突っ張って抵抗する。
もう少しでも位置をずらせば次に進んでしまう。
互いにそれを待ち望んでいながら、相手に選択を委ね、己が元に降る瞬間を獲得しようとする。
高まり募る相手への期待と自己の忍耐でともに深まる吐息が滲みあう。
絡めた指を握り締め震わせて、その重圧に抗っているのか押し崩されるのを願っているのか。
やがてどちらからともなく、熱に触れて融ける雪のように自然に境界が揺らいだように思った。
ぞわぞわとした感覚が背筋にも内襞にも伝わる。徐々に溺れ始めているような。
その重さがその質量が浸透していく。その感覚が伝える、鈍く厚みのある響き。
「う…ンッん…、あ、あ」
絡みつく肉襞を押し広げながらさらに深くその身を沈める。軽く上下に揺さぶりながら
奥に進む動きが息を乱す。
残響を感じる部分がある。このまま動かれたら、そこを攻められたら。
思わず想像しただけですでに腹筋が意思に反して縮み上がる。彼が腰をゆっくりと浮かせる。
「ぁ……ん」
それを捉えようとしても捉えられない、掴もうとしても掴みきれない感覚のもどかしさ、目尻に涙が滲む。
「今日は随分と脆いな。どうしてだろう」
辱め、煽り立てようというわけでもなく、自分に言い聞かせる独り言のように呟いている。
「あッッ、……。会いたかったから。言ったじゃない。あなたとするのが好きなの。わかったでしょ」
「ふ。そうか。会ってこんなふうにされたかったからか…。それはいい」
その言葉を試すように小刻みに振られる。上下に動き奥には進めない。ひっかかりを感じる部分が、
舌の表面のような細かい襞が、絡み噛みあって摩擦が強まる。
「ああ…それ、だ、め」
「先に進めたほうが宜しいか」
「よろしいか、じゃないわよ、あん! 知ってるくせに。ひ、ゃ…」
「素直に言えなければいつまでもこのままだ」
「いや、そんなの」
「私も、それは嫌だな」
「言っておくけど、あなたが我慢できなくなるほうがきっと先よ…」
「それはどうかな。でもそのつもりなら、まだ当分かわいい君は見られないのか?」
締め付けて捻ろうとしたが力が入らない。ぬるぬると滑る中がさらに感覚を高めて苦しめる。
「どうなんだ。恥を忍んで私の秘密を白状してやったかいがないな……。くく」
唇の端を歪めて自嘲的な笑みを浮かべるその目を、一種の感動を覚えて眺めた。
苛立ちが暗い翳りを落している。それが爆発するところまで引っ張れるだろうか。
いや、自分が我慢できなくなるのが先だ。きっと。
もう舌なめずりを繰り返してぴちゃぴちゃいう音が聞こえる。
「この期に及んでまだおあずけが必要なのかな、君には」
あと、ちょっと、ちょっと押されたら、回路が繋がり、声になって出てしまう。
意味がよくわからないまま覚えた何かのフレーズのように、無意識のうちにうわごとのように口走ってしまう。
「ああ、もう、お願いだから、そんな意地悪しないで来て。欲しい。ほしいの。奥にまで」
相手が相手なら、絶対に使わないのに。
もう声に出して言ってしまったらそんなことはどうでもいい。
彼は途端に気分を害したように見えた。あまりにわざとらしく響いてしまっただろうか。
「本当なのよ…ねえ」
冷たい石のような瞳の表面が何も映さず、無機質な光を放っている。
だが、すぐにそれが彼の回路を繋いだためだとわかった。
「モリガン……。今なら言えるか」
「いいわ、言ってあげる、特別に」
鼻先を舐めあげてやると、わずかに細めた目に逸る血気が覗く。
「君が普段は恥ずかしくてとても言えないようなことだ」
「なあに」
「言えるか? 私のものになると」
わずかな照れが儀式めいた場面と素振りを選んでいるが、その底にある心は戯れではない。
本当にかわいい。髪を撫でて耳元で囁く。
「あぁ。もう。そんなことなの? あなたの、ものよ。全て…。今はね。
して。好きにして。感じさせて欲しいの。あなたを」
その一言一言を発するたび、ゆるりとだが確実に絡んで包囲している円環に、
切れのある脈動が響くのが感じられた。
この高揚は自分のものなのか彼のものなのか……、まあ、もうどちらであっても構わない。
戯れではないことが伝わっただろうから。
環が静かに閉じてしっかりと抱きしめる。今はまだ頼りない糸口を放すまいとして。
「よく言えたな。かわいい私のモリガン。では欲しいものをやろうか」
「あん、素敵。いいわ。あなたのが好き。きて。一番奥まで」
「ふふ、その調子だ。もっと私を喜ばせろ」
ん…!
ぬめりながら一杯に漲り奥まで到達したものが、熱く内部を圧倒する。突き当たって
空吹かしするように、あるいはたたらを踏んだように、揺らめいた体が乳首の先を優しく押して歪ませる。
内側から胸までこみ上げたその限界を感じたとき、一度、鋭く跳ねてから重く突き動かされた。
「う…んッ、ん、んんっ、いい。いいわ。ああ、あ…。…デミト…リ、すごく、いぃ、いい。ああ」
「これが、好きだったのか」
「ん、好き。好き、そうされるのが。んくっ…あぁ」
腰の後ろに回された手がその下を更に引き寄せてウエストから折れた下腹部を平行に沿わせる。
衝撃を受け止めきれずに揺らいでいる胸も唇に挟まれて引き上げられ、固い歯にゆるく拘束されて逃げ場を失う。
狭い隙間に伸びた手が開かれた結び目に触れて、張り詰めた感覚を更に持ち上げる。
そのまま指先が捻れていく。
「あっ、く…く、ん、それ、…たら、いっ、っっちゃう、ん、ん…」
「そんなに慌てなくてもいい…」
そういうくせに、突き入ったまま恥骨を擦りあげるように更に圧迫しながら
掴んだターンを逃さずに一気に落とそうと仕掛ける。
その目論見通り、随分早く達してしまった。
「はぁ。……あなたを、ちょっと……見直したわよ。ふふっ」
まだ勢いを失っていないのを確かめて、蕩けた目つきで見上げる。
「まあ君がどれだけ私を見くびっていたか、ということだな。
私のものになったなら、いつでもこうして可愛がってやるのに」
「可愛がって、もっと、死ぬほど。そうしたかったんでしょ」
誘うように伸ばした舌の先が、軽く閉じた唇の間に吸い込むように受け入れられる。
もう一方の果てで同時に行われていることの返礼をするように、柔らかく包み込みながら
吸い込まれて、唇が押し合う。踵で広い背中をそろそろと撫でてけしかける。
頬が火照っている。貫かれた箇所が、周りを熱で溶かしてしまいそうなほどに感じる。
触れ合っているところ、境界と輪郭の全てが液状に蕩けて今は凪いでいる。
ひとたび境界が揺らいだら、今度は競い合うように引き寄せようとする。
その隔たりは、何が、どちらが作っているものであったのか。
妥協できないプライドのせめぎ合い。だが、敗れ去ることを、死を恐れているためではない。
既に相手の手の内に堕ちていることを自覚していながら、もったいぶって
戦利品の引渡しをぐずぐずと先延ばしにしているような……。
あるいは、甘い褒賞をちらつかせて引き返すことのできない奥地にまで踏み込ませるか、
相討ちは覚悟の上で。そんなわだかまりも、このままいけば解けるものだろうか。
「あぁん、待って。まだ…動いちゃ、だめよ……」
「動いてるのは君だ……君のなかが動いてるんだ」
「…うそ」
「ふふ、嘘じゃない、…わからなかったのか?」
無数の繊毛がわずかに捩れながら蠕動しているような気がする。意識しないまま、途切れることなく。
「……ぁ」
意図しなかった深みにまで、悪しき血に侵されている。溶かされた箇所を制御することがかなわない。
「これでも、わからない?」
ずれが生じる。
浸っている部分がゆるんだ境界線をゆっくりと伝い、これまでに踏破した距離を示して回遊する。
遠く反発する弾力の強さと同時に包み込まれている温かさに皮膚も意思も流れ動いていくようだ。
それは意外なほどに心地よかった。感覚が麻痺しているのかもしれない。
どこか頸の裏の奥底からじんわりと眠気のような酔いが広がっていく。
いつの日か見た幻の光景なのか、それともつい先ほど実際に起こったことか――
鎖骨の上を這っていた唇が、首筋の柔らかな肌を上り、気づいた時には既に噛まれていた。
ちくりと棘がささったようなかすかな違和感が、次の瞬間に恐ろしい熱を持って膨れ上がり
激しい疼きに変わる。破られた肌の表面は焼けつくように熱いのに、
内側からは頭の芯まで凍りついたような悪寒に襲われている。
本心から、永遠に繋がれてしまいたいような気持ちがする。
全てを支配されて最後の血の一滴までも冷たい闇の底に引き摺られていく。
髪を掴まれ、硬い石の床に引き倒され――
何度も屈服させられて、でも決して精気を与えられることはない。
力が奪われる。意識までも奪われていく。そのだるさがもはや快感になってしまった。
ああ。もっと。
そうやって掴んでいて。私の全てを。あなたのものにして。
今なら理解できる。
吸血鬼の虜となったものは皆、心の底ではそうなることを待ち焦がれていたのだと。
自ら気がつかないほど、強く遠く探し求めていたからこそ、
かの姿を見出してしまうのだ……自身の暗く優しい闇の中に。
厳格で強い絶対的支配者の、危うく甘やかな誘いに、その冷たい命令に耳を傾けてしまう。
本当は血の儀式など改めて必要ないほどに、目が合ったときにはすでに絡み取られ繋がれている。
心を縛るのに道具はいらない。プロトコールを知るものだけが了解している。
何かを問われていたような気もするが、思い出すことができない。
もう既に引き返せない決定的な選択がなされた気がする。
あるいは、それは言葉にして発せられたものではないのかもしれない。
言葉で聞くのとは違うことを試されていたのかもしれない。
うっとりと虚ろになった存在を、ゆらぐ感覚を支え補うように、その意志がそつなく導いていく。
折り目のついた書物の頁を無造作に繰るように開かれてしまった。
腰を下ろされたときには黙っていても読みなれた場所が提示されている。
倒した膝の間に、泉に口を漱ぎ礼拝するように身を伏せて、
あわせた唇がひそひそと彼らにしかわからない会話を交わす。
どこに何が記述してあるかは諳んじていて、忘れてはいない、どんな小さな反応も残さず掬い上げ
幾重もの連なりの奥に秘めた蜜をつきとめて薫らせる。
思うようにならない体が、思考の速度は落ちているのに、受ける刺激に対しては何倍にも鋭く反応する。
魂を売り渡した者の地獄への道のりを、再びその手強い円周を螺旋を描いて降ってゆく過程で、
段差につまづき意識ごとよろめく度に呼吸が止まりそうになる。
衝撃を避けて身を捩ると髪を引っ張り肩を掴んでまた同じところを通されてしまう。
何度繰り返されてもスムーズには通れない道なのに。もう、そこは。
音をあげるまでやめないつもりか……、
あげても許してもらえない。
これまでは相手を征服する行為であっても、征服されることはなかったのに。
果てもなく沈んでいくような感覚にとらわれ、その行き先にかすかな不安を覚えて思わずしがみつく。
「ぁあん、もう、嫌」
「嫌? フフ、いや、じゃないだろう? 君としたことが」
聞こえないほどの声で呟いたつもりだったのに、すぐに、背けた顔を顎を掴んで覗き込まれる。
「……いやなの。……泣いちゃうから」
「もう見た。君の可愛い泣き顔は」
「だめなの……いっちゃうから」
「いっちゃえばいい。今更恥ずかしくなったのか? この私にそうされているのが」
「さっさと殺されるほうがよっぽどましだったわ。こんな…辱めを受けるくらいなら」
「今までのは、私を騙すための策略だったと、演技だったとでも言い逃れるつもりだったのかな
……我を忘れた顔を見られるのがそんなに口惜しいことだとは」
膨らませた頬をつまんで引っ張られる。
「もう。黙って」
顔を見られないようにするつもりで、引き寄せて頬を合わせたのに、
熱を帯びているのを悟られたばかりか、更に耳の近くで囁き声が追い討ちをかける。
「ククッ、自分の姿だけを見ていたからだろう…? 鏡の代わりに、
この世で一番美しいのは君だと答えてくれる男どもを、侍らせて、こうやって奉仕させながら」
「いい加減にしてよ」
「だが、心配することはない。私も彼らのうちの一人だ。誰よりも君の美しさと強さを崇めている…」
「そんなこと言って……許さないわ。あなただけは」
「特別扱いしてもらえるとは嬉しいな。モリガン……。そのまま、こっちを向いて。目を閉じるな。
君の顔を、その瞳を、見ていたい」
「……っ」
深く突き刺されて、言い返すこともできず、新たな傷から血が滲み出すように視界が澱む。
いい気になった吸血鬼が極まるべく始動する。
抉られる度に搾り出されるような喘ぎを止められない。
ああ――、許せない。こんな思いをさせて。もう、ふざけてないで早く。
きて。あなたのが欲しいわ。あなたが私の中で拡がっていく感覚が好きなの。
私を呼びながら、喰いついて、私を傷つけてその悪しき血が侵していく。
あなたの、私に抗する強靭な意志に貫かれるのが何よりも好き。そしてそれを捻って捩って挫くのが。
いつかその冷たい胸に砕かれて散ってしまうのを夢に見ている。
もう焦らさないで。踏みとどまらなくていいわ。往き着くところまでいってもいい――。
返り血を浴びたような生温かい感触が一瞬にして肌の上に拡がった。
重なる体の隙間に滲みこんでいく……わずかでも距離が生じたらたちまち熱を奪い去り
二人の間にはまた深い溝が生じ、凍り付いてしまうに違いない。
長い時間がたったような気がした。が、ほんの数秒であったのかもしれなかった。
なぜかその心を見てしまうのが怖い気がして、目を開けられない。
「……どうして? どうしてくれなかったの」
「魂まで吸い尽くされたら敵わないからな」
硬い声……それは趣向というようなものではなく、明らかに恐れだった。
「……こうしていつまでもやらなければ、まだ少しでも繋ぎ止めておけるのか?
君を手に入れるには……完全に屈服させるしか方法がないのかな。本当に殺してしまうか」
「ここにいるのよ。あなたの腕の中に。全てあなたのものじゃない。好きにしていいって言ったのに」
それを掴むことをためらっているのは誰なの。
心の中で呟いた。口に出しては言えない思いを。
まだ迷っているの。可愛いデミトリ。
もう一つ方法があるわよ。あなたが屈服すること。素直に。自分の心を認めて。
全部本当なのに。あなたが心を決めれば。
好きなの。こうしているのが。好きなの……。
あなたが。
まだ気がつかないの? それとも決心がつかないの?
「好きにする……? ふふ。
刹那の快楽を与えることは簡単だ。だが、私が望むのはそういうことではない。
私のものになるという意味は、私の血を、私の命を分け与えるということだ……」
冷やりとする感触の指が、耳の後ろから首筋をなで、喉元のくぼみに下りてくる。
「わかるか。君がするように相手の命を奪うことではない……」
「一刹那では物足りないのね?」
「ふ、永遠では物足りない。だから……君を手に入れたい」
*
表面をゆるく滑っている。水の皮膜が泡立てられる音色を響かせ千切れ滴になって飛び散る。
その声がだんだん余裕を失って、普段は聞けない思いつめた声音に変わる。
切ない吐息を飲み込んで舌の上で味わうと、痺れるほどに鮮やかな共感覚が拡がる。
意地の張り合いが馬鹿らしくなるほど、もうずうっとこうしていたい。
余計なことは言わなくてもよかったのだ。最初から。
ゆるやかに後退する動きに引き摺られて
その快感がどこまでも引き伸ばされていく。爪痕を残しながら、地平線の果てまでも。
傷つけられた部分に甘い樹液が滲む。想いが縺れて、更に肌を湿らせる。
視界が霞んで見えなくなるところまで行ってしまいたい。
思考も彼方に沈んで、この感触だけで息を繋ぐところにまで。
ねえ、わかる? こんなに。ねえ。
舐めあい擦れあう熱を帯びた肌の下に、香りたつ精血が更なる渇望を呼び覚ます。
どちらが征服するか、勝利を手にするかという次元を超えて、本能の飢えに駆られて
堪え性もなく、そこが接吻を繰り返している。吸い付きながら息継ぎも忘れて
引っ張り合い、もつれ合って、絡んでいる。互いに伸びて引かれて弾かれて。
ああ、まだ、これではまだ。飽き足りることを知らず貪りあっている。
相手の全てを汲みつくそうとするように。
しばし動きを休めた時でさえ、内側は治まることなくあがき続けている。
今はゆるく柔らかい水分と感情に包まれてうまく力を逃し滑っているが、
低く鈍い唸り声をあげてくすぶり踏みとどまっている互いの衝動が、一度噛み合ってしまったら
やはりどちらかを死に至らしめるまで止まれないだろう。
仰け反った背後で髪の先が着地するたびぱたぱたと音がする。
その度ごとに気持ちが強くなっていく。
もう、それなら……それでもいい。止まらないで。このまま沈んでもいい。
いいわ。
あなたの鼓動に揺られたい。いつまでもあなたのその拍子と速度で揺られていたい。
連れて行って。早く。したいのなら、抵抗する隙を与えずそうして。
束縛されたくはない。縛るのなら、息もつかせないほど
考える暇も抗う術もないほどに強く私の全てを握っていて欲しい。
わかる?
こんなに……。
「わかっている」
瞼を開くと目が合った。声に出して言ったつもりはないのに。
「わからないとでも思ったか」
あぁ…! 確信を持った響きに胸を打たれる。
「なに? 何がわかってるの? どうして?」
それでも聞いてみると、彼は意外そうな顔をした。
「ああ、もういい。目がそう言っていた…。わかっている…もういい、いくぞ」
小さな声でもう一度、いくぞ、モリガン、と呟いて息を吸い込み、目を閉じる。
きっちり咬み合うよう設計されたもののように、くっ、とそれが嵌まりこんだ。
もう滑る空間もたわむ有余もなく、ぴちりと塞ぎ尽くしたまま、そう言った通りに核心を衝いて
最初から自身の臓器の一つであったかのごとく内規を離れず精緻で凶暴な脈を着々と刻みあげる。
境界を突き破るのではなく癒着してしまったまま塵灰となそうとするように。
受け止めることがかなわないほどまで激しさを増して。
ああ、だけど、これでは……。共に砕けてしまうしかない。いいの?
もう無理。これ以上我慢できない。制御できない。いいの、それでも。
ちょっと、待って、待っ…て……。
「来い」
迸る瞬間に最大限の力を発揮して拡散した勢いが、最後の躊躇をも突き崩しなぎ倒して諸共に至らせる。
熱く噴き出し溶け出す流れが、もたらされたものなのか自らが融解したものなのか、もうわからないほどにまで。
目が眩むような閃光に射抜かれて一つに重なった胸が同じ鼓動を打っている。
あぁ。もう……このままでいたいわ。それでいいでしょう。
どちらがどちらのものでもない。もう離れられない。
こんな思いをさせるなんて。もう。赦してあげない。放してあげない。
まだ続いている、その脈が
最後の一滴まで吐き出して鼓動を止めるまで。
肩を掴んだ手がずるりと滑って力をなくす。転落してしまう…果てもなく。
このまま目が覚めたら消えてしまう、なにもかも。
今感じている、包み込まれている温もりも冷たい塊となって終わる。
――だからもう目を開けたくない。
停滞した世界のうちにまた失ってしまったものの数など確かめても意味がない。
待ってなどいられなかった。後にとっておいたりできなかった。
欲しいものはすぐに手に入れなければ気がすまなかったのだ。
重なる胸の間に隙間が生じ、汗に濡れた皮膚に冷たい空気を感じたと思った瞬間に
しっかりと抱きとめられた。
静かな呼吸を感じる。
その唇の形に触れていると、爪の先に噛み付かれた。
それだけの元気が残っているということか。
目を開け、ぐったりと弛緩した表情の吸血鬼をそこに見出す。
「ご気分はいかが?」
「…悪くない」
「それだけ?」
「…かなりいい」
「かなりね」
「最高だ、……と言ってやってもいい。今日目覚めてからは」
「目覚める前は?」
「夢の中だ」
「あら、夢は見ないと聞いたけど。何の夢?」
「知っているくせに」
「知らないわ」
「それなら、君には教えられないな。昼も夜も悩ませられる悪夢、と言っておこう」
「……うんざりしちゃうわね?」
「まったくだ」
私を求め、私を夢見ずにはいられないほど、その永遠とは暗いのか。
「心の底から同情するわ。でも私はご機嫌なの。寝かせておいた極上のボトルの栓を抜いた気分」
「で? どうだった……見掛け倒しか?」
「そんなに得意げな顔しないでよ。虐められたいの?」
反発しようとした開きかけた口が、黙って満足そうに閉じられる。
見つめていると、その瞬間が甦ってくる。こみ上げる感覚に思わず息をつく。
ぁ…。身動きすればこの手の内からこぼれすり抜けていってしまう……
あなたをこのまま捕まえていたいのに。
「あ、デミトリ…まだ……、まだ、抜いちゃいや」
感極まったように強く抱きしめられて、身悶えた一瞬のうちにやはりそれは抜け去ってしまった。
「あぁ…ん」
心残りの色を見た吸血鬼が、威厳を保って告げる。
「……おかわりをお持ちしよう。しばしおとなしく待ちたまえ」
「うふふ……負けず嫌いなんだから。知らないわよ。どうなっても」
*
夜明けが来る前に、その唇が、何か決定的なことを言いだすような予感がしていた。
わかっているなら言わないで。そこに踏み込んだら終わりだから。
彼の目が訴えるのを見た。言葉にして言うべきではないことを。
行くな。全てをやるから。私の元から去らないでくれ。と。
「楽しみは後にとっておくものじゃなかったの?」
跨いで、三本目を抜く。彼の気が変わったりしないうちに。
異論はなかった。
口金を外されて、内側から湧き上がる活力が早くも押し上げる勢いを手の内に感じる。
閉じ込められていた想いの圧力が高まり、栓が膨らんで盛り上がる。
一度に暴発させないように細心の注意を払いながら
手のひらでその抵抗力を味わい、愛おしいものを慈しむ。
「どうしよう? 今のあなたって本当に……、とってもスウィートだわ」
「…たまにはいいだろう?」
「そんなことでは、悪い魔物の格好の餌食ね。遠慮なく頂戴するわよ」
「ふ…好きにするがいい……気の済むまで」
その目があの時と同じく、陶然として指の先を眺めている。
「やっぱりこうして欲しかったんじゃない…」
頬をつつき、下唇を噛んで引っ張ると低く唸った。
「いいこと? 目を閉じてはだめよ、最後まで」
息を吐き出して瞬きする。それは一体抗議なのか承諾なのか。
ふふ。いつまでもつかしら。
どれほどのものか、
あなたがひとときの夢に陥落し膝をつくまでは。
私がその瞳の焔に永遠を見出し、全てを委ねて酔っていられる間は。
精命の純度を世の時間の尺度で測ってみても仕方がない。
500年も続かないことは知っているのだ、そんな単位でないことは。
500秒? 300秒?
もしかしたら、その半分でも足りてしまうほど?
そうして、彼は来た。変わらずに熱く、意外にゆるやかな流れで。
ついにはその両目を閉じて。
グラスの内側をゆっくりと長く跡を引いて垂れ落ちていく濃厚なワインの脚のように、
その想いがこの内面の襞と隔たりを埋め尽くして幾筋も流れていく。
白く瞼の裏を灼きながら。
抱きしめられる。二度と放すまいとするように。
愛しい…、私だけのもの。
えもいわれぬ至福の味がする。
それもそうだ。たとえ瞬き一回の内のうたかたであろうと
至上の夢を――闇の祝福を受け世界を約束されたこの私を、
その胸に抱いている限りは、彼こそがこの世の全てを許された最も幸福な者。
2006.03